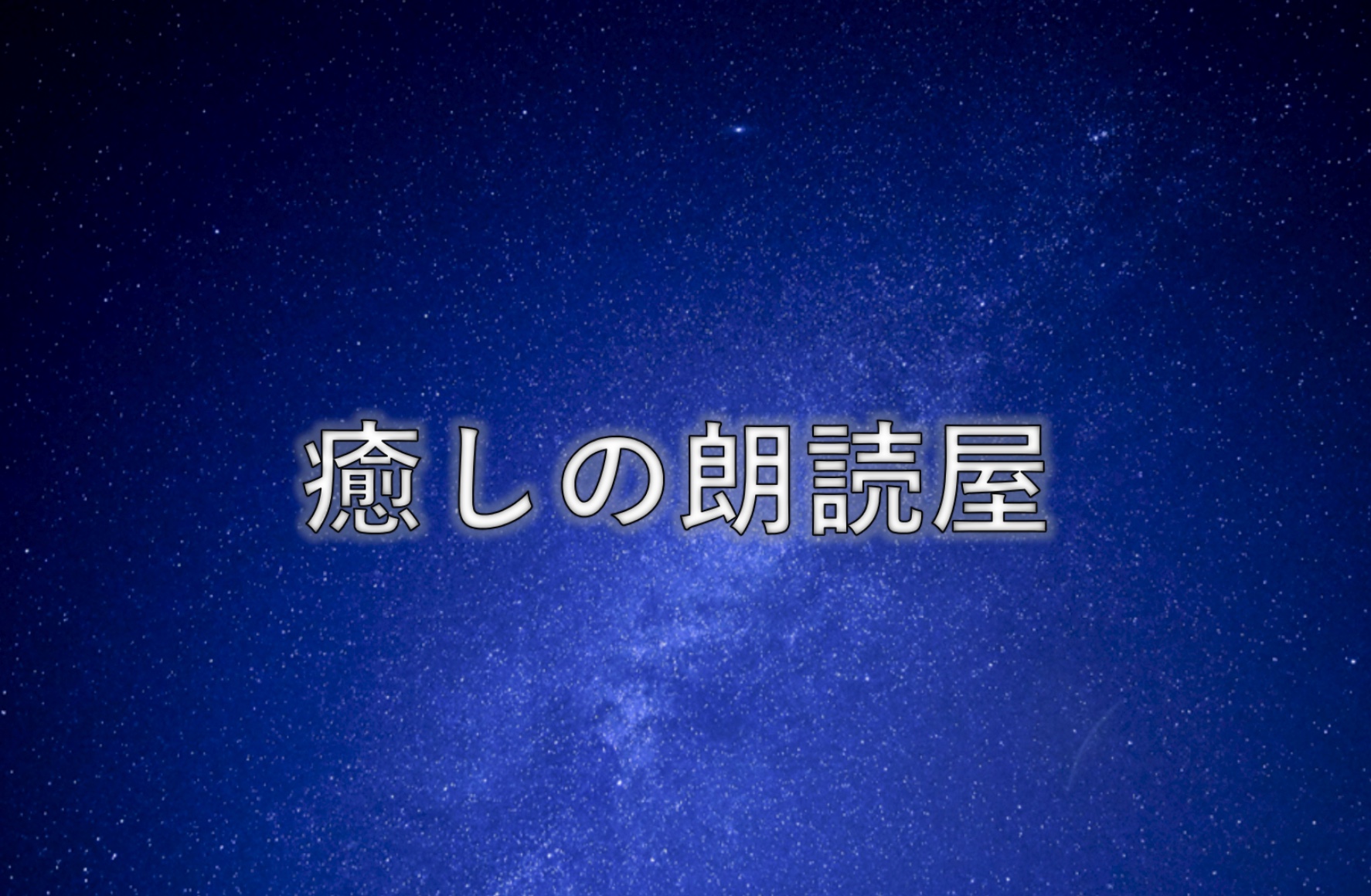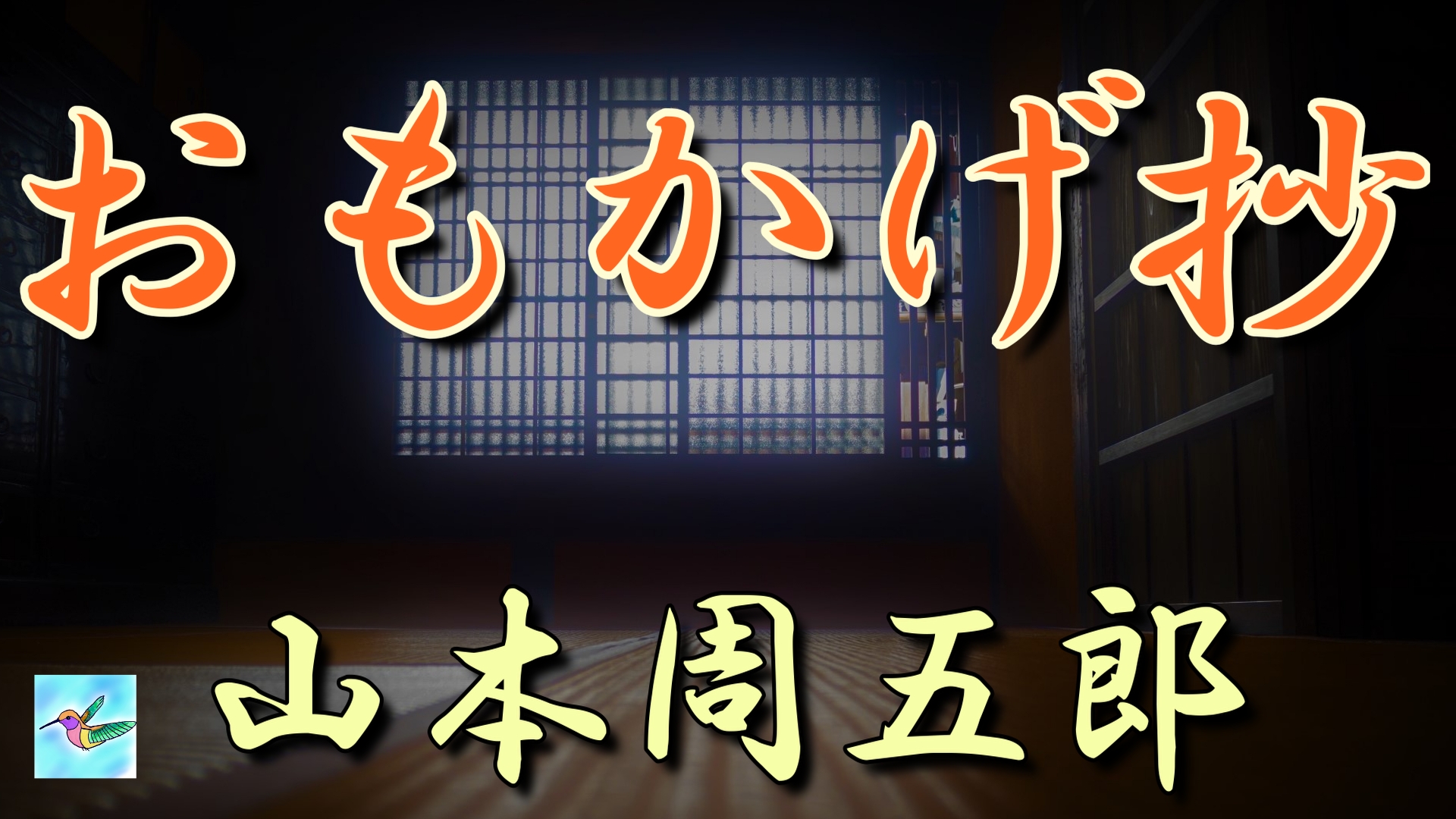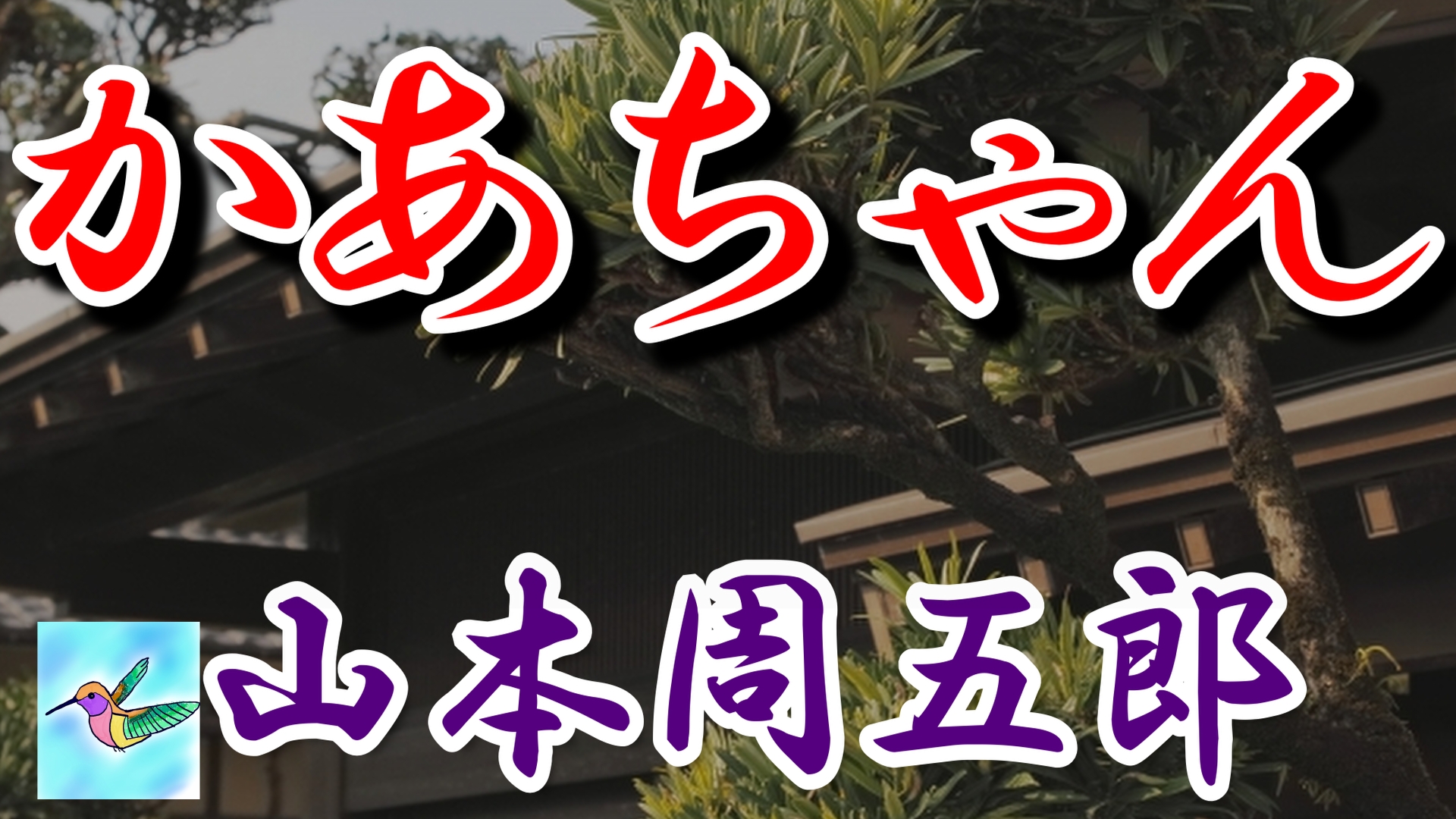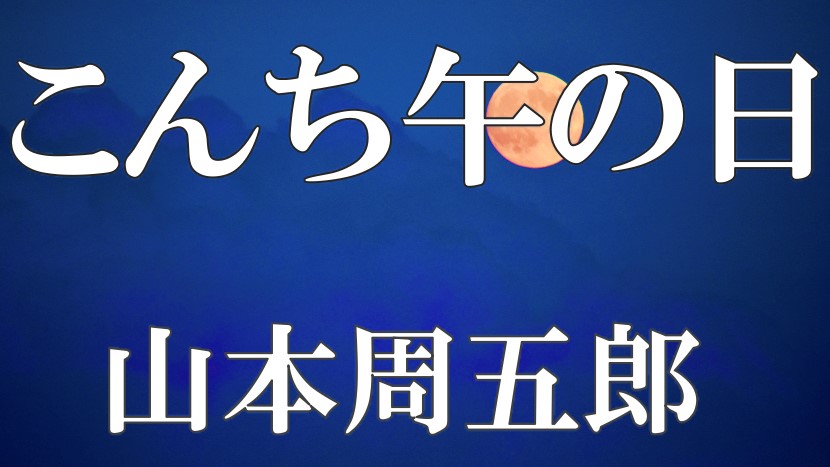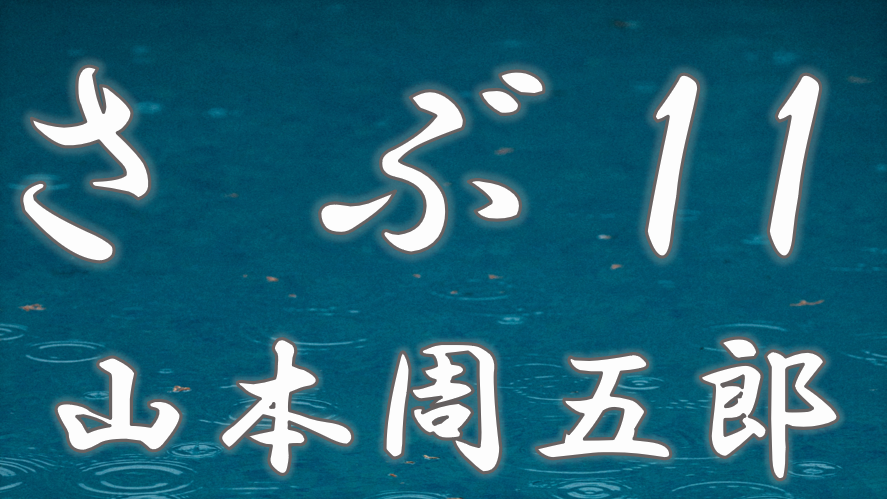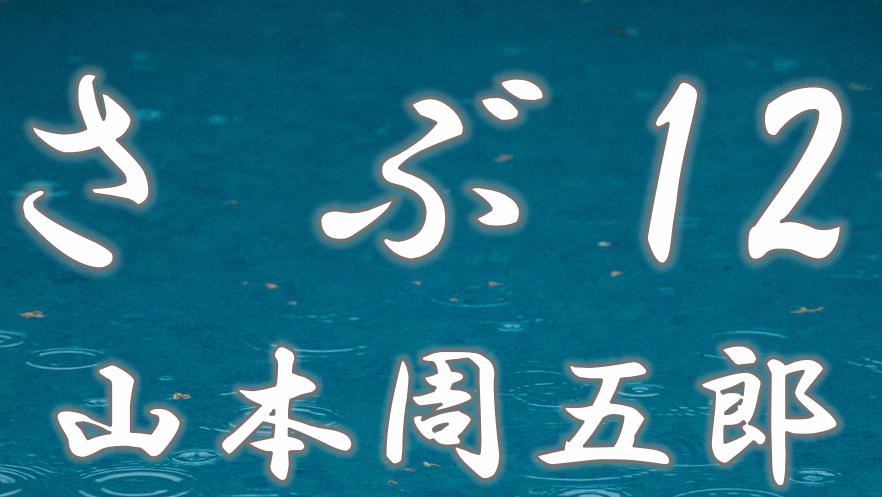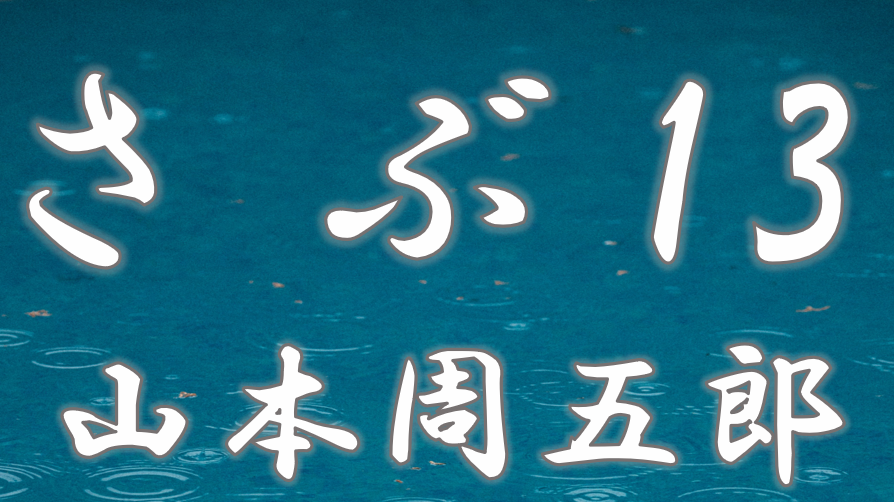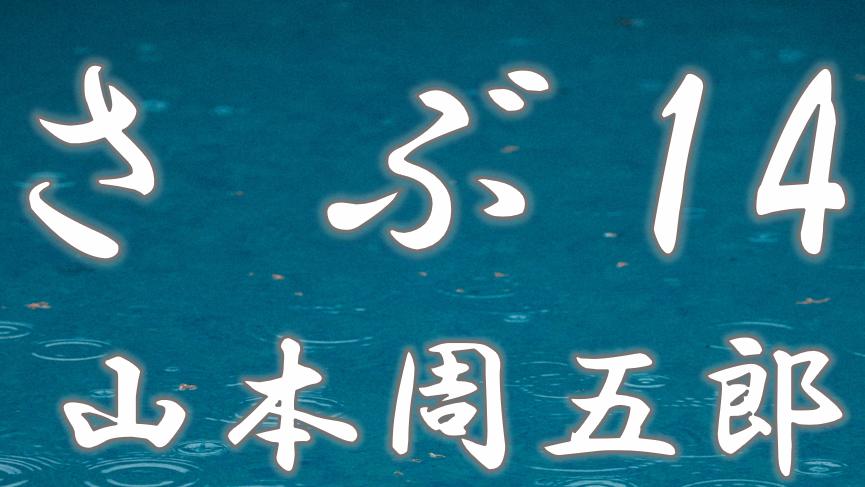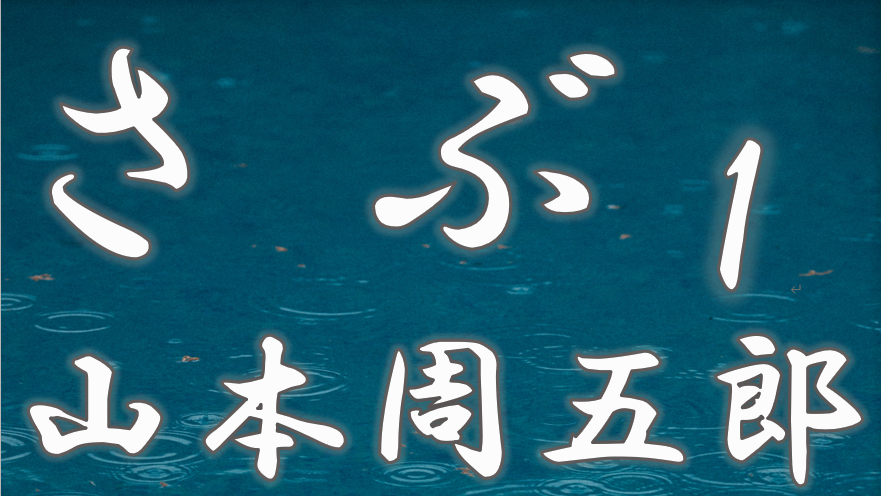【朗読】おもかげ抄 山本周五郎 読み手アリア
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「おもかげ抄」です。この作品は昭和12年キングに掲載されました。旧題は愛妻武士道です。遠州浜松の城下町を舞台に主人公の浪人、鎌田孫次郎は、甘田甘次郎と呼ばれるほど妻に優しく深い愛情で尽くしています。彼の誠実な心と、彼を取り巻く人々の温かな交流がとても心に響く作品です。
おもかげ抄 主な登場人物
鎌田孫次郎・・・二十八、九、上背のある立派な体つきで、色の浅黒い目の涼しい美男。誠実な性格で知られている。
六兵衛・・・「猪之松」の隠居。孫次郎を気にかけ寺子屋を作る。
沖田源左衛門・・・井上播磨守の家臣、大番頭。孫次郎の誠実な心と腕を見込んで息子の千之助に稽古をつけてもらう。
椙江・・・孫次郎の妻。気鬱症。美しく、孫次郎に深く愛されている。
千之助・・・源左衛門の息子。
小房・・・源左衛門の娘。
吉公・・・猪之松の口の軽い者。孫次郎を甘田甘次郎とからかう。
犬飼研作・・・浜松家中の武士。剣術の腕があり、孫次郎と剣術で対決する。
金八・・・魚売り。孫次郎を甘田甘次郎と呼ぶ最初の人。
おもかげ抄 アリアの感想と備忘録
この話を読んで一番心に残ったのは、やっぱり孫次郎の一途な愛と誠実さでした。遠州浜松の静かな城下町を舞台に、亡き妻への深い愛情とその愛情がもたらす悲しみと再生の物語。孫次郎の妻への愛は、単なる言葉や行動にとどまらず、彼の生き方そのものに染み込んでいます。彼の中に妻は生き続け、その姿を妻に見せるために彼は日々を送っています。この姿にとても感動させられました。物語の最後にようやく孫次郎が新たな人生を受け入れる姿が描かれ、哀しみから立ち上がり、再び愛を見つけたときにはホッとしました。二人が紀州に旅立つのは心の旅でもあり、過去と未来をつなぐ架け橋のようにも思いました。