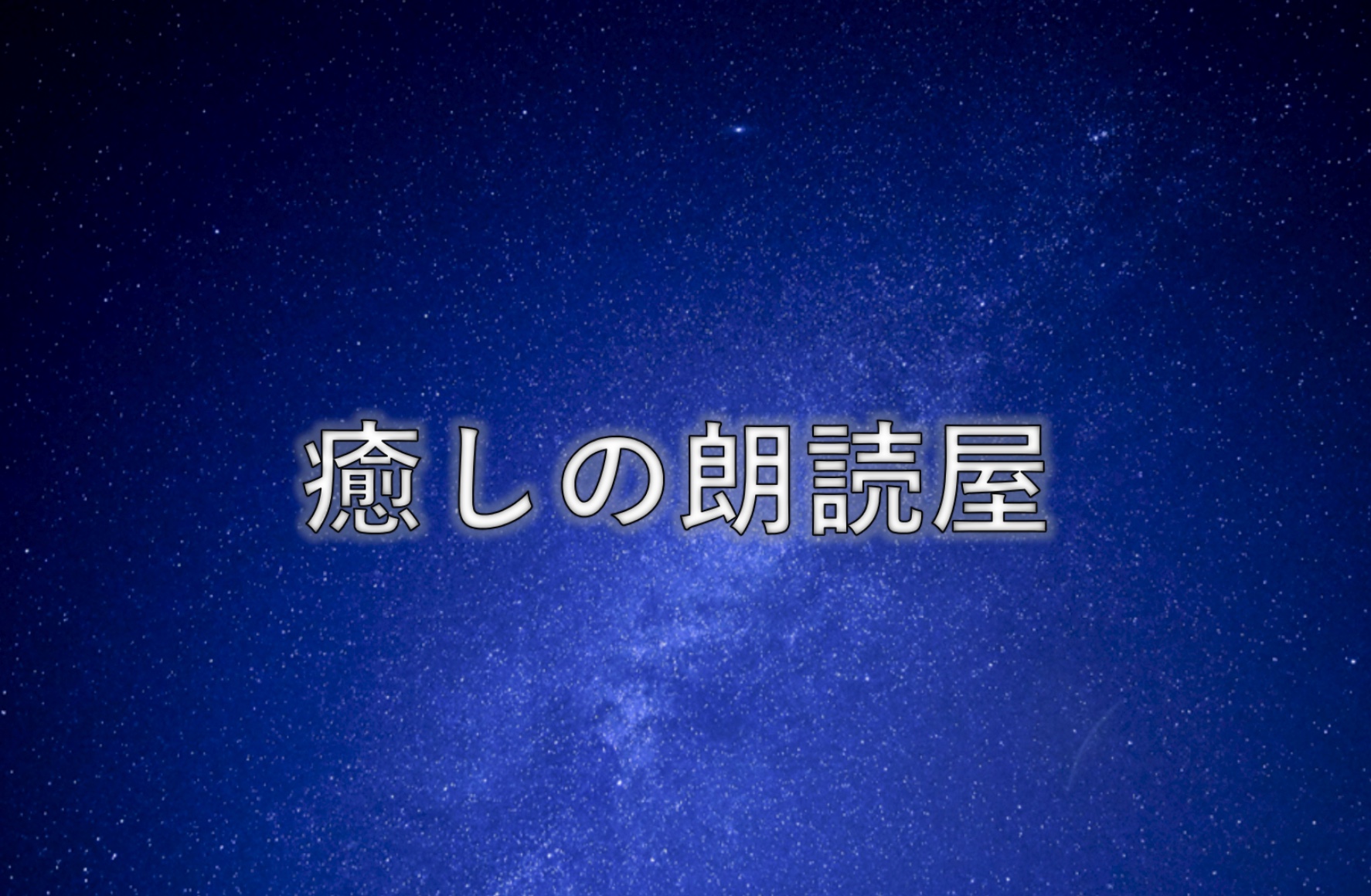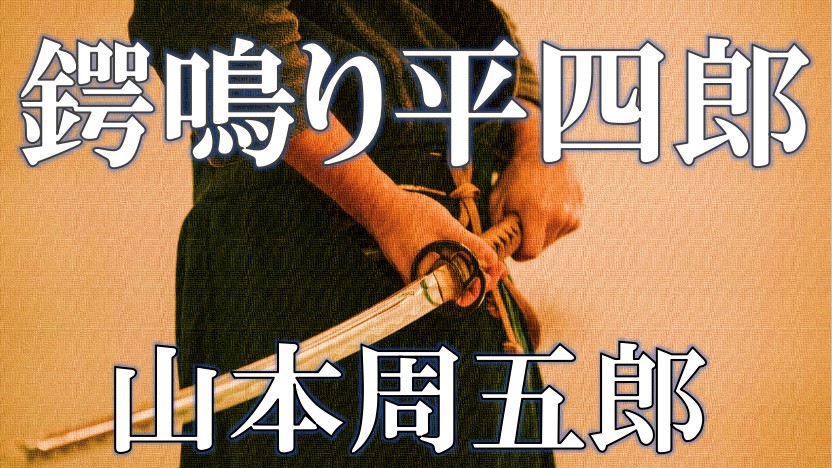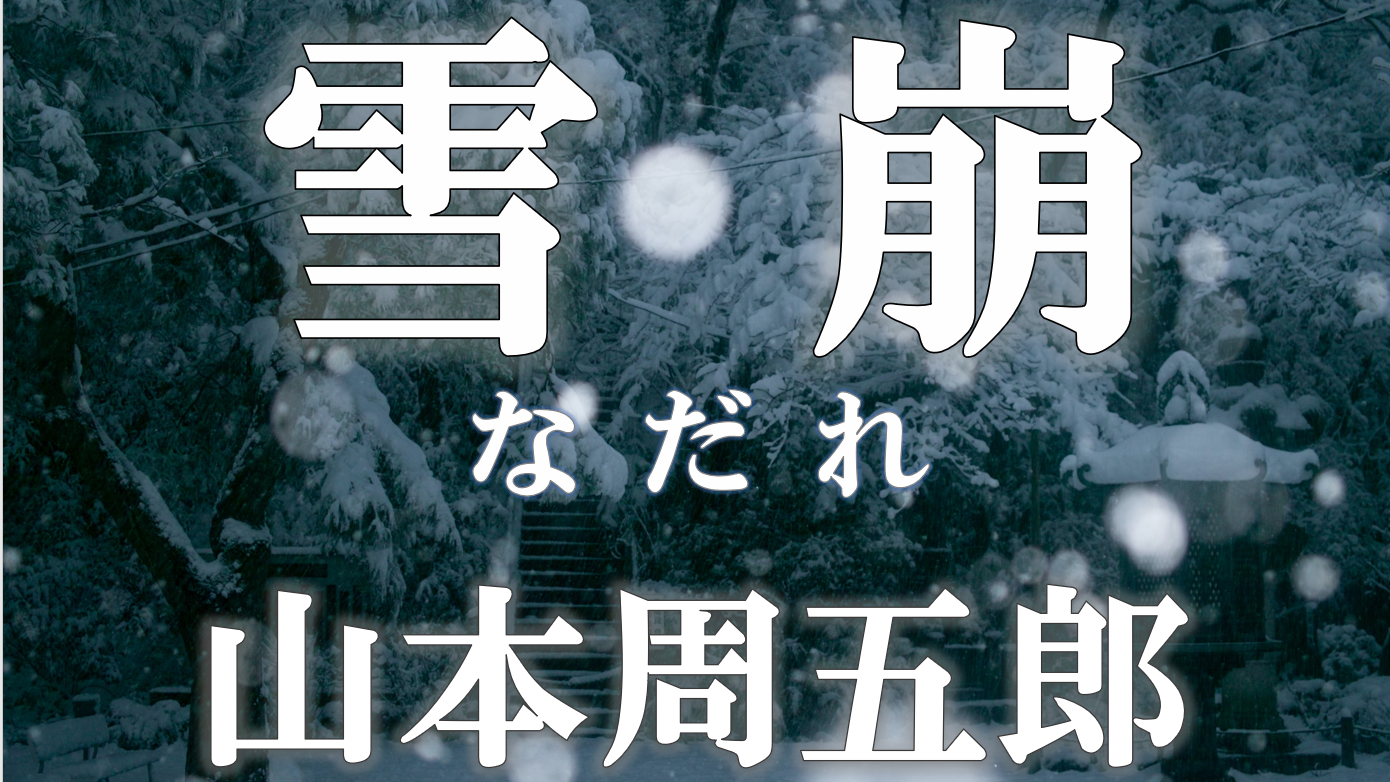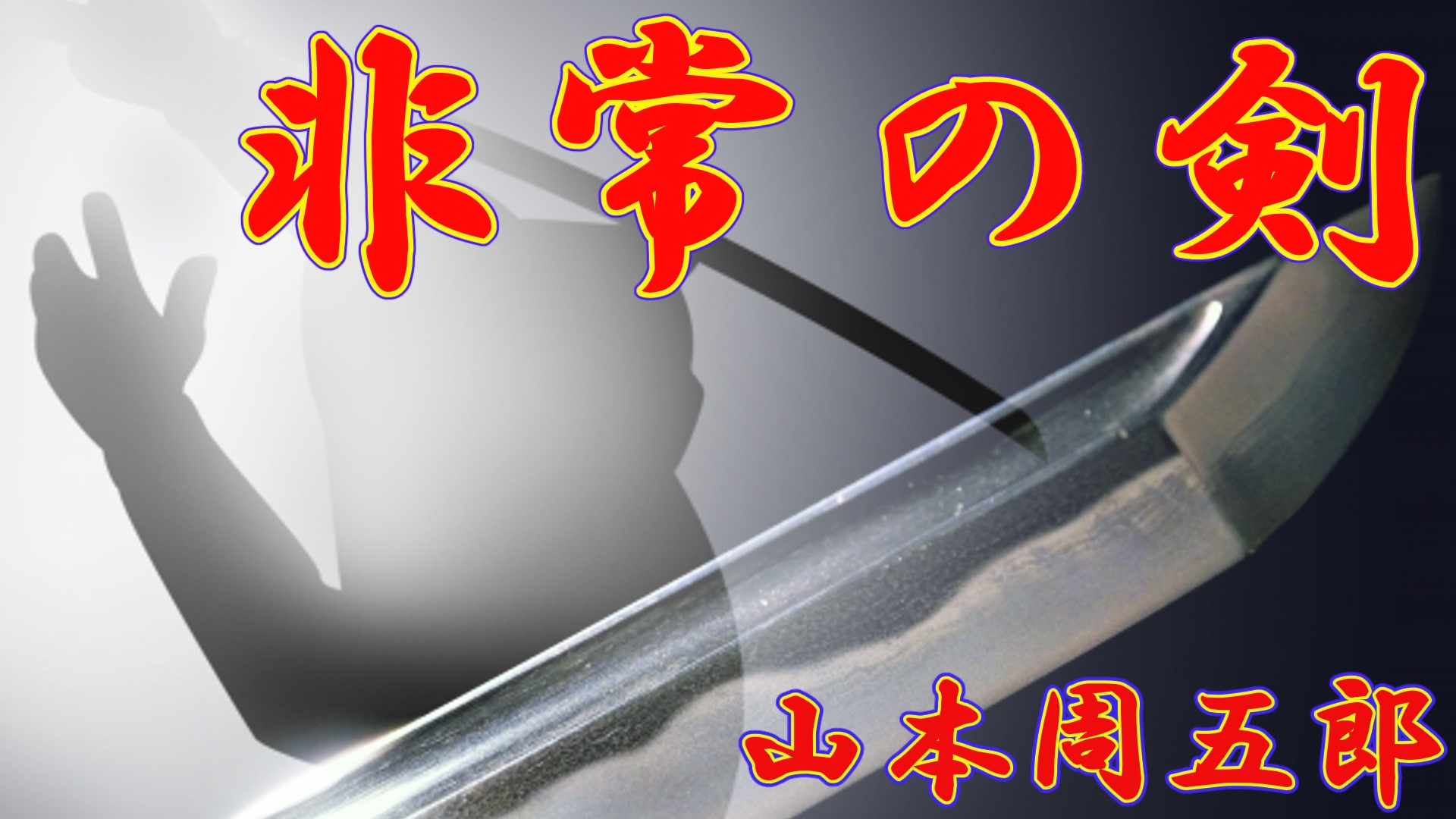【朗読】避けぬ三佐 山本周五郎 読み手アリア
避けぬ三佐 山本周五郎 あらすじ
冬の駿河国。屈強な武士・国吉三左衛門が、痩せこけた臆病な小犬を連れて悠々と歩いていた。彼は「避けぬ三左」と呼ばれ、どんな矢玉も、人の流れも、運命さえも避けることのない男だった。ある日、仲間から天気を問われるも、彼の返答は意外なものだった。「これから嫁をもらいにゆく」。彼が訪れたのは上司・大橋弥左衛門の家。戦の気配が漂う中、彼はあえて結婚を申し出た。理由はただ一つ徳川家が関東へ移封され、将来の戦いは長きにわたる。ならば、子や孫へと忠義を繋がねばならぬ。彼はまだ見ぬ女性を妻に迎えようとし、それが駿府で“かぐや姫”と称えられる絶世の美女・鷲尾小萩であることを知らなかった。しかし運命は待ってくれない。婚儀の前に、小田原征伐の出陣命令が下る。
避けぬ三佐 主な登場人物
- 国吉三左衛門(くによし さんざえもん)
徳川家の武士で、榊原康政の家臣。「避けぬ三左」「天気の三左」と呼ばれる豪胆な男。人や矢玉、雨さえも避けず、どんな状況でも「いい天気だ」と言う。徳川家の関東移封を知り、子孫に忠義を繋ぐために結婚を決意する。
徳川家の武将たち
-
榊原康政(さかきばら やすまさ)
徳川四天王の一人。三左衛門の主君であり、彼の覚悟を理解し、戦場でも特に気にかける。関東移封の意義を三左衛門に説き、新たな時代の到来を示す。 -
大橋弥左衛門(おおはし やざえもん)
榊原家の年寄(重臣)で、槍組の侍大将。三左衛門の縁談の相談を受けるが、彼の突飛な申し出に驚く。 -
鷲尾八郎兵衛(わしお はちろうべえ)
榊原家中の勇士で、三左衛門が結婚を申し込む小萩の兄。三左衛門の申し出を快諾し、戦場まで駆けつけて婚約の成立を伝える。
その他の重要人物
-
鷲尾小萩(わしお こはぎ)
三左衛門が嫁に迎えようとする女性。駿府で「かぐや姫」と称される絶世の美女。三左衛門は彼女の顔を見たことすらないが、兄の武名を信じて縁談を決める。 -
名もなき若侍たち
三左衛門に天気を尋ねる駿府の若侍たち。彼の変化に気づき、「まさか恋患いか」と噂する。 -
敵将・松田康長(まつだ やすなが)
北条氏の武将で、山中城を守る。最終的に討死する。 -
その他の徳川家臣
- 酒井忠次(さかい ただつぐ)
- 井伊直政(いい なおまさ)
- 本多忠勝(ほんだ ただかつ)
- 鳥居元忠(とりい もとただ)
- 大久保忠世(おおくぼ ただよ)
※いずれも徳川家の重臣で、小田原征伐に参戦している。
アリアの備忘録
三左衛門は、どんな状況でも決して避けない男。矢が飛んできても、人とぶつかりそうになっても、運命さえも逃げずに真正面から受け止める。戦場でも堂々と敵城の前に立ち、「降伏しろ」と叫ぶその姿は、まさに武士の理想だ。そんな豪胆な彼が連れているのは、痩せこけた臆病な小さな犬で、これはきっと彼の繊細さや優しさを象徴していたと思う。戦場では屈強な武士として恐れられる彼が、見たこともない女性を信じ、その未来を守ろうとする姿には、ただ強く戦うだけではなく、守るべきものを持つことこそが本当の強さなのだということでしょう。彼が「ああ、いい天気だな」という一言はただの天気の話ではなく、彼の心の迷いがすっきり晴れたことを示していた。この話は、どんな時代を生きる者にもどんな困難があろうと自分の道を信じて進め!と周五郎氏は云いたかったのだと思う。