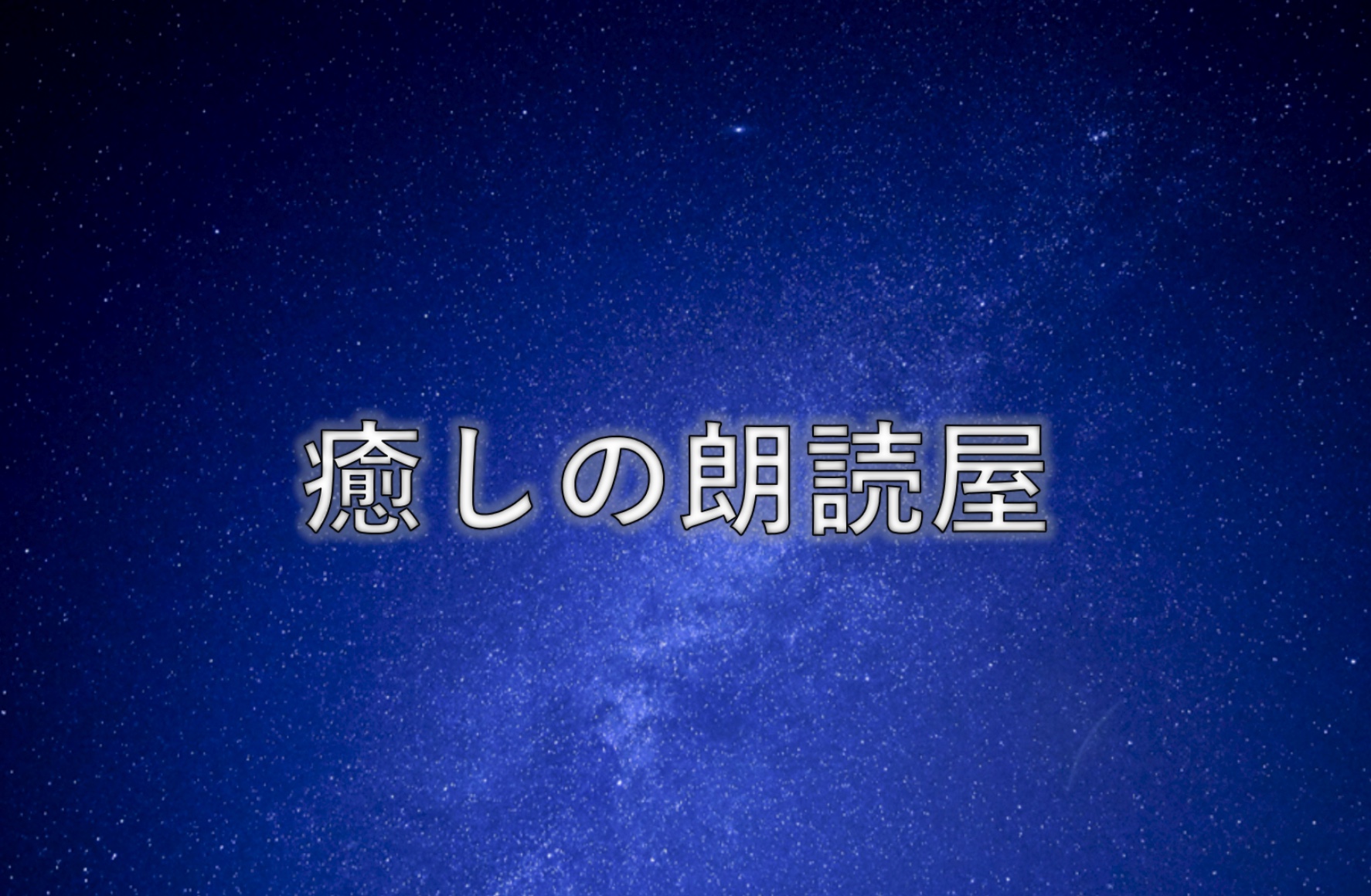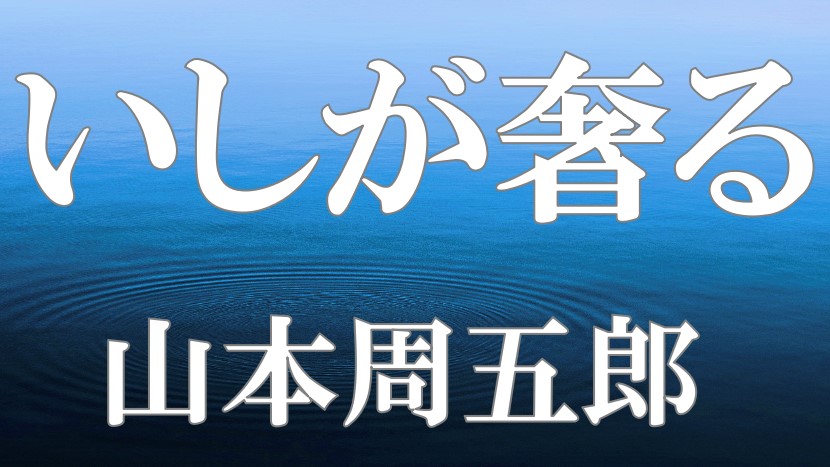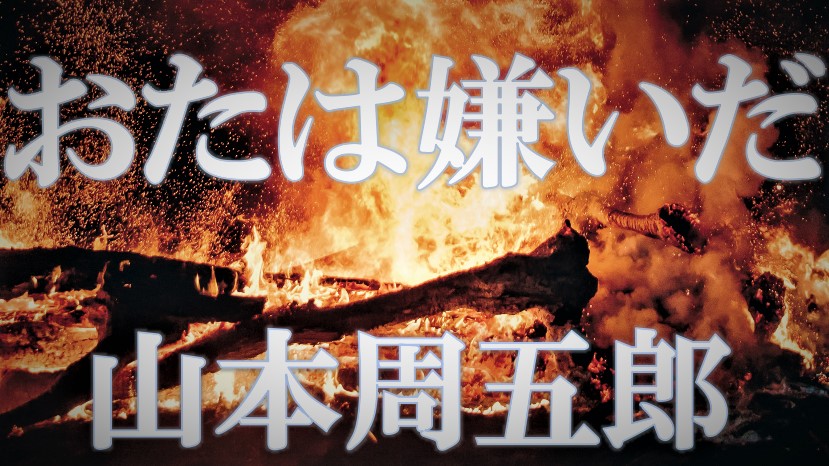【朗読】おたは嫌いだ 山本周五郎 読み手アリア
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「おたは嫌いだ」(昭和30年)です。(月の松山/新潮文庫)津由木門太が迷いながらも本当に愛する人を見つける話です。主人公・門太の心の中や一人ごとが多く書かれています。「おた」は双葉のことです。門太と双葉は幼い頃から仲がよく、まるで兄弟のように親しかった。双葉は自分のことを「おた」と呼び、門太のことを「もんたん」と呼んだ。
おたは嫌いだ 主な登場人物
津由木 門太・・・二十六歳独身。馬廻りだが使番を命ぜられて普請小屋に詰めている。両親を失ってから、姉と叔母の小萩に育てられた。双葉(おた)と幼なじみ。
すみ江・・・もんたの姉。十四歳の頃、主殿に恋し失恋した。それ以来、奥女中に上がり、現在では中老となる。
税所主殿・・・年寄肝入。御印筐の出し入れの責任者。門太にすみ江の気持ちをきいてほしいと求婚を頼む。
双葉(おた)・・・二十二歳。勘定奉行の娘。門太の幼なじみ。十七歳で奥勤めにあがり、今はすみ江の下で奥方づきの部屋持ちになっている。
お銀・・・深川の料理茶屋の娘。門太が結婚を考える娘。
三浦信吉郎・・・門太の友達。のんべえだが酔うとべらぼうに強い。
おたは嫌いだ あらすじ(※ネタバレを含みます)
門太とおた(双葉)は四つ違いであった。門太が二十一になったとき、姉のすみ江が「双葉さんを嫁にもらう気はないか」と門太にきいた。門太は笑って「おたをですか」とききかえした。おたとしては嫌いじゃありません。しかし妻としては好きになれそうもないんです。小さいときからあまり親しくしてきたので、その、つまり他人のような気がしないんです。私にとっておたは妹みたようなものです。おたと結婚することは、私には妹と結婚するのと同じことなんです。それから五年経つ・・・双葉は十七歳で奥勤めにあがあり、現在では姉の下で奥方づきの部屋持になっている。姉は口には出さないが、二人の結婚をあきらめていないらしい・・
おたは嫌いだ 覚え書き
御印筐(ごいんばこ)・・・藩主対馬守の印章を入れた筐。月に一度ずつ、工事担当の大名三家から呈出する書類へ総奉行として対馬守が照合検印するもの。そのたびに宝庫から出し、すむとすぐに宝庫へ戻す。
部屋子(へやご)・・・江戸時代、大名屋敷で御殿女中に召し使われた下女。
かどわかす・・・だまして、女・子どもを連れ去る、誘拐する。
禁足(きんそく)・・・罰として外出を禁止すること。
無学文盲(むがくもんもう)・・・学問・知識がなく、文字が読めないこと。また、そのさまや、その人。
手合(てあい)・・・連中、やつら。やや軽蔑していう。
番太(ばんた)・・・江戸時代、町や村に雇われ、夜警や火事、水門などの番に当たった者。非人身分の者が多かった。
無腰(むごし)・・・腰に刀を差していないこと。丸腰。
風態(ふうてい)・・・身分や職業をうかがわせるような外見上のようす。身なり。
奇天烈(きてれつ)・・・非常に風変りであるさま。
無頼漢(ぶらいかん)・・・無頼な男。ならずもの。ごろつき。
のら息子・・・怠け者で遊び好きの息子。道楽息子。
練達者(れんたつしゃ)・・・熟練して深く通じているもの。
露顕(ろけん)・・・秘密や悪事など隠していたことが表に現れること。
壮観(そうかん)・・・規模が大きくてすばらしい眺め。
賜暇(しか)・・・願い出て休暇を許可されること。また、その休暇。
竜吐水(りゅうどすい)・・・江戸時代から明治時代にかけて用いられた消化道具。
呪詛(じゅそ)・・・神仏や悪霊などに祈願して、相手に災いが及ぶようにすること。
人心地(ひとごこち)・・・生きた心地。また、ほっとくつろいだ感じ。
業病(ごうびょう)・・・前世の悪業の報いでかかるとされた、治りにくい病。難病。
褒貶(ほうへん)・・・ほめることとけなすこと。事のよしあしをいう。