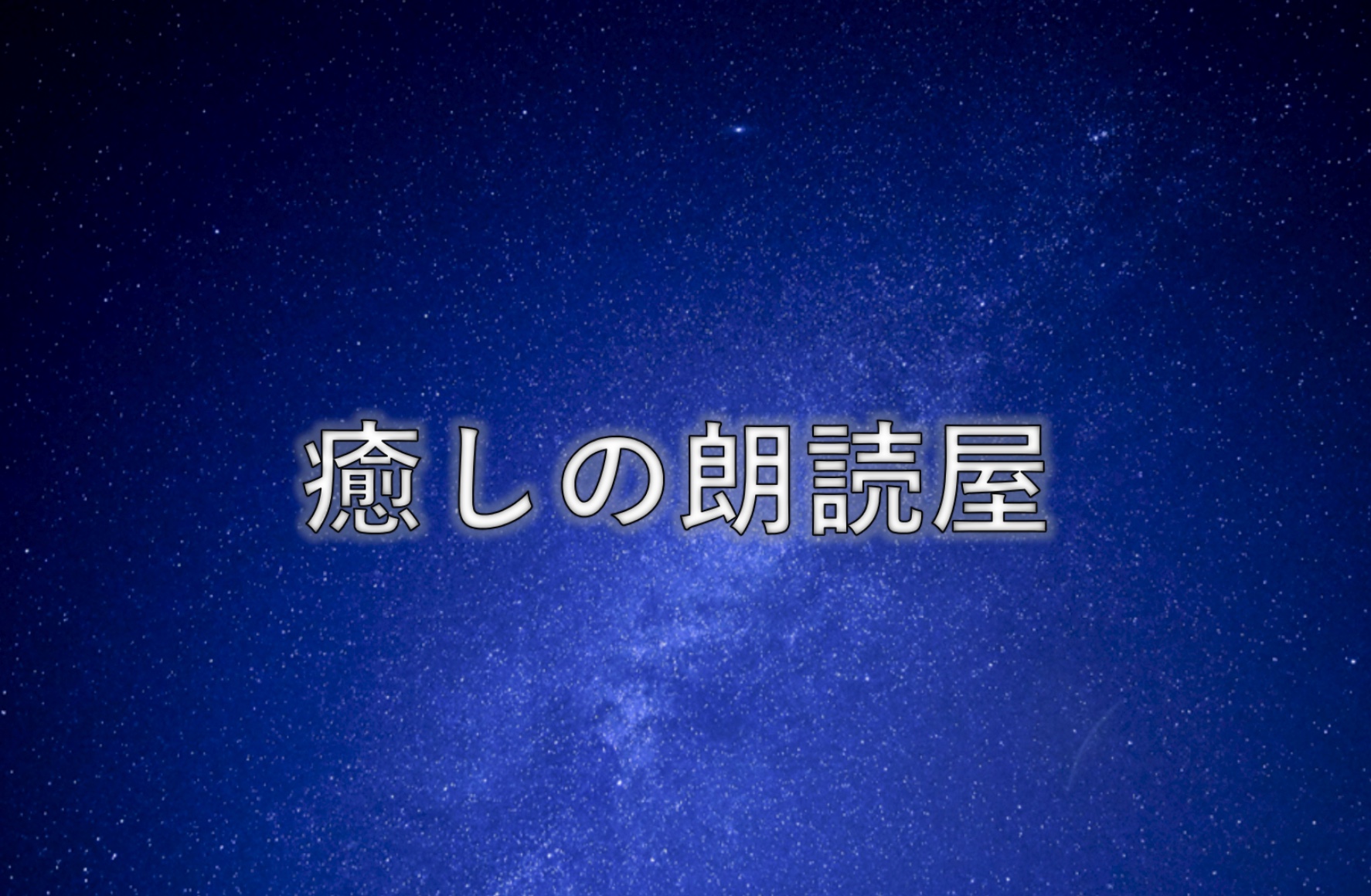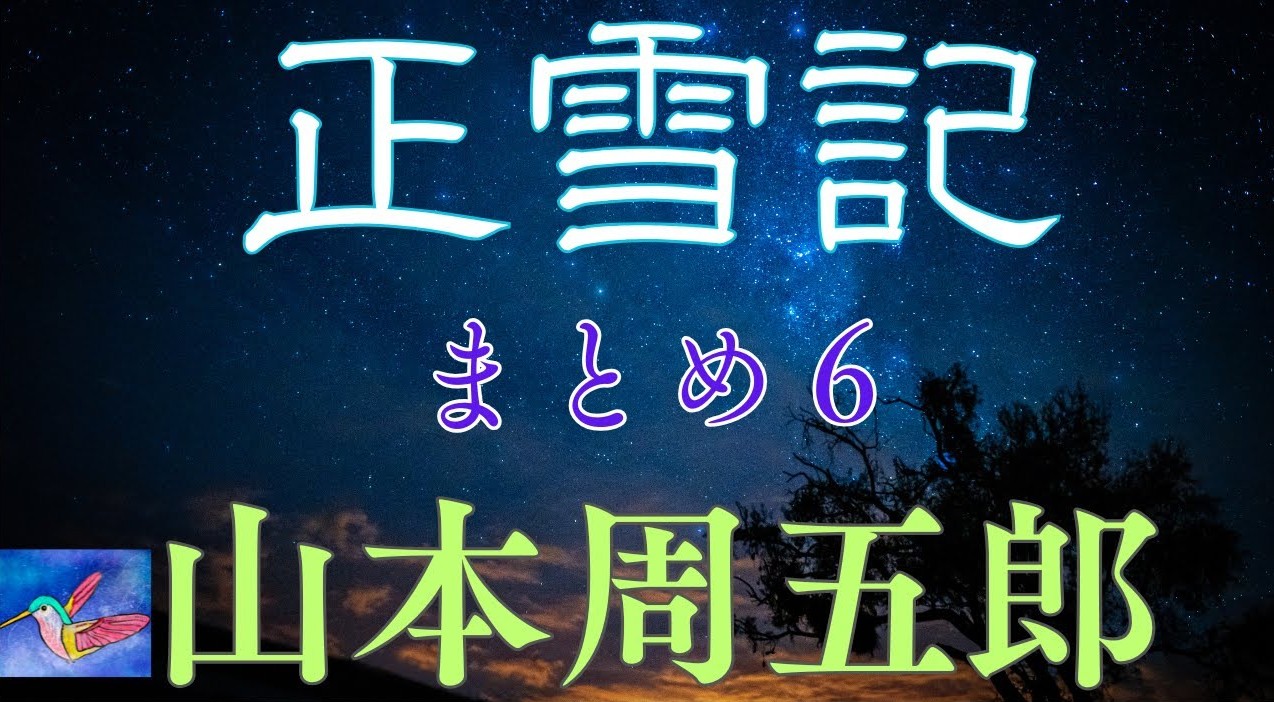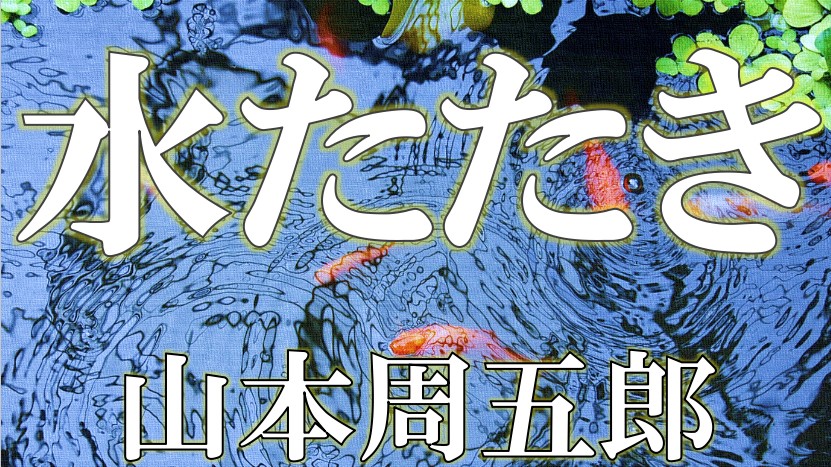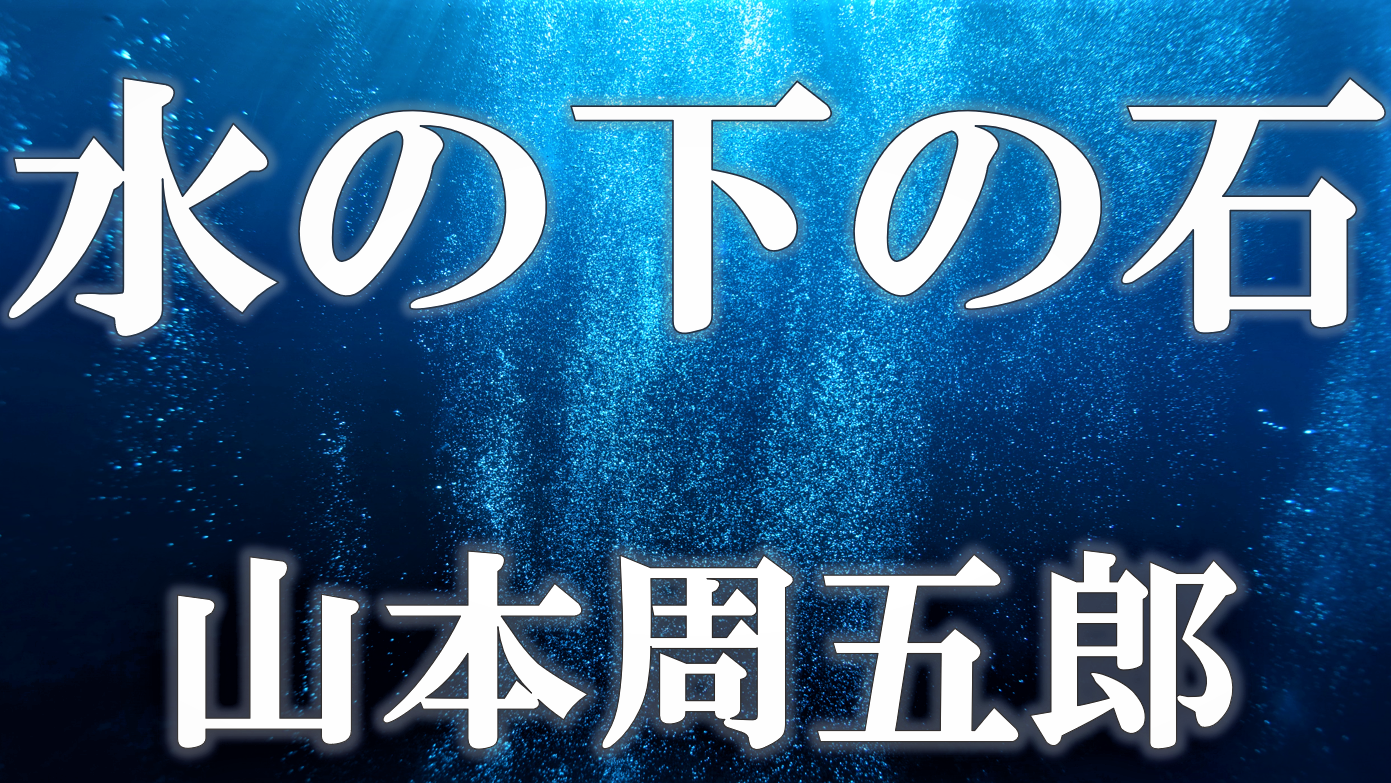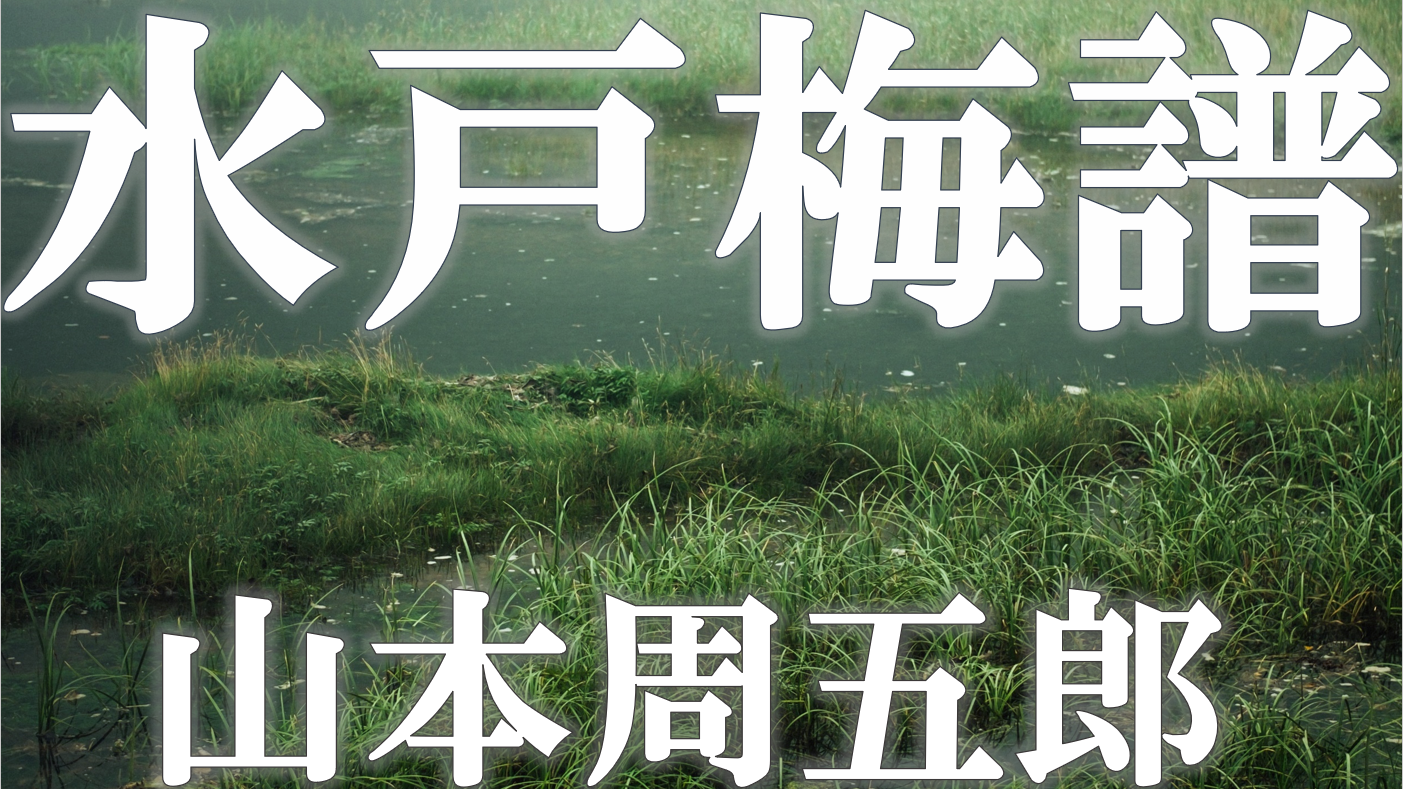【朗読】正雪記まとめ5 山本周五郎 読み手アリア
正雪記まとめ5 あらすじ
第1部8の1〜第2部1の3
夜明け前、与四郎は西へ向かう決意をし、小松と従者たちも後を追う。険しい山道を進むうち、猪之助は道の危険を訴えるが、与四郎は黙して答えない。森の奥深くで野宿した夜、小松はそっと寄り添い、「決してあなたを離さない」と囁くが、与四郎は冷たく沈黙する。
疲労と飢えが一行を襲い、ついに猪之助と藤吉は武器を取り、与四郎と対峙する。剣が閃き、猪之助は倒れ、藤吉も無力化される。狂気のように迫る小松を与四郎は突き放し、小松は「決してあなたを諦めない」と叫ぶ。
その後、傷を負った与四郎は意識を失い、隠れキリシタンの部落で救われる。そこで与四郎は、信仰に生きる人々の静かな暮らしを目の当たりにし、やがて天草の乱の勃発を知る。彼は運命を感じ、再び旅立つ。夜空には、御嶽山で見た自身の星が輝いていた。
正雪記まとめ5 主な登場人物
🔸与四郎・・・孤高の旅人で剣士。寡黙で冷徹な一面を持つが、内には強い意志を秘めている。小松や従者たちと山を越えるが、彼らと衝突し、ついには決別する。彼も傷を負い、隠れキリシタンの村で救われる。
🔸小松・・・名家勾坂家の娘。気高く、情熱的な性格で、与四郎への激しい執着を持つ。過酷な旅にも耐えるが、次第に精神的に追い詰められ、ついには与四郎に刃を向ける。最後まで彼を自分の手に入れることを誓う。
🔸猪之助・・・勾坂家に仕える従者。忠義に厚く、武術にも長ける。険しい道を進む与四郎に反発し、ついに戦いを挑むが敗北する。負傷し、与四郎の前から姿を消す。
🔸藤吉・・・もう一人の勾坂家の下僕。投げ笄の名手で、猪之助と共に与四郎と戦うが敗れる。戦闘の後、気絶して動けなくなる。
🔸増六・・・隠れキリシタンの部落・田島の長。落ち着いた人格者で与四郎を救い、信仰の教えを説く。やがて天草の乱の決起を知り、戦いへ向かう覚悟を決める。
🔸才助・・・増六の息子。父と共にキリシタンの信仰を守り、天草の乱への参加を決意する。
🔸天草四郎・・・神の使いとされ、キリシタン信徒たちを率いる。
ーその他ー
🔸シュモン善兵衛・・・隠れキリシタンの伝令。天草四郎の決起を知らせにくる。
🔸松倉氏・・・苛烈な統治を行う領主。一気の原因だと言われる。
🔸寄せての武将たち・・・幕府軍側の大名や武士たち。島原の乱鎮圧に動く。