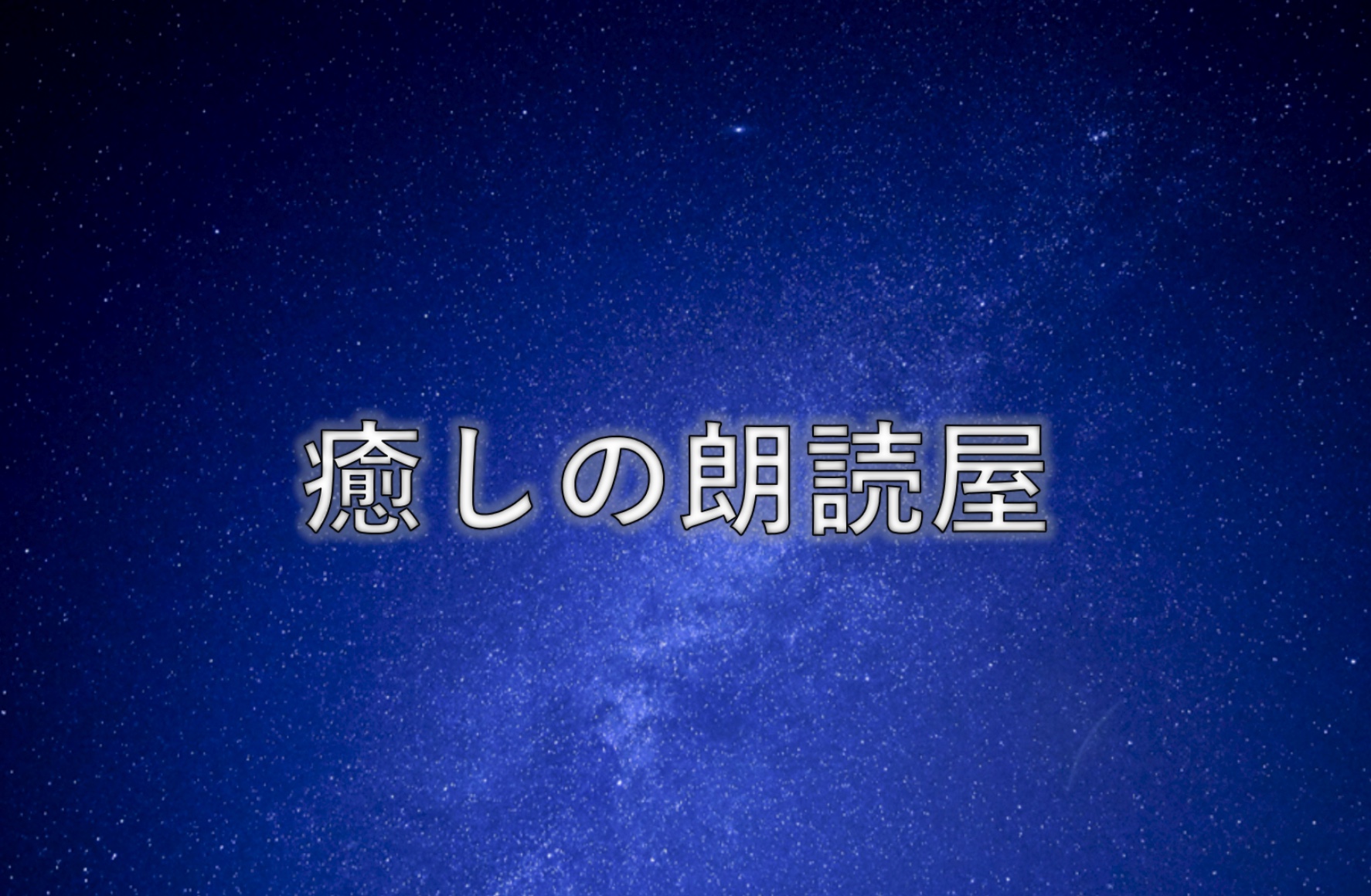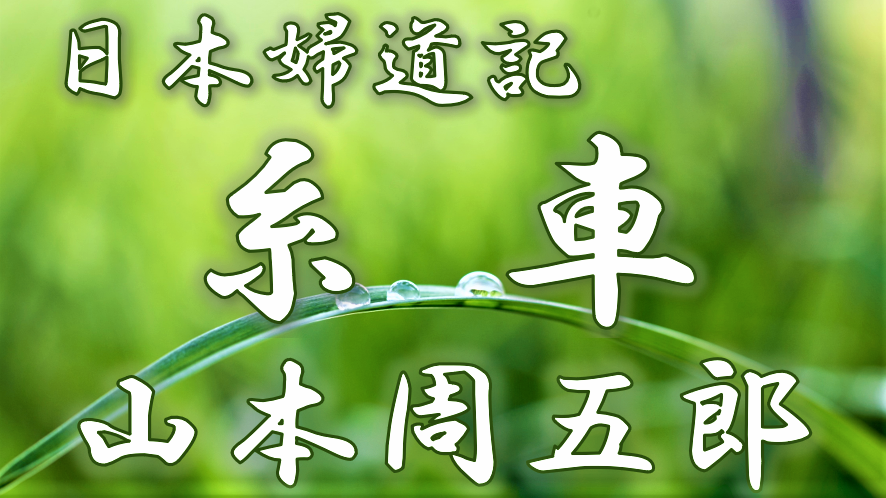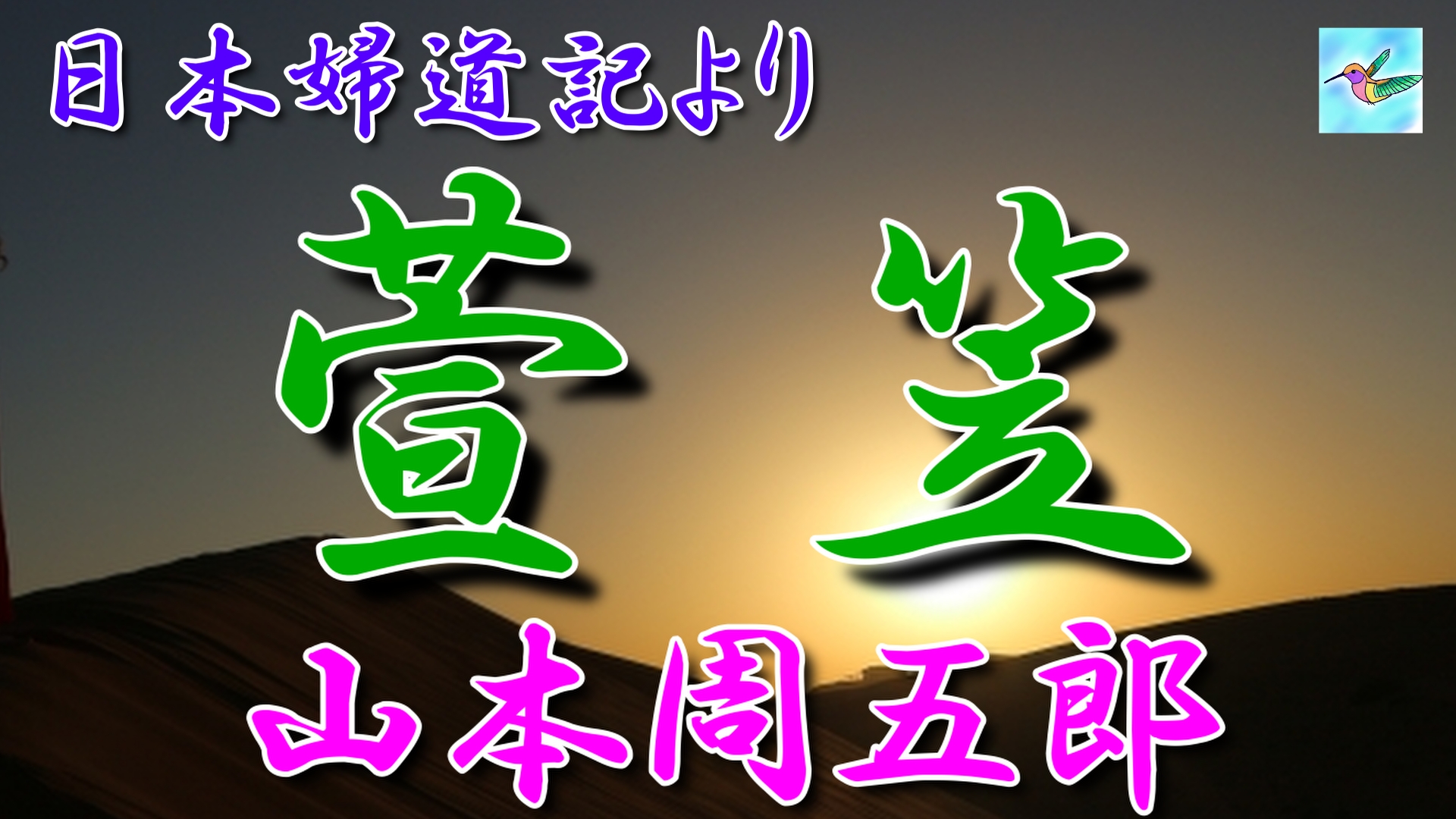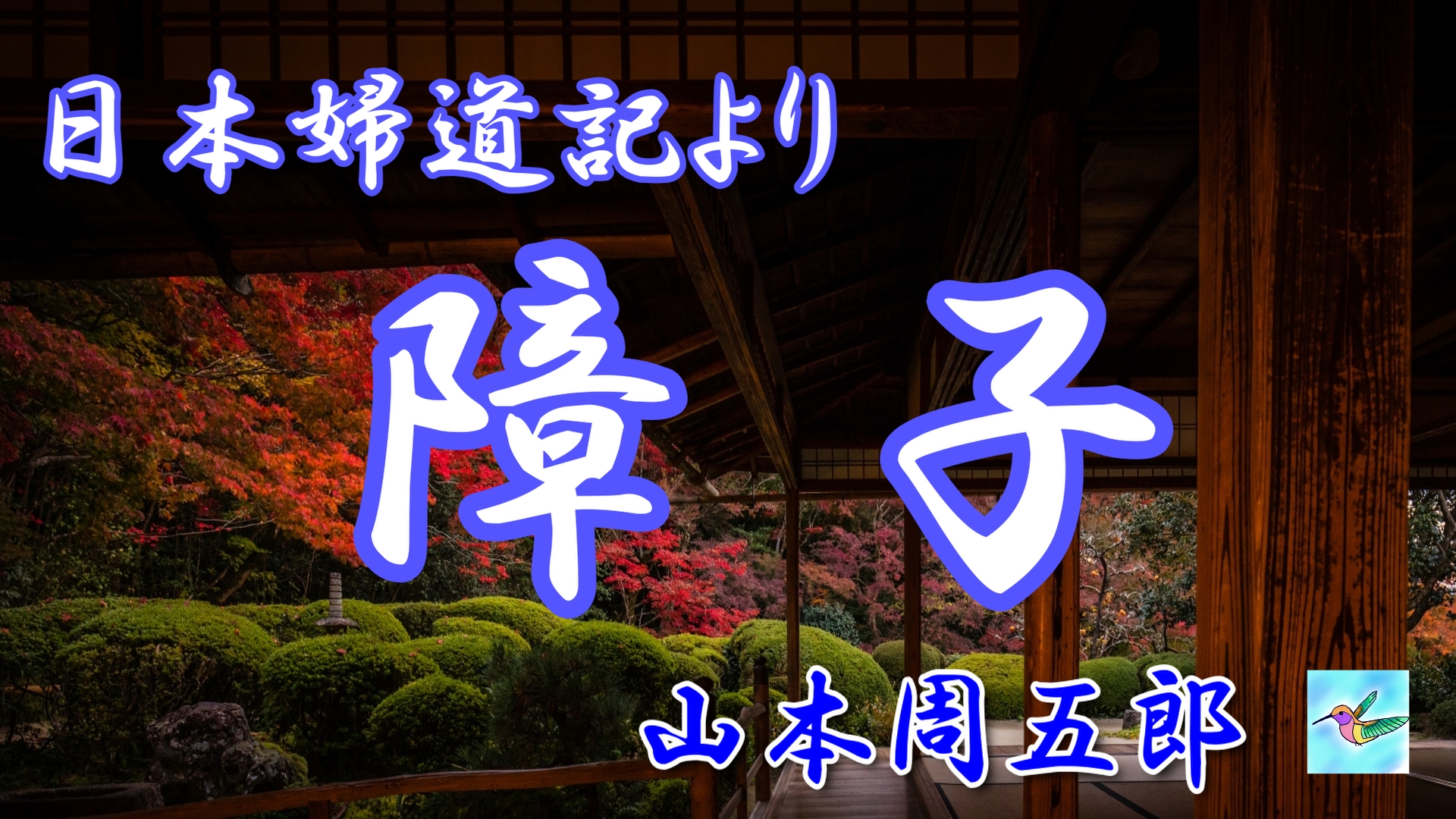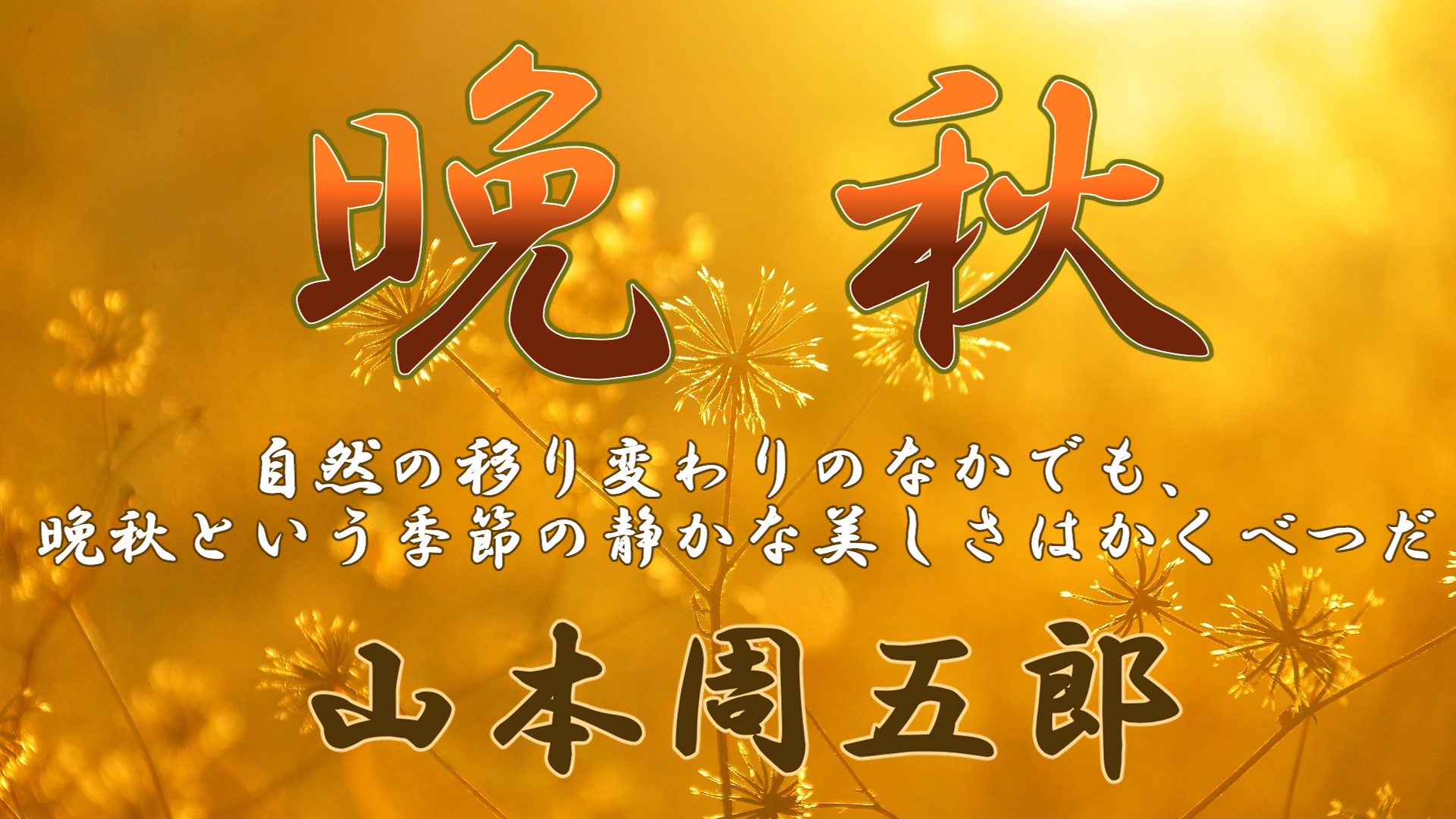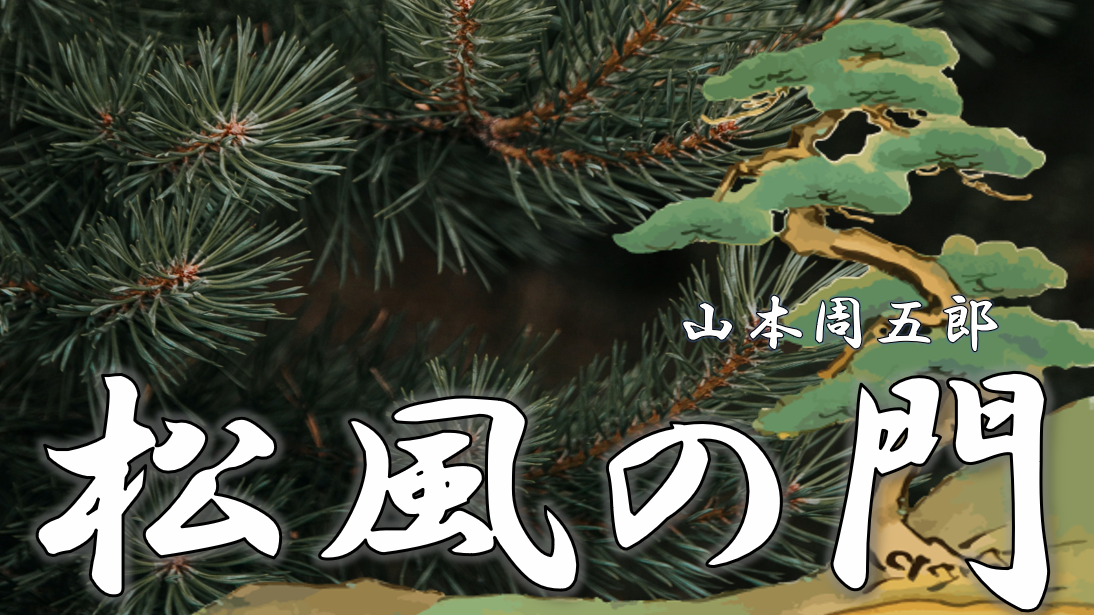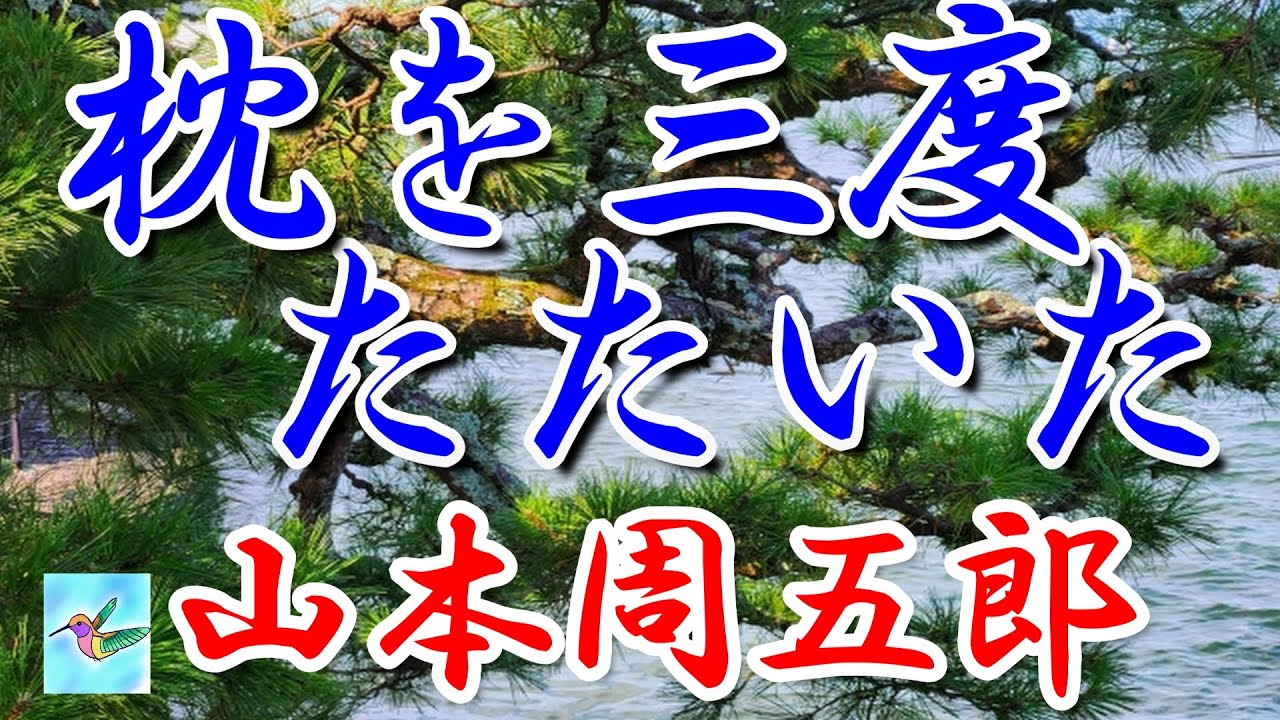【朗読】日本婦道記 糸車 山本周五郎 読み手アリア
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「日本婦道記 糸車」(昭和19年)です。今年十九になるお高は、松代藩につかえる今は病気で寝付いている父と幼い弟を抱えて、苦しい家計を支えるため、こまごました家事のいとまをぬすんで、松代藩の大切な産物、木綿糸をせっせと繰っては生計の足しにしていました。ある夜、父に呼ばれたお高は彼女の実の母親が思い病気にかかり、お高に一目会いたいので松本に来てくれるように云っていることを知ります。重い病に伏している産みの母のひとめ会いたいという言葉に強く宗を打たれたお高は、あとにもゆくさきにも落ち着かぬ気持ちで松代をたつのでした。家族とは何か、幸せとは何かを問う心温まるストーリーです。
日本婦道記 糸車 主な登場人物
お高・・・十九歳。父が倒れて以来、その看護や弟の世話、そして細々した家事のいとまを偸んで、せっせと木綿糸を繰っては生計の足しにしている。最近はその木綿糸を褒められることも多く、少しでもよい仕事をしようとつとめているお高にとってそれは何よりの喜びだった。
依田啓七郎・・・お高の父。松代藩につかえる五石二人扶持の軽いさむらい。温厚な人。二年前に卒中を病んで今は勤めをひき、寝たり起きたりしている。妻は松之助が三つの年に亡くなった。
松之助・・・お高の弟。十歳。名義だけ家督を継いでいるが、まだ元服もしていないのでお扶持は半分しかさがらない。
西村金太夫・お梶・・・お高の実の両親。はじめ身分が軽くたいへん困窮していたときにお高を依田へやったが、今は出世をしたのでお高を引き取りたいと考えている。
保之丞・・・西村の弟。まだ前髪だちで、お高の来ることに興味をもってお高に話しかけたり眺めたりする。
日本婦道記 糸車 覚え書き
魚籠(びく)…魚釣りの時に、魚をいれておく籠。
目笊(めざる)…編み目の粗いざる。
会所(かいしょ)…江戸時代に種々の目的をもって人の集会をしたところ。
家督(かとく)…相続すべき家の跡目。あとつぎ。
元服(げんぷく)…奈良時代以降、日本で成人を示すものとして行われた儀式。
扶持(ふち)…助ける意から転じて、武士が米などを給して家来、奉公人を置くこと。
素読(そどく)…意味の解釈を加えず、本の文字を読み上げること。
糸繰り(いとくり)…繭や綿花から糸を取り、より合わせること。またそれをする人。
行燈(あんどん)…照明器具の一つ。蝋燭や油脂をを燃料とした炎を光源とする。
小謡(こうたい)…謡曲中の短い一節を、謡うために特に抜き出したもの。
丹青(たんせい)…色彩
火桶(ひおけ)…木で作った丸い火鉢。
絢爛(けんらん)…華やかで美しいさま。
篤実(とくじつ)…情が深く誠実なこと。
情誼(じょうぎ)…人と付き合う上での人情や誠意。