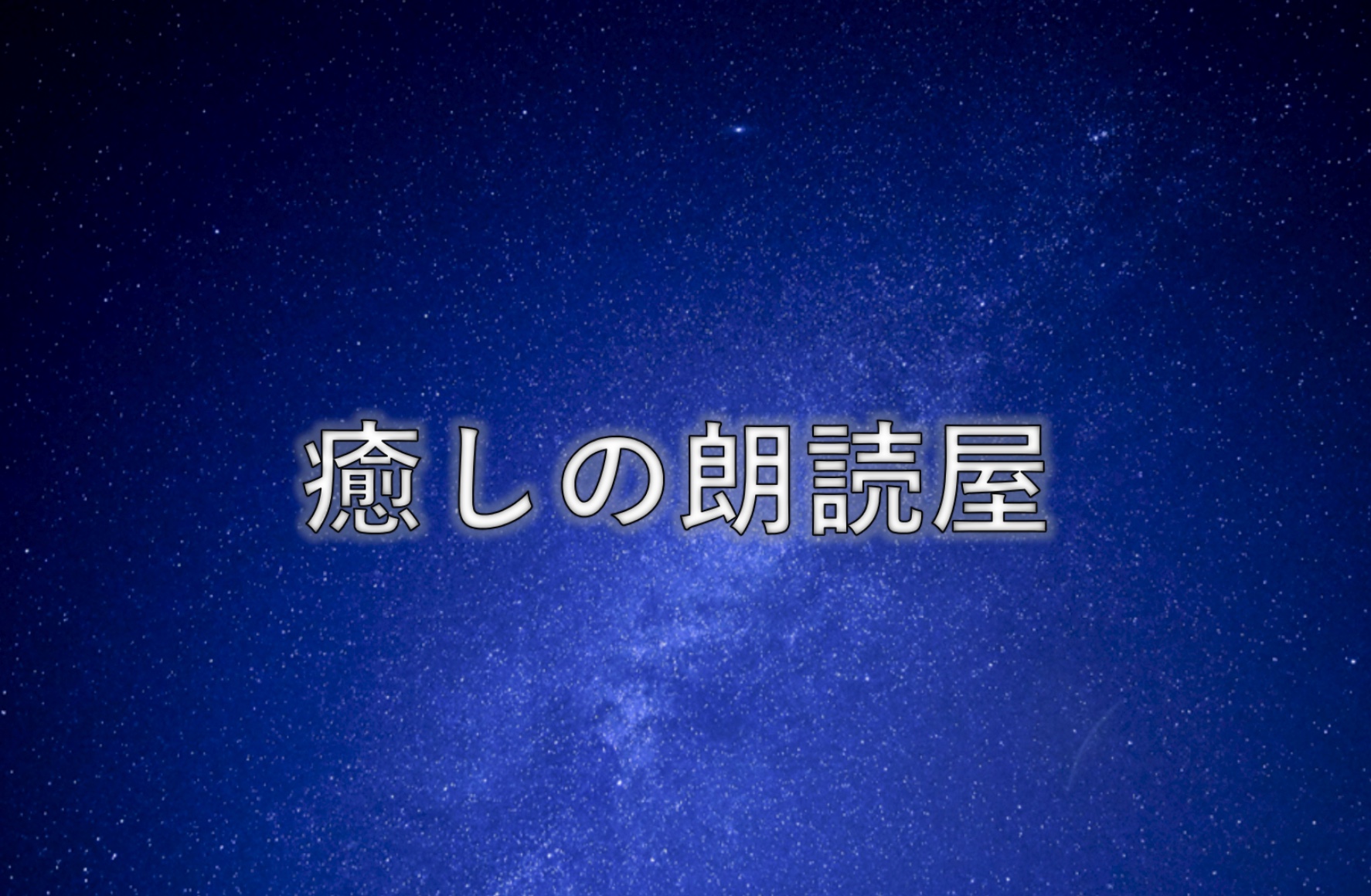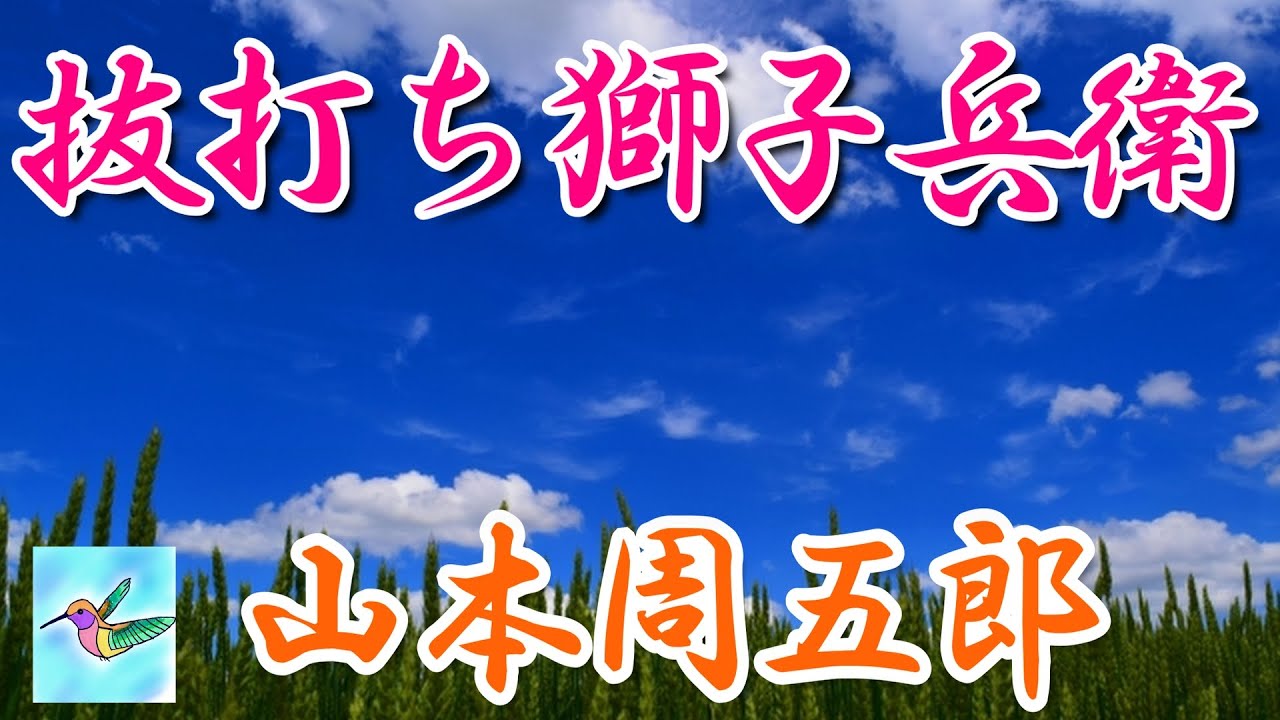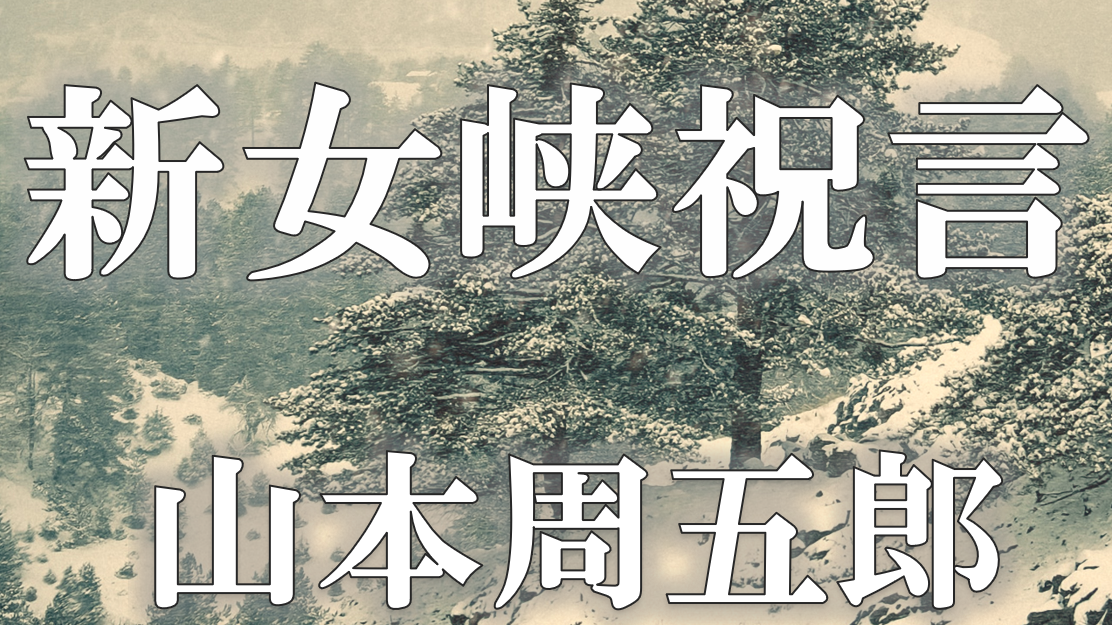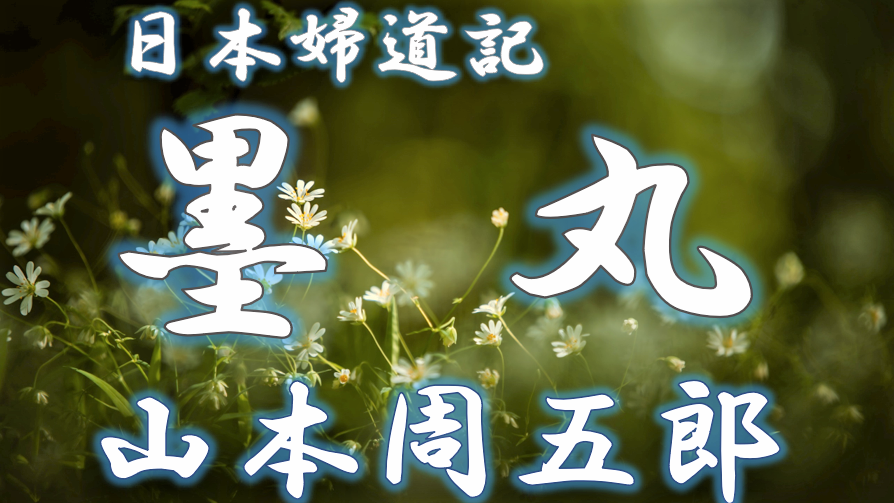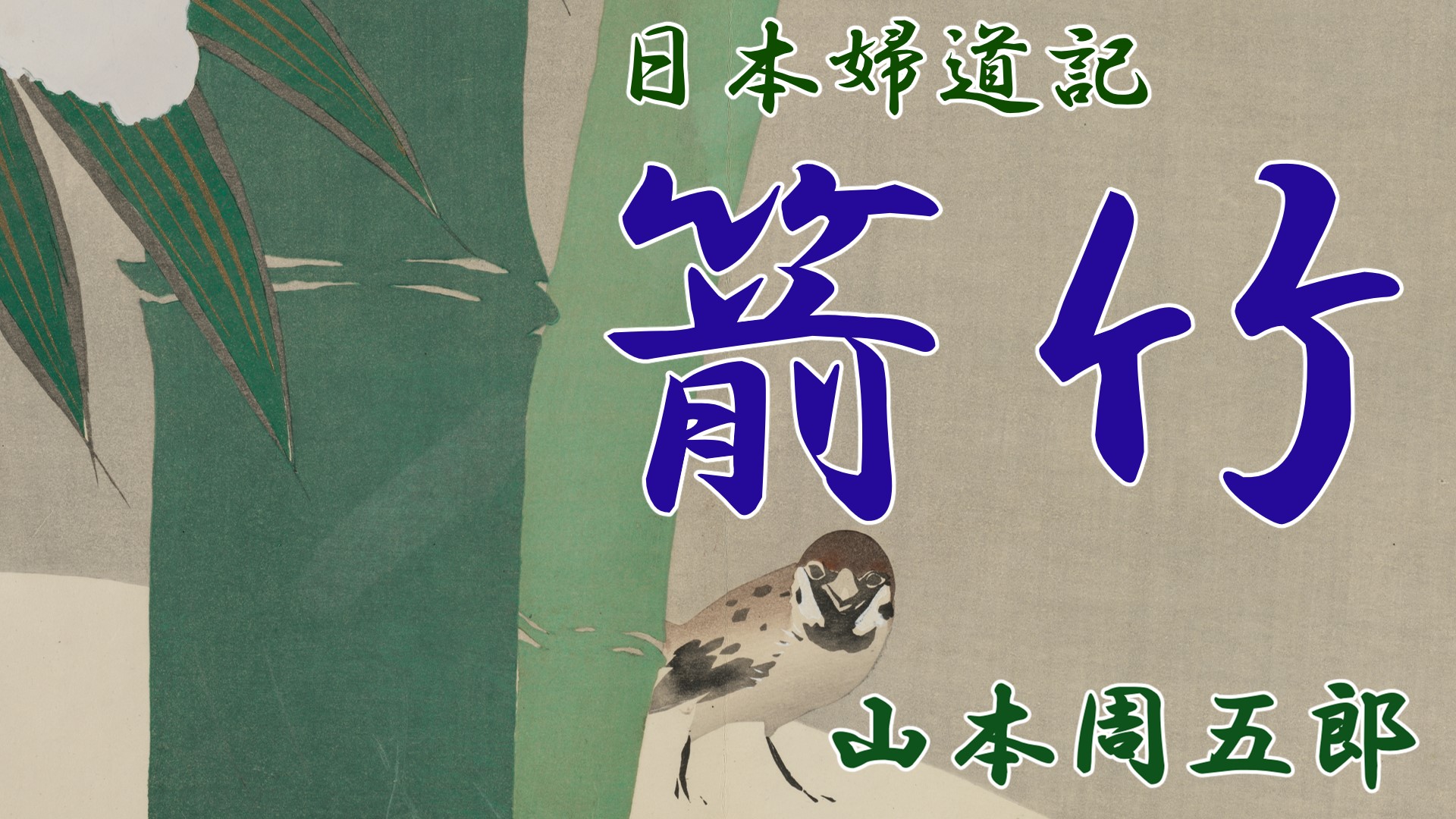【朗読】抜打ち獅子兵衛 山本周五郎 読み手アリア
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「抜打ち獅子兵衛です。この作品は、昭和15年講談雑誌に掲載されました。37歳の作品です。寛永19年の江戸、両国広小路という目立つ場所に「賭け勝負、木剣真剣望み次第、試合は一本、申し込みは金一枚、打ち勝つ者には金十枚呈上。中国浪人天下無敵 抜打ち獅子兵衛」と大書された高札が立ち、町の人々の注目を浴びます。なぜ目立つところに高札を立てたのか?最後までごゆっくりお聴きください。
抜打ち獅子兵衛 主な登場人物
舘ノ内佐内(獅子兵衛)・・・改易された主人の元家臣であり、主人の遺族を護るために「抜打ち抜打ち獅子兵衛」として賭け勝負に挑む。若く美貌で剣の腕前も非常に高い。
妙泉院・・・旧主人、柘植但馬守直知の未亡人。遺族を代表する存在であり、佐内の行動を戒める。
倫子姫・・・旧主人、柘植但馬守直知の一人娘。十七歳。純真で無垢な存在。佐内にとって最も大切な存在であり、彼女を護るために佐内は尽力している。
柘植但馬守直知・・・備中新見で二万石だったが、幕府の忌諱に触れることがあって3年前に改易された。
松平虎之助・・・出雲国広瀬三万二千石、松平壱岐守の子で21歳、御連枝の気品は争えぬ威厳を備え、鬼若殿と呼ばれている。
藤兵衛・・・松平虎之助の家臣。。虎之助の命で佐内に挑むが敗北する。
抜打ち獅子兵衛 あらすじ
江戸の両国広小路で獅子兵衛は挑戦者を次々と打ち負かしています。ある日、松平壱岐守の子である虎之助が現れ、彼の命で家来の藤兵衛が獅子兵衛に挑むも、彼にあっさりと打ち負かされてしまいます。
物語はさらに進み、獅子兵衛の名が「佐内」であり、持輪寺にて主人の後室である妙泉院さまと対面し、賭け試合の件で叱責を受けます。寺を去る佐内に主人の娘である倫子姫が彼を引き留め、彼が去ってしまうことを悲しみます。佐内は倫子姫のために真実を語ることはできないが、心の中で永遠に彼女を護り続けて行くことを誓い、再び江戸の闇の中へ消えていくのでした・・。