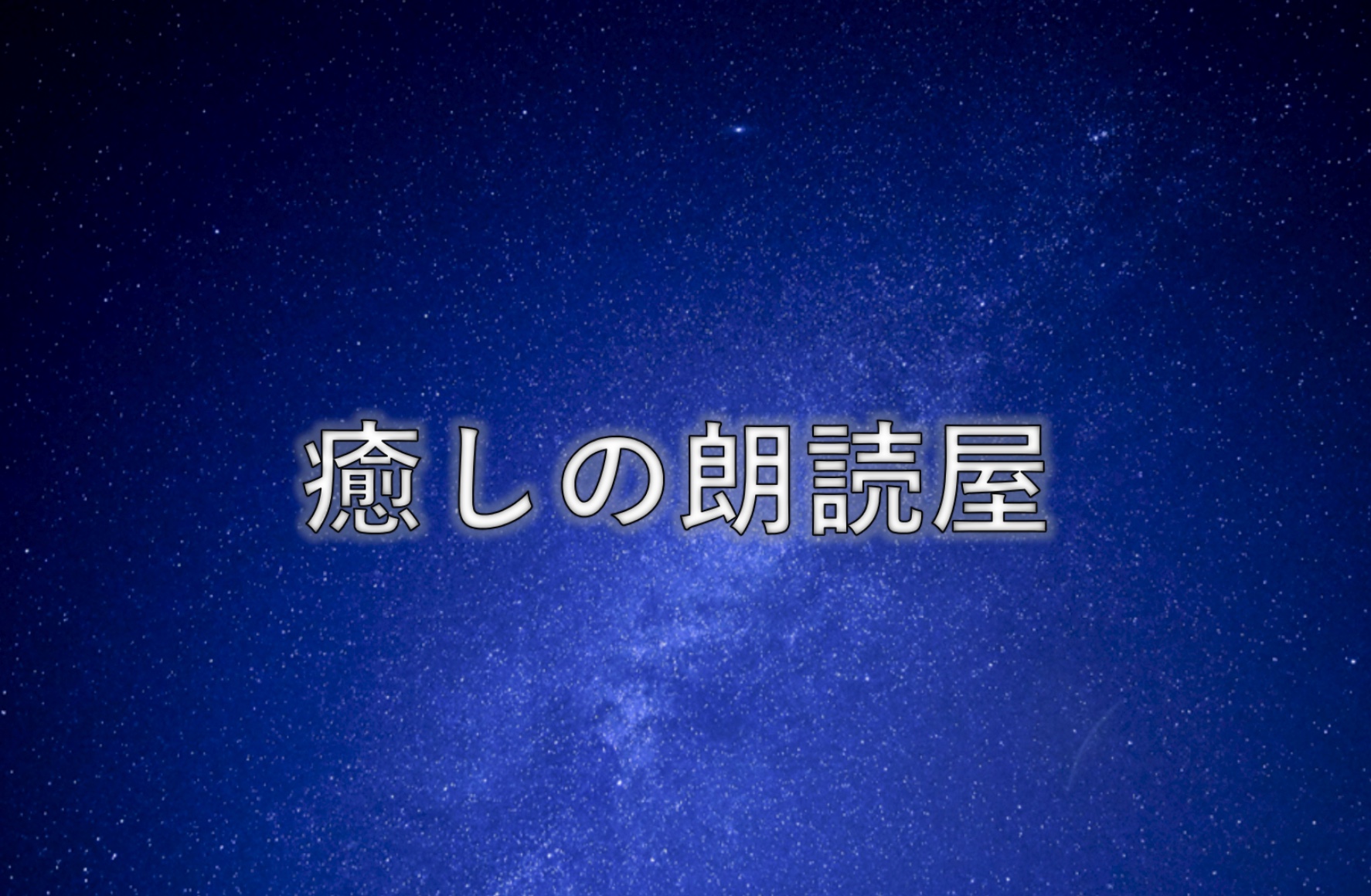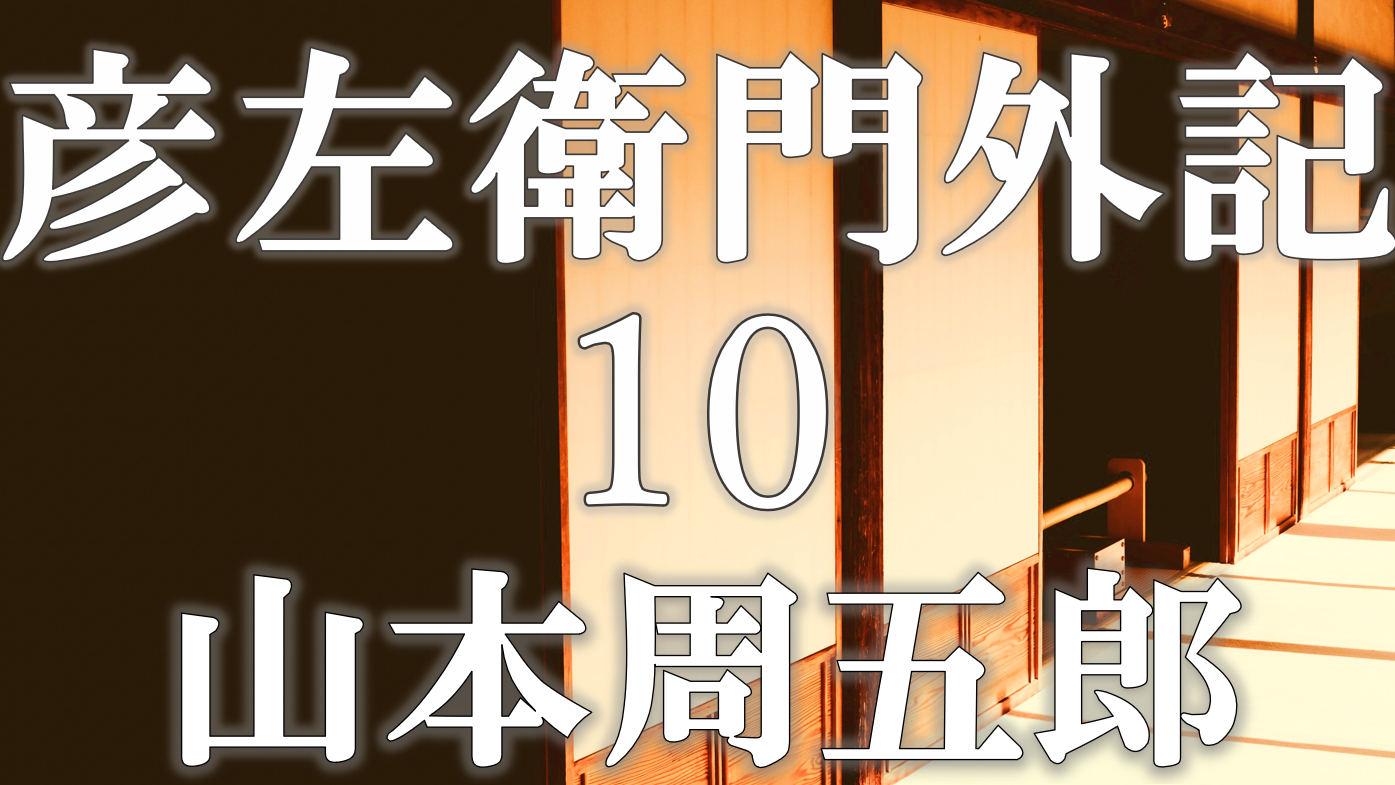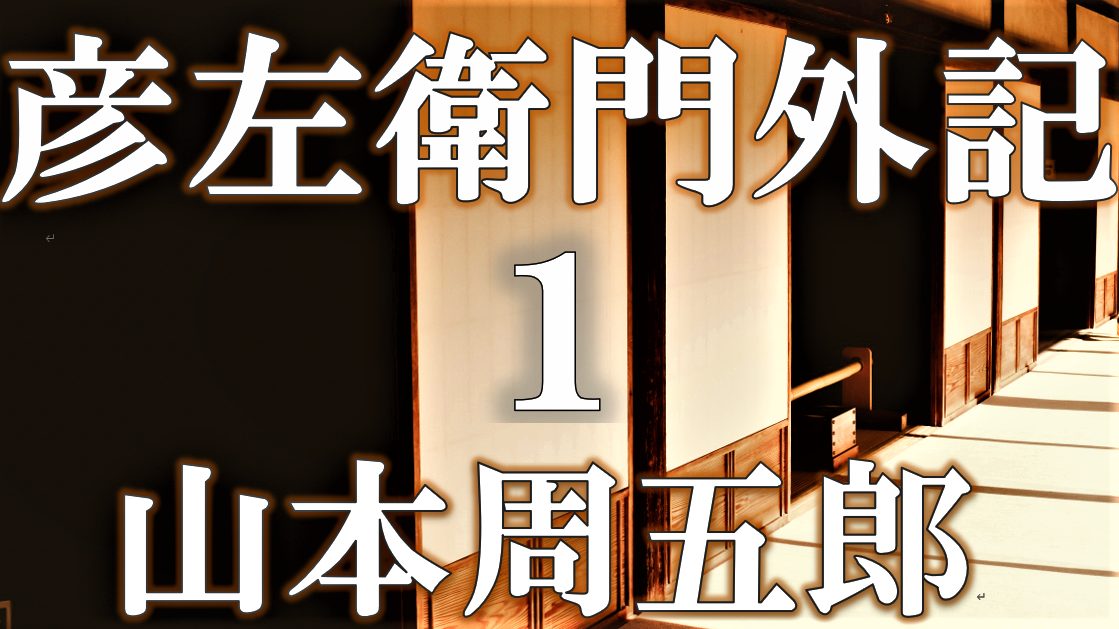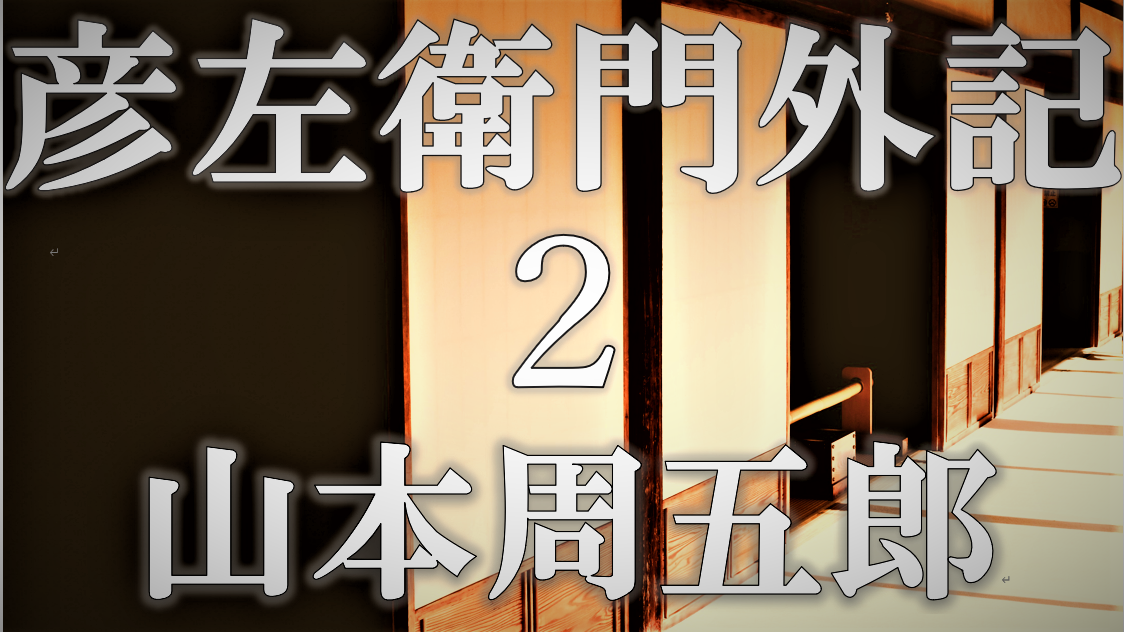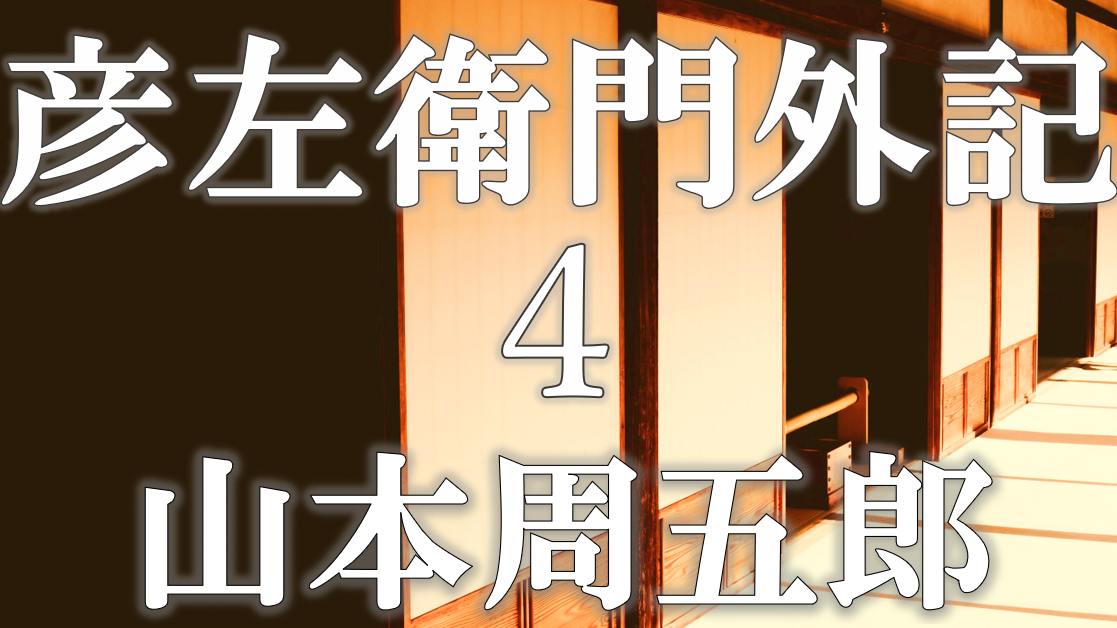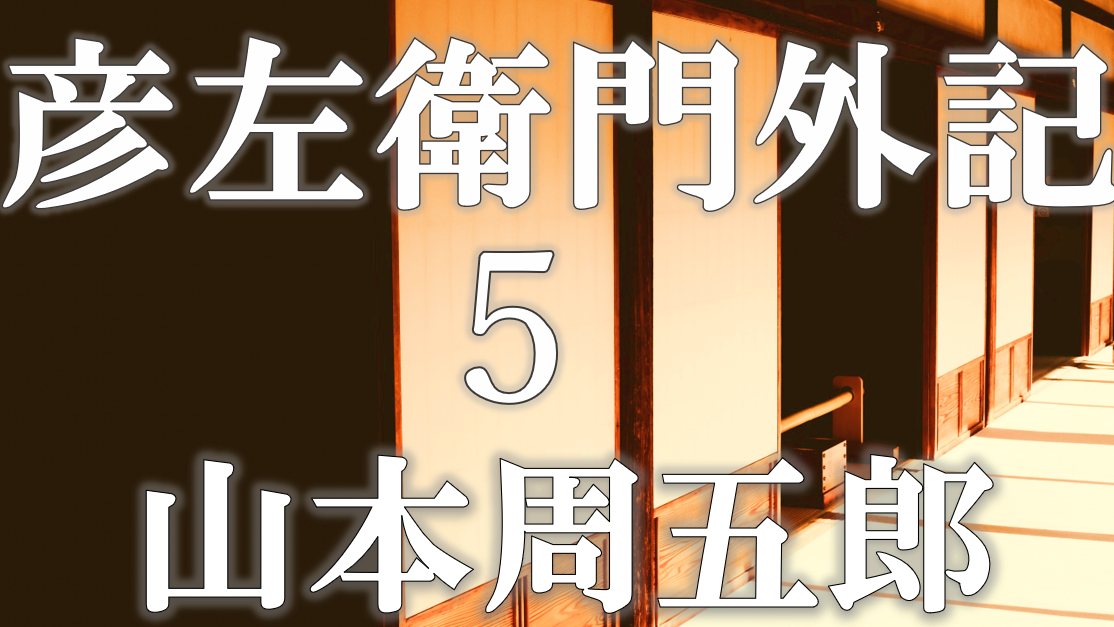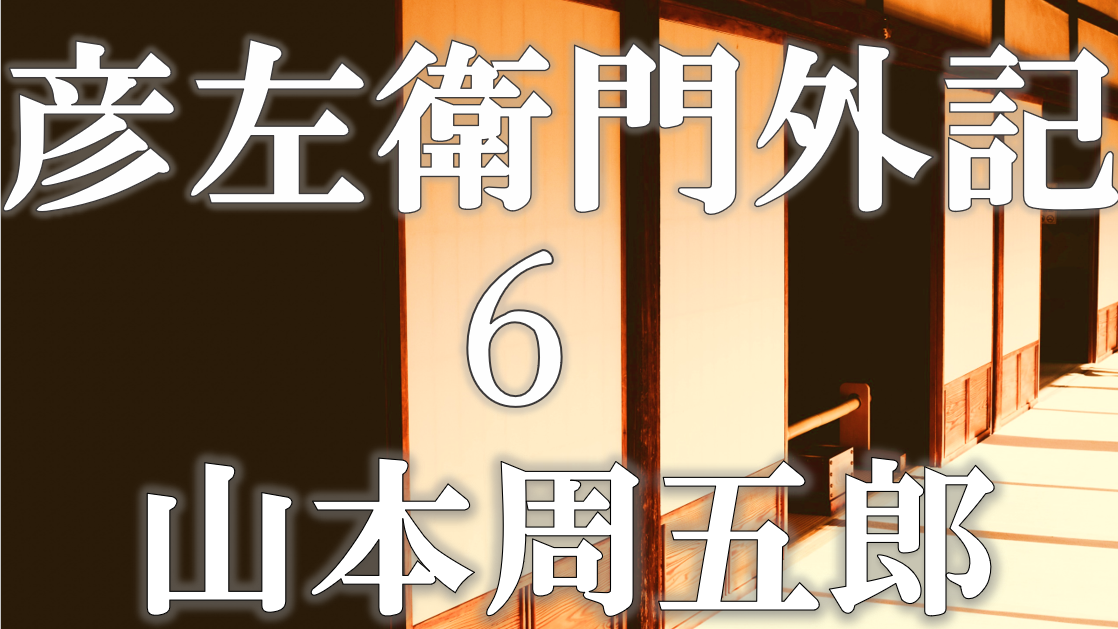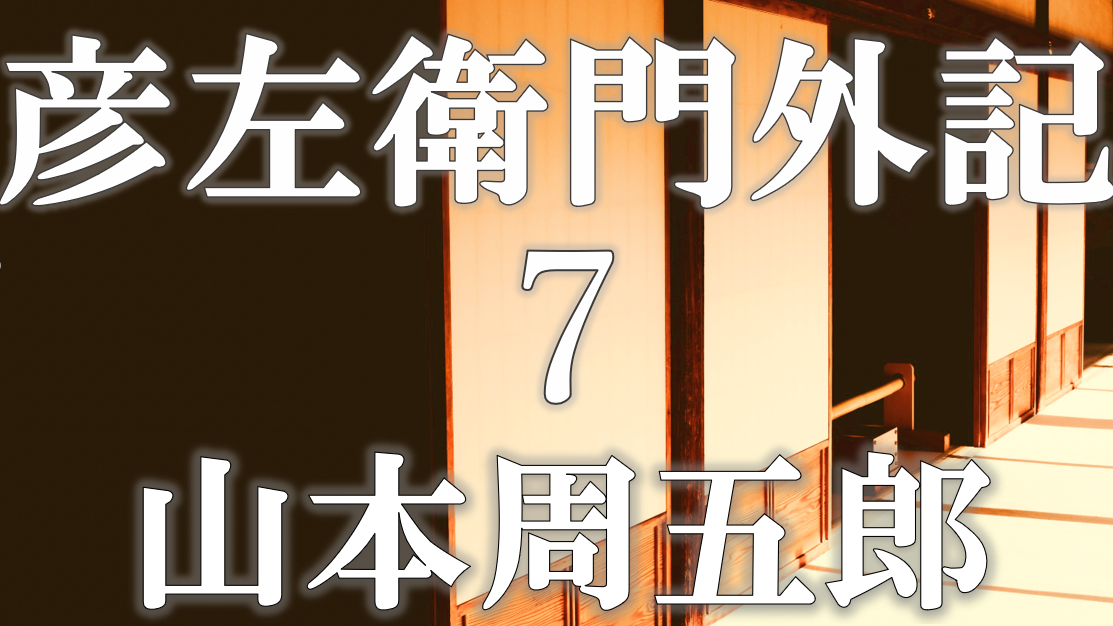【朗読】彦左衛門外記4 山本周五郎 読み手アリア
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「彦左衛門外記4」です。数馬は水野十郎左衛門をかもにして三十余日、彼をめぐって次々と事が起こった。第一は「ご意見番の墨付」の問題で白柄組の糾問を受けたが、数馬は十八人の白柄組をあっさり言いくるめ、煽動された十郎左衛門はすっかり彦左衛門に惚れ込み、仲間も共にしきりに本所まいりを始めたのであった。第二は同じく「ご意見番の墨付」のことで大伯父に大喝をくらったが、数馬はすばやく伯父の鋭鋒を脇へそらすことに成功し、帰るときには機嫌よく呼びかけられたくらいだった。次に数馬は奥平邸で危うく屋敷の者に捉まりそうになり、狼狽して逃げ出したため足首を捻挫してしまった。また、養父の三郎太郎左衛門が十五歳の千貝と再婚することになり、数馬に年若い継母ができたのであった。
かん太
季節はもう九月、晩秋になって、数馬は奥平家の庭で、寒くなったら姫とどこで逢うか?雪の中で愛の語らいもできないだろう・・と呟いたとき、燈籠のすぐ向こうで密談する三人位の声を聞くんだ。誰が何の相談をしているのだろう・・・妙に気がかりだった。
アリア
ちづか姫とは、奥殿の中で逢うことになったよ。しかし早苗の案内で屋敷から出るときに、あの力士のように逞しい いつき姫にばったり遭遇するんだ!数馬は早苗のうしろに隠れ、全身をちぢめて小さくなるんだ。運よく、いつき姫は夜盲症で見つかる心配はなかったんだ。
かん太
養父と再婚した多賀井千貝さんが新登場したよ。千貝は、極めて純粋に数馬の母親としてのつとめを自覚し、母として彼を躾け、教育してやろうと考えるんだ。継子いじめじゃないんだよ!
彦左衛門外記4 新しい登場人物
多賀井千貝・・・十五歳、養父の三郎太郎左衛門の再婚相手。小柄だが、今に肥えてみせるぞと宣言しているような体付きで、すでにその胸や腰には前触れの肉が付き始めているし、しもぶくれのたっぷりした頬や、厚いしっかりとした唇や、力のこもった眼光なあどには、人を圧伏する気構えが十分に備わっている。数馬を絶え間なしに呼びつけ、用を命じたり小言を云ったり訓戒を垂れたりする。
アリア
数馬は身長170㎝強くらいで、体重は60キロ。(五尺七寸、十五貫六百)スラっとした体形だね。この頃の人にしては大きいかもね。アリアも身長172㎝だよ!数馬に勝った~~~かな!
かん太
千貝(数馬の継母)はね、150㎝弱くらいで、体重は45キロ弱だよ。(四尺九寸あまり、固太りで十一、二貫くらい)標準的な感じがするね。いつき姫はどうなんだろ・・?
彦左衛門外記4 覚え書き
仮宅(かりたく)・・・しばらく住む家、仮の住まい。
引手茶屋(ひきてぢゃや)・・・遊郭で、客を遊女屋に案内する茶屋。
好学の士(こうがくのし)・・・学問が好きで、それに熱心なひと。
煽動(せんどう)・・・気持ちをあおり、ある行動を起こすようにしむけること。
慷慨(こうがい)・・・世間の悪しき風潮や社会の不正などを、怒り嘆くこと。
無頼(ぶらい)・・・正業につかず、無法な行いをすること。また、そのさまやsのような人。
作興(さっこう)・・・ふるいおこすこと。盛んにすること。さこう。
驕慢(きょうまん)・・・おごり高ぶって人を見下し、勝手なことをすること。
俗塵(ぞくじん)・・・浮世のちり。俗世間のわずらわしい事柄。
直諫(ちょっかん)・・・下位の者が相手の地位・権力に遠慮することなく率直にいさめること。
花押(かおう)・・・署名の代わりに使用される記号・符号のこと。
世情人心(せじょうじんしん)・・・世俗の考え、俗人の心。
古人(こじん)・・・いにしえびと。昔の世の人。こじん。
多事多端(たじたたん)・・・仕事が多くて大変忙しいさま。
大喝(だいかつ)・・・大きな声でしかりつけること。また、その声。
糾問(きゅうもん)・・・罪や不正を厳しく問いただすこと。
煩瑣(はんさ)・・・こまごまとしてわずらわしいこと。
鋭鋒(えいほう)・・・言葉や文章による鋭い攻撃。
圧伏(あっぷく)・・・力で押さえつけて服従させること。
おぼこ・・・まだ世慣れていないこと。また、そのさまや、そういう人。
諄々と(じゅんじゅんと)・・・じっくり教え諭すこと。丁寧。
悍馬(かんば)・・・気が荒く、制御しにき馬。あばれ馬。
食傷(しょくしょう)・・・同じことに何度も接し、飽き飽きして厭になること。
巴御前(ともえごぜん)・・・源義仲の側室。武勇を持って知られ、常に義仲に従ってしばしば戦功を立てた。
夜盲症(とりめ)・・・薄暗くなると物が見えにくくなる症状。ビタミンA欠乏など。
残菊(ざんぎく)・・・晩秋、初冬まで咲き残っている菊の花。
老耄(ろうもう)・・・おいぼれること。また、その人。