【朗読】勘弁記 山本周五郎 読み手アリア
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「勘弁記」です。この作品は昭和20年、42歳の作品です。最後がざっくりいってしまうので、実はもっとお若い頃の作品かと思いました。自分自身の問題でないことで果し合いになるのですが、よく考えると相手が妹婿だっただけに許せない気持ちが強まったのかな。ちょっと乱暴だなと思った作品でした。皆さんはいかが思われましたか?
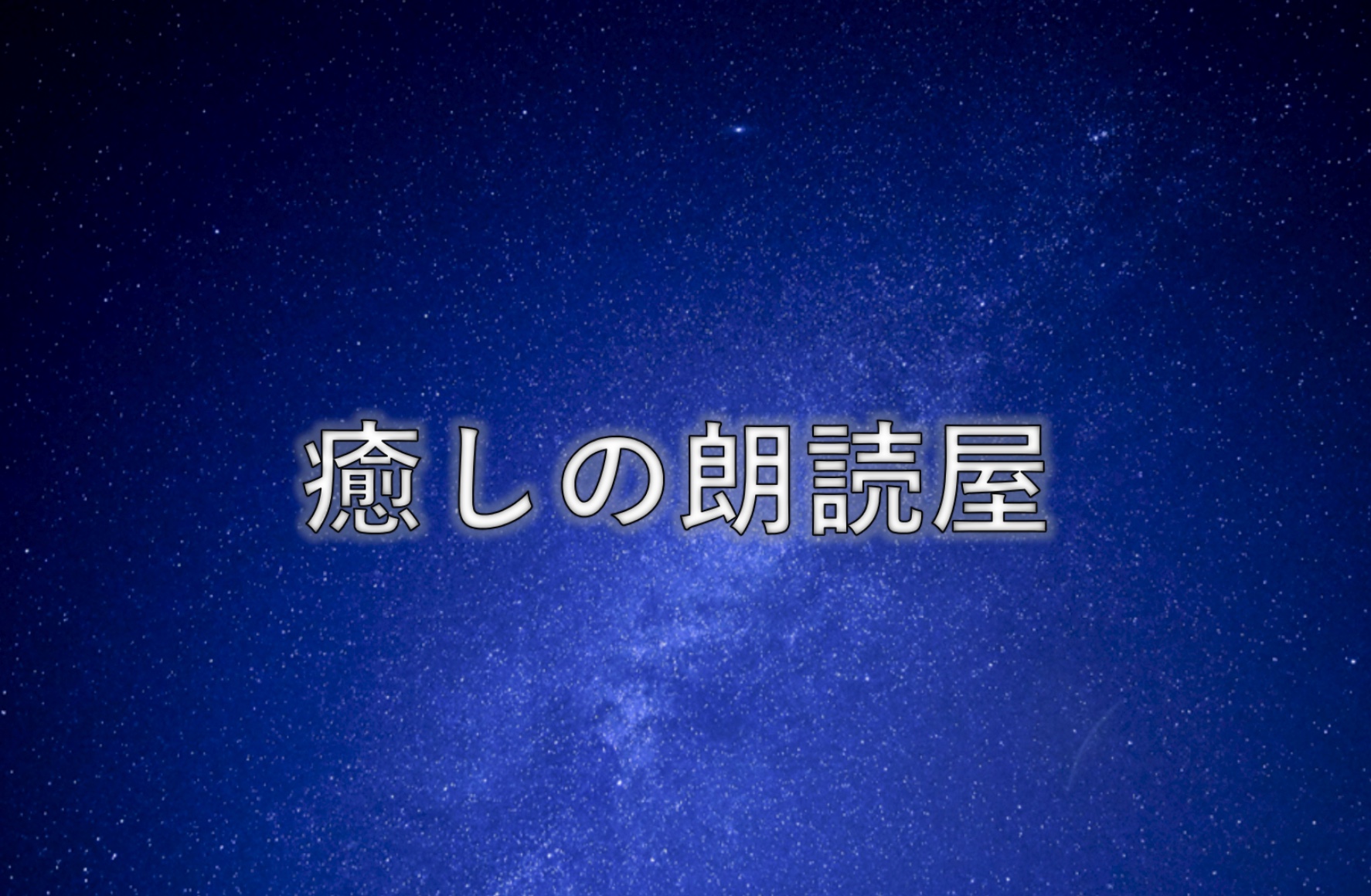
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「勘弁記」です。この作品は昭和20年、42歳の作品です。最後がざっくりいってしまうので、実はもっとお若い頃の作品かと思いました。自分自身の問題でないことで果し合いになるのですが、よく考えると相手が妹婿だっただけに許せない気持ちが強まったのかな。ちょっと乱暴だなと思った作品でした。皆さんはいかが思われましたか?
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「千代紙行燈」(昭和14年)周五郎先生36歳の作品です。同年だけで、「奇縁無双」「峠の子守唄」「違う平八郎」「粗忽評判記」「金作行状記」等など書かれています。
奈美・・・十八歳。病める緋牡丹といった美しさ。江戸表日本橋小伝馬町の呉服商、松田屋の主人。身体が弱く父母を亡くして悲しい身の上。
そで・・・奈美のばあや。
佐伯助次郎(若様金三)・・・播州浪人。旅の道中さらわれそうになった奈美とそでを助ける。
喜右衛門・・・松田屋の支配人。うわべは実直だが、腹はよくない男。
痕権(痕の権兵衛)・・・高頬に刀痕のある男。かみそりのような眼をしている。
藤沢の宿から江ノ島に向かって歩いてた奈美とばあやのそでは、突然後ろから走ってきた若侍に、宿で彼の金子を盗み去った者と間違われる。すぐに誤解は解けたが奈美は若侍にひと眼の恋をした。・・・しかしすぐに若侍は走り去ってしまった。一夜経って旅の帰りの道中、身代金目的に痕の権兵衛にさらわれそうになる奈美とばあやのそでは、偶然、先日の若侍に危ないところを助けられる。若侍は播州浪人の佐伯助次郎といい、江戸の身寄りの者を訪ねていく途中だった。助次郎はそでの勧めで奈美の住む橋場の寮の離家に立ち寄ることになった。そこは千坪の敷地に贅を凝らした母屋と茶室風の離室が建っていた。滞在して七日目、助次郎は奈美の琴の音に足を止めた。それは「千鳥の曲」であった。亡くなった母代わりの姉がよく弾いていた曲である。助次郎はこの曲を聴くと気の優しかった姉を思い出す癖がついていた。奈美は、助次郎の姉の話を聞き、自分の悲しい身の上に重ね、涙するのであった。そこへ、そでがやって来て奈美の哀れな身の上を語った。松田屋の主人は五年前に死んだ。店は京の松田屋の系統で、京の方を本店と呼んでいた。ひと頃は、本店の二男辰之助を奈美の婿に迎える話もあった。しかし、支配人の喜右衛門がうわべは実直に装いながら店の勢力を自分の手に握り、本店と手を切るように謀っていた。奈美と辰之助の縁談も自然と消滅したのだった。さらに喜右衛門は自分の倅を奈美の婿にと計りはじめていた。話を聞いた助次郎は、「長者番付に載っている大家でも裏にはこんな悲劇がある」と深くため息をついた。
従類(じゅうるい)・・・一族、家来の総称のこと。
人品(じんぴん)・・・人としての品格。特に身なり、顔立ち、態度などを通じて感じられるその人の品位。
辻斬り(つじぎり)・・・武士が刀剣の切れ味や自分の腕を試すために往来で人を斬ったこと。
追剥ぎ(おいはぎ)・・・通行の人をおびやかして衣類や持ち物などを奪うこと。
恰幅(かっぷく)・・・肉付きや押し出しから見た、からだの恰好や姿。
理非(りひ)・・・道理にかなっていることと外れていること。
詠歎(えいたん)・・・物事に深く感動すること。
野面(のづら)・・・野のおもて、野原。
荒涼(こうりょう)・・・荒れ果ててものさびしいこと。また、そのさま。
妙筆(みょうひつ)・・・非常にすぐれた筆跡。また、その書画や文章。
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「千本仕合」(昭和16年)です。。正月中ごろに松坂城下に現れた草刈馬之助は、領内で千番仕合をして武道修行をしたいという。むろん断る筋はないので許したのだが、その若者ひどく強い。松坂城下で腕利きと呼ばれたものを三人、名あるものだけでも二十余人を破り、他にも三十番に余る徒士勝負を取っている。(ならぬ堪忍/新潮文庫)
和泉三郎兵衛・・・紀伊ノ国田辺城の武士。天心独名流、柳生流を修行した剣法では家中若手の中で屈指の名をとる。
お志保・・・三郎兵衛の妹。十八歳、田辺領きっての才女の誉れ高い娘。容色も群を抜いて美しく、琴の名手、歌を詠み詩をつくる。小太刀と薙刀にも男勝りの腕を持つ。
草刈馬之助(成瀬格之進)・・・見たところ二十七八と思える、色の浅黒い美丈夫。領内で千番仕合を願い出て次々と剣の達人を破る。
紀州の太守頼宣・・・武を愛する。有名な兵法家が家中に集まる。
金之助・・・お志保の従兄妹。お志保を愛している。
緋桃(ひもも)・・・花が濃紅色の桃。
憤激(ふんげき)・・・はげしくいきどおること。ひどく怒ること。
美丈夫(びじょうぶ)・・・美しく立派な男子。
夜半(よわ)・・・夜中。
筆勢(ひっせい)・・・書画に表れた筆の勢い。また文章の勢い。筆力。
慇懃(いんぎん)・・・真心がこもっていて、礼儀正しいこと。また、そのさま。
真剣(しんけん)・・・本物の刀剣。
自負(じふ)・・・自分の才能・知識・業績などに自信と誇りを持つこと。
右手(めて)
厘毛(りんもう)・・・厘と毛。転じて、きわめてわずかなこと。
遅速(ちそく)・・・遅いことと速いこと。遅いか速いかの度合い。
後詰(ごづめ)・・・先陣の後方に待機している軍勢。
甲斐甲斐しい(かいがいしい)・・・動作などがいかにも手ぎわよく、きびきびしているさま。
名聞(みょうもん)・・・名声が世間に広まること。世間での評判・名声。
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「半化け又平」です。この作品は昭和11年、少女倶楽部に掲載されました。播州姫路の城下、八重樫主水の道場の一人娘、椙江は、年ようやく十九歳、才知に秀でているうえ、城下町で評判の美しい縹緻をもっていたが、老年になった父をよく助けて、七人の内弟子と下女下郎の一家を、娘の手ひとつに切り盛りしていました。道場の下郎に「半化け又平」と呼ばれる下郎がいて、どこか間がぬけていて、いつもえへら笑いをしているが、色白の眉の濃い、口元の引き締まった立派な人品で、椙江にはどういうわけか、又平の素振りに納得のいかぬところがあるように、「もしかして・・仔細あってわざと愚か者の風をよそおっているのではないか。」と思えて仕方がないのでした。
半化け又平・・・八重樫主水の道場の下郎。一年ほど前に奉公に来た。在方の百姓の三男とのことだが、色白で眉が濃く、口元の引き締まった立派な人品。
椙江・・・八重樫主水の一人娘。又平はただの下郎ではないと思っている。
八重樫主水・・・古中条流の達人、家臣ではないが、領主池田候から年々五百俵ずつ手当てをうけ、家中の武士に指南をしている。しかしそれは姫路藩以外の者に伝授してはいけない「お止流」の条件付きだった。
沼田軍十郎・黒板権六・石山弾兵衛・・・八重樫道場の門弟中で三羽鳥と呼ばれる腕利き。
岡部五太夫・伊丹兵右衛門・・・竜虎と呼ばれる師範代。
凌ぎ(しのぎ)・・・苦しい局面やつらいことを、なんとかもちこたえて切り抜けること。また、その方法・手段。
人品(じんぴん)・・・人としての品格。特に、身なり・顔立ち・態度などを通じて感じられるその人の品位。
才知(さいち)・・・才能と知恵。
弄り物(なぶりもの)・・・もてあそびもの。なぐさみもの。
秋思(しゅうし)・・・秋に感じるものさびしい思い。
哀傷(あいしょう)・・・心に深く感じて物思いに沈むこと。
臥所(ふしど)・・・寝所、寝床。
紙燭(しそく)・・・手元を紙で巻く松の木を棒状に削った明かり。
大上段(だいじょうだん)・・・剣道で頭上に高く刀を振りかざす構え。
戛(かつ)・・・硬いものどうしが触れ合う音。
白髯(はくぜん)・・・白いほおひげ。
徒(あだ)・・・実を結ばずむなしいさま。無益なさま。
枉げて(まげて)・・・道理や意思に反して行動するさま。無理を承知で頼むときに使う。
大喝(だいかつ)・・・大きな声で叱りつけること。
有明行燈(ありあけ)・・・夜明けまで夜通しつけておく行燈。
横奪(おうだつ)・・・無理に奪い取ること。
飛燕(ひえん)・・・飛んでいる燕。
顛倒(てんとう)
右足(うそく)
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「古い樫木」(昭和23年)です。福島正則は邸内で扈従組の富井主馬が、表使いの女中と奥庭で密会しているところを発見する。正則は一言叱りつけて許すつもりだったが、主馬は恥じる様子がなく「自分たちは末を誓った仲で不義ではない。」と昂然と額を挙げて云った。正則はそれが気に入らず、彼らを納戸部屋に檻を作らせそこに監禁した。
福島正則・・・豊臣秀吉の武将。五十九歳。安芸備後五十万石の領主。幾十たびの合戦で数知れぬ高名てがらを立て、死んだ後に名が残るとしても「それで何か得たものはあったか。」「誰かを本当に愛し愛されたことがあるか。」「人を亡ぼし城を焼き領地を奪っただけではないか。」と自問する。今は古い樫木の側にいるときだけ落ち着いた安らかな気持ちになることができる。
古い枯れた樫木・・・奥庭の泉のほとりにある樹齢八九百年、枯れてからも年月が経ち、遠くから見ると巨人の枯骨のようにも見える。正則はその姿に激しく心惹かれている。
富井主馬・・・扈従組の若侍。気はしの利くみどころのある男。女中と奥庭で密会しているところを発見されるが悪びれない。
女・・・主馬の恋人。表使いの女中。主馬に「互いにめぐり逢い、互いに愛し合ったというだけで五十年生きるよりも真実に善く生きた。」と云う。
佐太兵衛・・・庭番の老僕。正則と同郷で百姓だった。正則が二十五歳で伊予のくに二十万石の領主になった時、頼ってきて身を寄せた。
保乃・・・正則の側女。六歳と四歳の女の子を産む。正則に向かって何でもずけずけと云う。
夫人・・・正則を深く理解する。牧野忠成の妹。
鳥居忠政・・・正則と親しい人。幕府の上使。正則の娘たちの行く末を頼まれる。
御館(おたち)・・・御屋敷
密通(みっつう)・・・ひそかに通じ合うこと。
糺明(きゅうめい)・・・罪や不正を糾問し、真相を明らかにすること。
悪心(おしん)・・・恨みを抱き、悪事をしようとするよこしまな心。
不義(ふぎ)・・・男女が道に背いた関係を結ぶこと。
昂然と(こうぜん)・・・意気の盛んなさま。自信に満ちて誇らしげなさま。
草創期(そうそうき)・・・新しく物事の始まった時期、初期。
琅玕(ろうかん)・・・美しいもののたとえ。暗緑色、または青碧色の半透明の硬玉。
枯骨(ここつ)・・・死人の朽ち果てた骨。
霜雪(そうせつ)・・・霜と雪。
孤峭(こしょう)・・・きびしく一人だけでいること。
衰耗(すいもう)・・・衰え弱ること。
虚礼(きょれい)・・・うわべばかりで誠意を伴わなわない礼儀。形式的な礼儀。
追従(ついしょう)・・・他人の気に入るような言動をすること。こびへつらうこと。
栄枯(えいこ)・・・栄えることと衰えること。
変遷(へんせん)・・・時の流れとともに移り変わること。
卓抜(たくばつ)・・・他のものをはるかに抜いてすぐれていること。
輾転反側(てんてんはんそく)・・・悩みや心配のために眠れず、何度も寝返りを打つこと。
気色(きしょく)・・・心の状態が外面に表れた様子。顔色。
井水(せいすい)・・・井戸の水。
米塩(べいえん)・・・人間の生活んい欠くことのできない米と塩。
笑殺(しょうさつ)・・・大いに笑わせること。また、あざ笑うこと。
久闊(きゅうかつ)・・・久しぶりの挨拶をする。
譴責(けんせき)・・・しかり責めること。不正や過失などを厳しくとがめること。
虐政(ぎゃくせい)・・・人民を苦しめるむごい政治。
配流(はいる)・・・刑罰のひとつ。罪人を辺境や島に送る追放刑である。
流謫(るたく)・・・罪によって遠方へ流されること。
幽鬼(ゆうき)・・・死者の霊魂。
騒擾(そうじょう)・・・集団で騒ぎを起こし、社会の秩序を乱すこと。
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「古今集巻之五」(昭和33年)です。周五郎先生55歳の名作です。主人公、永井主計の妻が結婚三年目で理由も分からない自殺をします。主計は妻に死なれてから始めて、自分が妻に気をつかったこともなく無関心であったこと、妻を娶り、妻がそこにいるというだけで安心し、妻と人間と人間との芯からのつながりを持とうとしなかったことに気が付き、妻のことが少しづつ分かっていきます。妻の自殺の理由が全てわかったとき主計は・・・・。
永井主計・・・現在は無役だが、近いうち旧禄を復活され中老職にあげられる。開放的で卑屈なところもなく少しもかげのない性質。だが妻に死なれたいたでが深く、妻が自殺した理由をつきとめない限り本当に立ち直ることはできないと思っている。
杉江・・・主計の妻。遺書も手紙も残さず、長持、箪笥などすべてを驚くほどきれいに始末して自殺する。ただ枕の下に一冊の「古今集巻之五」を残していた。
岡本五郎太・・・大目付役。主計の親友で自殺した妻を発見したときからずっと彼の力になる。杉江の自殺理由を探る。
六左衛門・・・主計の父。先代の藩主のときに、課役騒動の責任を負って、家禄削減、役目罷免となっていた。卒中で倒れ、隠居所で療養中。
細野源三郎・・・小柄な、いかにも賢そうな顔立ちで目が際立ってすずしく澄んでいる。学才があり、松崎塾の教授助手をつとめていた。
寛延二年三月八日の夕方五時から永井主計の送別の宴を催した。主計は十五日に参勤の供で江戸へゆくことになったのだが、他に、こんど永井家が旧禄を復活され、主計が中老職にあげられることになっていた。宴の翌日早朝、岡本五郎太宅に永井より急の使いがきた。五郎太が永井を訪ねると主計が仮面のような顔をしていた。案内されて妻の寝所へ行くと、夜具の上で白無垢を着、脛を水浅黄の扱帯で縛り、短刀を左の乳房に柄まで突き刺し、柄を両手でしっかり握ったまま自殺していた。五郎太は理由を聞いたが、主計には何も分からなかった。遺書も手紙もなく、長持、箪笥、手文庫、文箱、鏡筥など全て驚くほどきれいに始末してあった。五郎太は夜具の枕の当たる位置の下から一冊の本を見つけた。それは「古今集巻之五」だった。五郎太は町医を呼び、杉江は病死ということになった。
鋭鋒(えいほう)・・・言葉や文章による鋭い攻撃。
母堂(ぼどう)・・・他人の母を敬っていう語。母君、母上。
胡蝶装(こちょうそう)・・・糊付けした面を開くと、胡蝶が羽を開いたようになる書籍の装丁の一種。
蘭法(らんぽう)・・・オランダの医学。
蕩児(とうじ)・・・正業を忘れて酒色にふける者。
脇息(きょうそく)・・・座った脇に置いて肘をかけ、身体をもたせかける道具。
行跡(ぎょうせき)・・・行状。身持ち。こうせき。
英明(えいめい)・・・すぐれて賢いこと。また、そのさま。
差し控え(さしひかえ)・・・江戸時代の刑罰の一つ。不祥事があった時、出仕を禁じ、自邸に謹慎させたこと。
課役(かえき)・・・仕事を割り当てること。
郷蔵(ごうぐら)・・・凶作に備えて穀類を保存した共同倉庫。
罷免(ひめん)・・・職務をやめさせること。免職。
妄執(もうしゅう)・・・迷いによる執着。
学才(がくさい)・・・学問の才能。
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「合歓木の蔭」です。この作品は昭和23年「新読物」に掲載されました。十七歳の奈尾は兄の市蔵の友人、岩田半三郎と婚約して祝言の日取りも決まっていました。奈尾は、市蔵という兄だけで女姉妹もなく、母も亡くし、厳しい父のもとで育てられて友達もありませんでした。二の丸御殿の舞台で行われる演能に叔母に付き添われて行ったとき、誰かがじっと奈尾を見ていることに気づきます。それは無礼なことなのだが奈尾は少しも怒りの感情は起こらず、むしろあやされるような密やかな喜びが胸に溢れて、一種のするどい快楽のような感じにとらえられるのでした。そしてそのじっと見る眼の主は、萩の廊下で奈尾の袂に結び文を入れ、その夜、庭の合歓木の蔭へ呼び出すのでした。
奈尾・・・十七歳。八百五十石の年寄肝入役の娘。小さいときから夢見がちな性質で、空想の方が現実より生々しく実感がこもっているように感じる。半三郎と婚約中、ふとすると誰かが遠くから自分を呼んでいるような錯覚におそわれる。そして結び文の主が、合歓木の蔭でささやく恋情の言葉に捉えられていく。
市蔵・・・奈尾の兄
岩田半三郎・・・七百石の納戸奉行、温厚で善良で思いやりが深く、奈尾にゆき届いた愛情を示してくれる。
男・・・老職なにがしの二男。
こけら落とし・・・新たに建てられた舞台で初めて行われる催し。
演能(えんのう)・・・能を演じること。
拝見(はいけん)・・・見ることをへりくだっていう語。
耳こすり・・・人の耳許で小声にささやくこと。
眼まぜ・・・目くばせ。
賜餐(しさん)・・・殿さまから酒食を賜る。
三晩(みばん)
四半刻(しはんとき)・・・現在の約三十分。
放恣(ほうし)・・・気ままでしまりのないこと。
収斂(しゅうれん)・・・縮むこと。引き締まること。
無風帯(むふうたい)・・・一年中、あるいは季節によってほとんど風のない地帯。
平板(へいばん)・・・変化に乏しく面白味のないこと。
閃光(せんこう)・・・瞬間的に発する光。
悪癖(あくへき)・・・悪い癖、よくない習慣。
煩瑣(はんさ)・・・こまごまとして煩わしいこと。
喪心(そうしん)・・・魂が抜けたようにぼんやりすること。
宝暦の春、島原で「満月」と呼ばれる花魁がいた。名の通り満ち欠け知らぬ美しさを誇り、十九の若さで世を魅了し、人々はその姿を一目見んと集まった。
彼女の元に通う三人の男たち──
老いを忘れ、財を惜しまず尽くす「金丸長者」。
美貌を誇り、身を持ち崩す「青山銀之丞」。
商売の才を持ち、恋に溺れる「播磨屋千六」。
三人は、それぞれの思いと欲望で満月を巡って争うが、満月の笑顔と技に翻弄され、人生を狂わされてゆく。やがて破滅に向かい、追い込まれた二人──銀之丞と千六は、ひと春のあと、満月の道中で再会する。
そこで見たのは、金丸の紋を掲げて誇らしく歩む満月の姿。そして、彼女から放たれたたった一言・・・
島原の松本楼に咲く絶世の花魁。
5歳で親を亡くし、松本楼に売られる。
美貌と才知に恵まれ、全国に名を轟かせる存在。
実は重い病を患いながら、男たちの間で巧みに立ち回る。
最期は金丸に身請けされ・・・
越後出身の大富豪。
老齢ながら満月に夢中になり、財を惜しまず尽くす。
最終的に満月を身請けし、死後は寺を建て僧となる。
出家後の法名は「友月(ゆうげつ)」。
関白七条家に仕える若侍。
容姿端麗な色男で、自らの魅力に自信満々。
満月への想いから身を持ち崩し、盗みや逃亡を重ねる。
最終的に満月への悔いと憎しみを胸に、僧となる。
出家後の法名は「友銀(ゆうぎん)」。
大阪の廻船問屋の若旦那。
満月に一目惚れし、店の財産を使い果たす。
のちに長崎で密貿易で成功し、一万両以上を得る。
満月を思い続けたが、死を知り涙する。
出家後の法名は「友雲(ゆううん)」。
満月を幼少時から育てた楼主。
彼女の病を金丸に正直に告げるなど、思慮深い人物。
井遷寺に住む怪僧。
本堂を細工し、賭場で客を脅して金を奪う。
後に銀之丞に討たれる。
吉岡鉄之進(よしおか てつのしん)
井遷寺で僧を討つ際に使った偽名。
本願寺の会式(えしき)
満月の花魁道中と並ぶほどの盛況を見せる仏教行事。
鼻曲山人(はなまがりさんじん)
江戸の学者。金丸邸に訪れ、満月の住居を筆録に残す。
登場人物たちは、「愛」「欲」「名誉」「復讐」「懺悔」といった深い情念に突き動かされ、やがてすべてを脱ぎ捨てて一つの墓前に辿り着きます。
彼らの心の変遷こそが、この物語の最大の見どころです。
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「噴き上げる花」(昭和17年)です。小姓組のきわめて平凡な、気の弱い男がこつこつと一人で火消し道具を試行錯誤しながら作り上げていく話です。
伊藤右太夫・・・食録百石。小姓組、中畔六左衛門の支配内で「水がかり」をつとめる平凡で気の弱い善良な男。
中畔六左衛門・・・加賀家物頭六百石、上屋敷「二の手」支配。
立原玄蕃・・・加賀藩士。三女を伊藤右太夫に娶ってもらいたいと云う。
菊枝・・・十七八の美しい娘。立原玄蕃の三女。
伊藤右太夫・・・もう一人の同名異人。書院番で妻帯者。
火事は江戸の華と云われた。「華」という表現は江戸人のやけくそとから景気をまぜたもので、火事になると大きくなるし、いつも巨万の財物を灰燼し、人畜の命を失うのが例だった。その頃の消化法は幼稚なもので、さあ火事だというと何百となく手桶を持ち出し、井戸なり川なりまた用水なり、手都合によって汲み上げたものを、現場まで人を並べて順繰りに送って消したものである。だからおいそれと消えないし、烈風のときなどは役に立たなかった。伊藤右太夫は「水がかり」でその指揮をしたが、火に水をかけるのを見るたびに、これでは埒が明かぬことだという感を深くしていた。何か方法はないものか。もっと敏速に、もっと高く水を届かせる方法がありそうなものだ。それから彼は、こつこつと工夫を始めたのである。まずは誰でも思いつきそうなところから手を付けた。すなわち子どもの水鉄砲である。
同名異人(どうめいいじん)・・・名前が同じ人。
財物(ざいぶつ)・・・金銭と品物。たから。
灰燼(かいじん)・・・灰や燃え殻。建物などが燃えて跡形もないこと。
人畜(じんちく)・・・人間と畜類。人と家畜。
定火消(じょうびけし)・・・江戸幕府の職名。江戸市内の防火、警備を司り、若年寄の支配下にあった。
方角火消(ほうがくびけし)・・・江戸城を中心に5区に分けて担当の大名を決め、その方角に火災が発生すれば出勤した。
近所火消(きんじょびけし)・・・幕府が藩邸の近隣の町屋の消火への出勤を義務づけた。これを各自火消といい、近所火消ともいった。
大名火消(だいみょうびけし)・・・寛永20年に始まる火消。
敏速(びんそく)・・・反応・行動のすばやいこと。また、そのさま。
粗忽(そこつ)・・・軽はずみなこと。そそっかしいこと。また、そのさま。
雲泥月龞(うんでいげつべつ)・・・両者があまりにも異なっていること。天と地。月とすっぽんのように違いすぎる意。
湯壺(ゆつぼ)・・・温泉などで、湧き出る湯をたたえたところ。湯舟。
玄蕃(げんば)・・・水手桶。
緩怠(かんたい)・・・いいかげんに考えてなまけること。また、そのさま。
竜吐水(りゅうどすい)・・・江戸時代から明治時代にかけて用いられた消化道具。竜が水を吐くように見えたことからつけられた。
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「四人ばやし」(昭和27年)です。料理茶屋の二階で起こる出来事を描いた一場面ものです。正太郎の最初の印象と最後がガラリと変わって面白いです。
正太郎・・・金物問屋「伊賀屋」の長男。幼い頃から手に負えないと云われ続けている。
おたみ・・・正太郎の妻。結婚生活がうまくいかないことを悩んで平吉に相談する。
平吉・・・太物問屋「堺屋」の手代。幼い頃から我慢強く、親や近所の人の期待する通りに育つ。
おつま・・・水茶屋「梅むら」のおんな。初めて逢った時から正太郎が好きだった。
料理茶屋の二階で正太郎は、平吉から十両の金を強請り取ろうとしていた。小屏風の内側には女がひとり倒れていた。手足を縛られ、猿轡を噛まされ、軀を曲げて横ざまに倒れていた。解けた帯の端が畳の上に延び、髪が無残に崩れていた。そんな姿を見られるのがいやなのだろう。女は身を縮め、顔をそむけた。正太郎は、妻おたみに平吉が二度も文をつけたとき、これっきりという約束をした。しかし平吉は、またしても妻おたみに文をつけたのであった。正太郎は、平吉と妻おたみの仲を疑っていた。正太郎と平吉は幼なじみであった。正太郎は金物問屋「伊賀屋」の長男で、腕白で我が強くて、始終みんなから悪く云われていた。手に負えないと云われていた。平吉は、「伊賀屋」の裏の長屋で、父親は俗にこね屋という下っ端の仕事をし、生活はむろん貧しかった。平吉は温和しい子で頭もよく、小泉町の寺子屋でも成績の一番良い子だった。太物問屋「堺屋」十一の年から奉公にいき、今では立派な手代となっていた。平吉とおたみは小泉町の寺子屋時代からのつきあいであった。
安普請(やすぶしん)・・・安い費用で家を建てること。また、そういう粗雑なつくりの家。
紙本(しほん)・・・紙に書いた書画・文書。
残忍(ざんにん)・・・無慈悲なことを平気ですること。
ひらぐけ・・・ひもや帯に芯を入れず、平らに仕上がるようにくけること。また、そのひもや帯。
結び文(むすびぶみ)・・・細く巻畳んで、端または中ほどを折り結んだ書状。恋文や儀礼に用いられた。
掛け取り(かけとり)・・・掛け売りの代金を取り立てること。
仮借(かしゃ・かしゃく)・・・大目にみてやり、まあまあと許すこと。
急調子(きゅうちょうし)・・・調子や物事の進み方が非常に速いこと。急テンポ。
婀娜(あだ)・・・女性の容姿や身のこなしが、なまめかしく、美しい。
おぼっこい・・・小さい子や精神年齢が低い人に対して使う幼いというような意味。
溜飲(りゅういん)・・・飲食物が胃に滞って、酸性の胃液がのどに上がってくること。
仰反る(のけぞる)