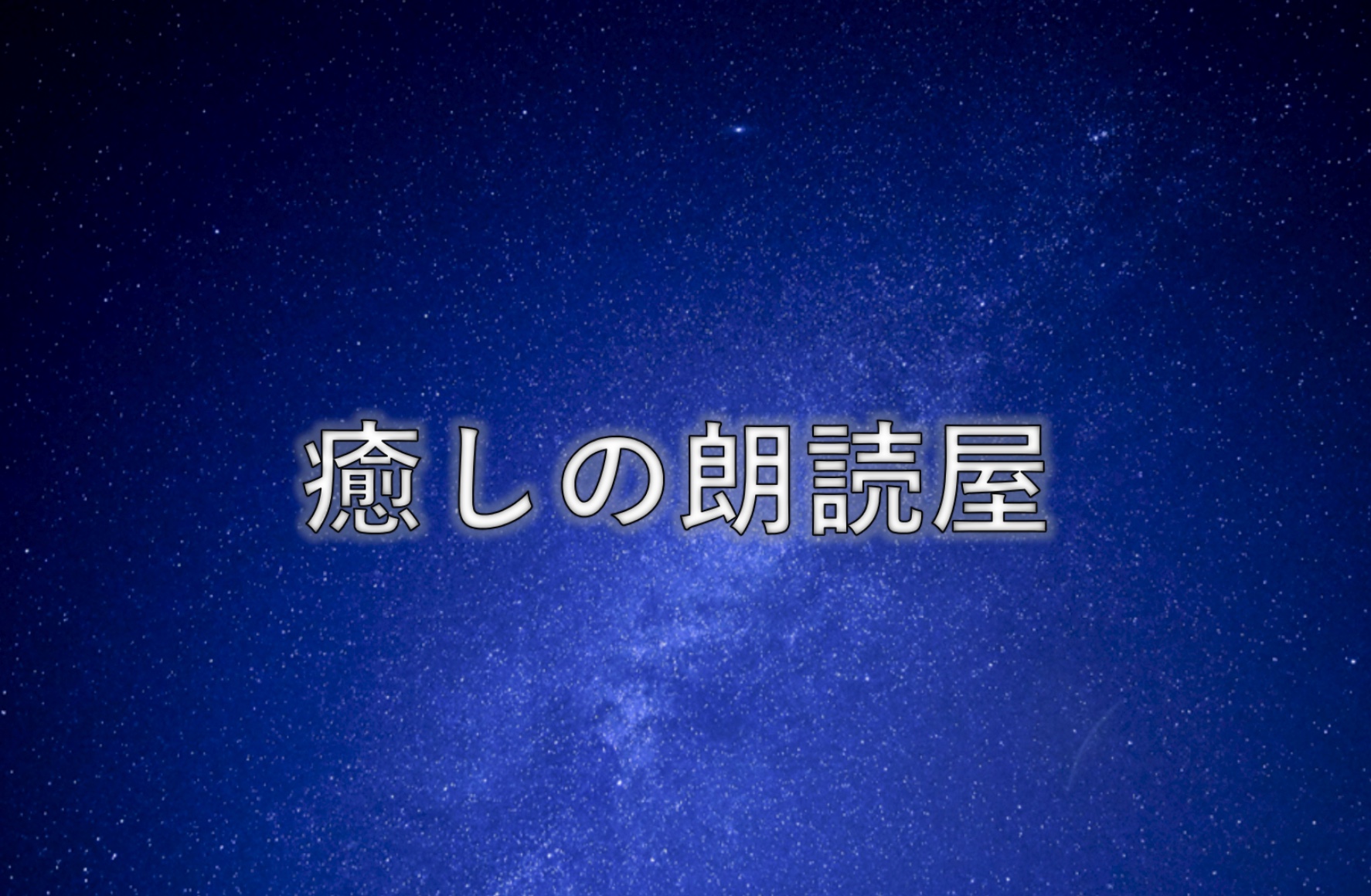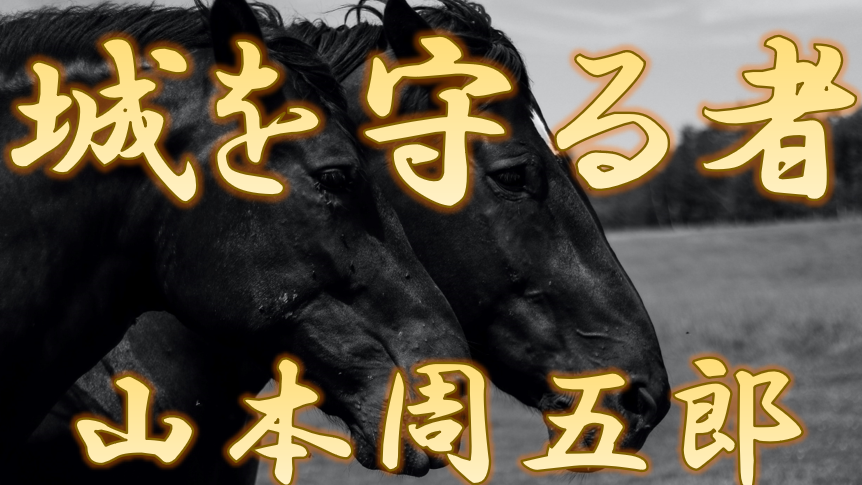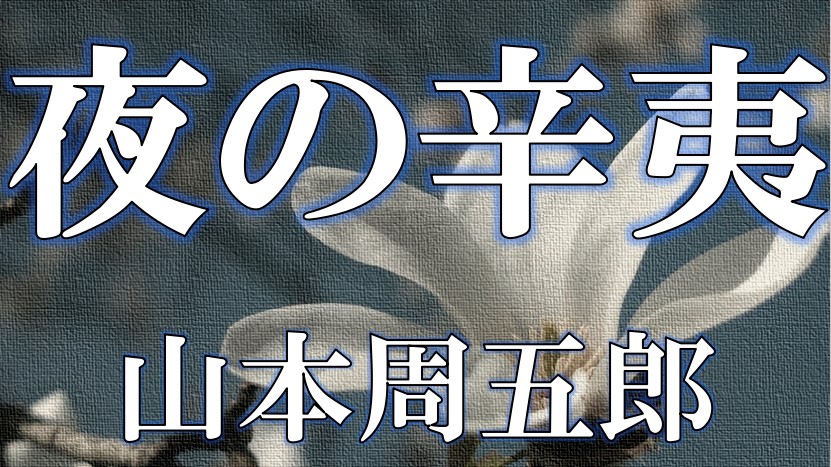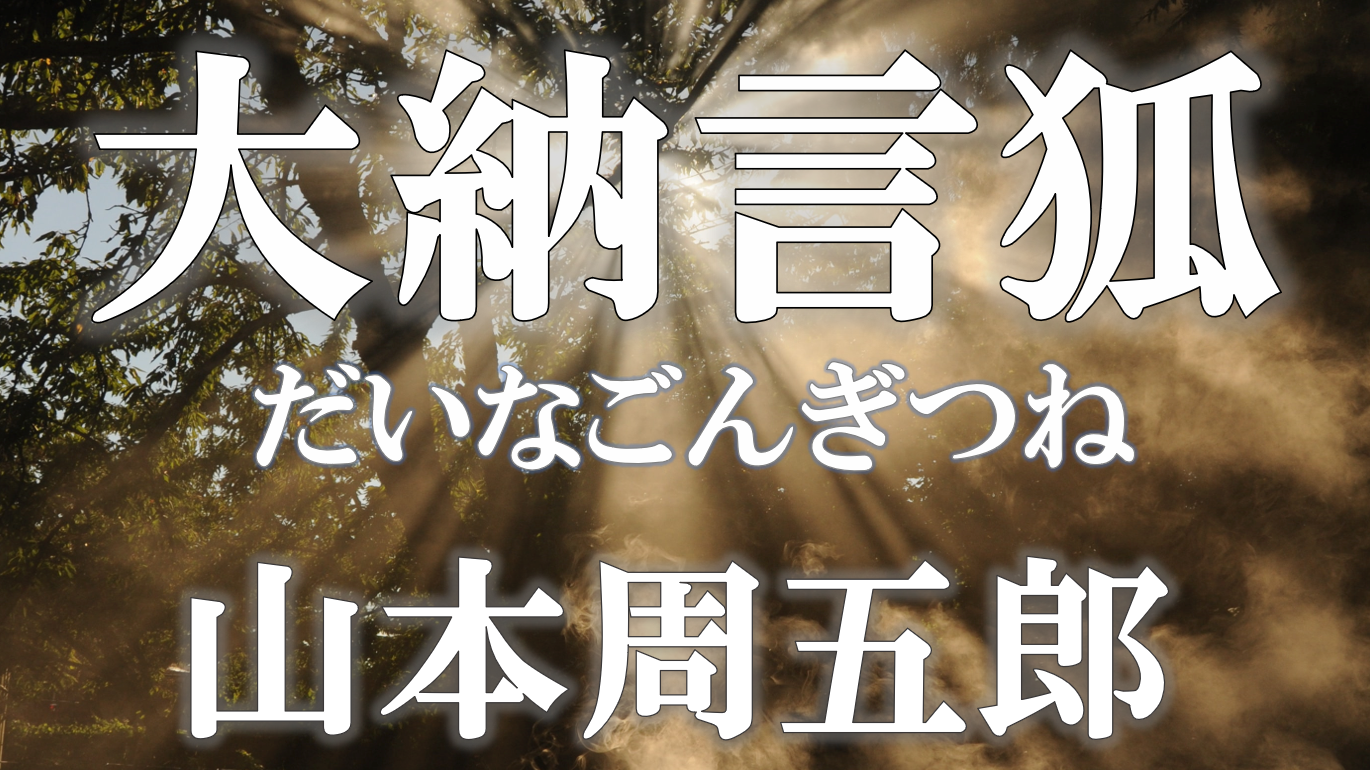【朗読】四日のあやめ 山本周五郎 読み手アリア
こんにちは!癒やしの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「四日のあやめ」です。この作品は、昭和29年(51歳)オール讀物に掲載されました。武家もので、武家で育った千生が夫を守りたい一心で取った行動から始まります。武家ものでありながら、千世の目で多く書かれているところがよかったです。
四日のあやめ 主な登場人物
千世・・・五大主税介の妻。兄の学問所からの親友だった主税介に恋をして結婚した。15歳の時、彼への想いが恋であることに気づき、兄の重三郎に告白した。
五大主税介・・・馬廻りの二百二十石。背丈は五尺九寸、筋肉質の引き締まった見事な体で毛深い。刀法を修業に日向の国の高鍋へ行く。現在は藩の道場で師範をしている。
江木重三郎・・・千世の兄。百九十石の納戸役を務める。主税介より四歳年長。主税介のことを古武士の風格と褒めている
深松伴六・・・主税介の親友で、七十五石の近習番。決闘の知らせを持って五大家を訪れるが・・
岩間勇作・・・五大家の家士。
四日のあやめ あらすじ
二月下旬の寒い朝、千世は居間で鏡に向かっていると、家士の岩間勇作が来客を告げた。その客は夫の親友、深松伴六で「大事が起こったからすぐ会いたい」と伝えた。千世は鏡に自分ではない老婆の顔が映る幻をみて不吉な予感に襲われる。深松の知らせは、馬廻りと徒歩組の決闘が始まったというものだったが、千世は良人を危険に晒したくない一心で、彼の来訪を知らせず。良人を寝かせたままにしておいた。
四日のあやめ アリアの感想と備忘録
千世が罪悪感に苦しみながらも良人にはその真意を隠し続ける場面、そして家中で良人の不参加が非難される中、自分の行動がどんなに悪かったかを理解し、離別さえ覚悟する場面、四日のあやめと兄から呼ばれた彼女の成長する姿が印象的でした。そして主税介がそんな未練な千世を丸ごと受け入れて共に成長することを決意する場面も良かったです。彼も千世を愛していたのですね。夫婦の絆が試され、二人が互いに理解しあうまでの過程は、現代にも通じる愛と信頼の話だと思いました。千世の判断が正しいのか間違っているのかは簡単に言えませんが、その葛藤と成長が、この話に深みを与えていました。