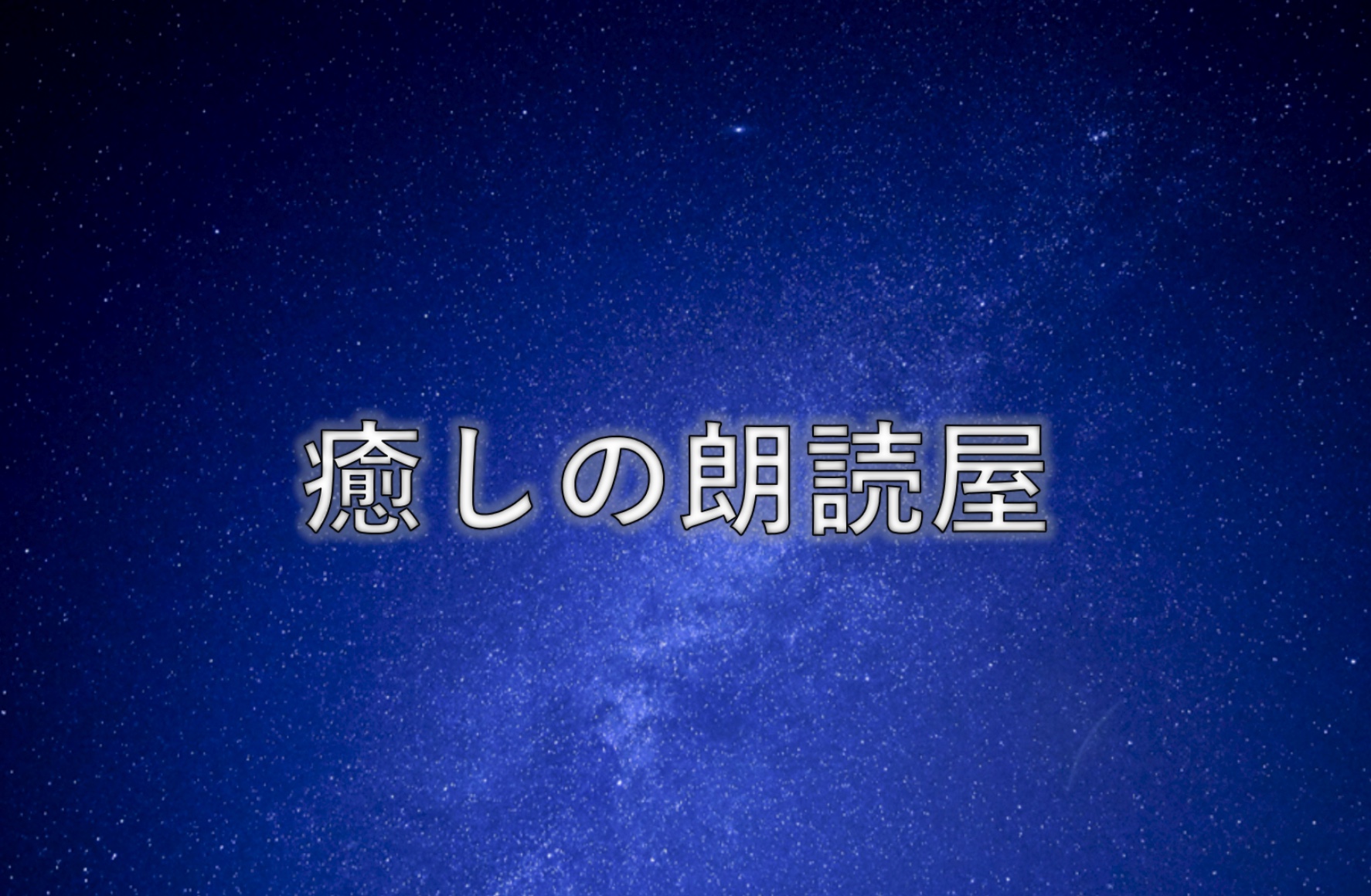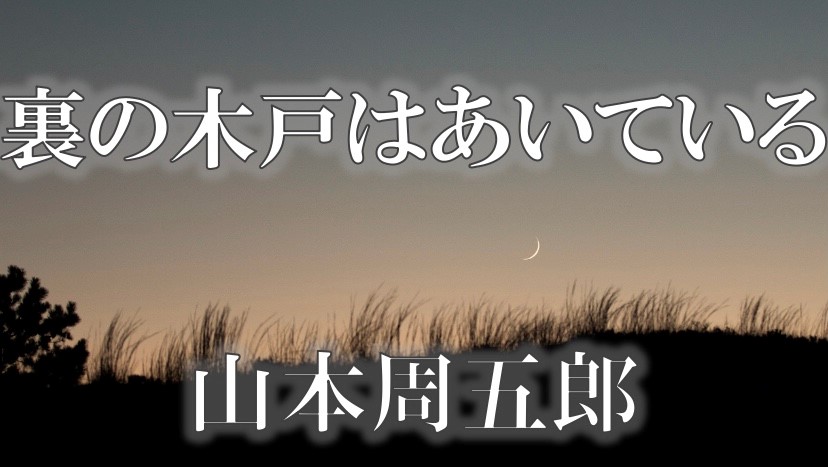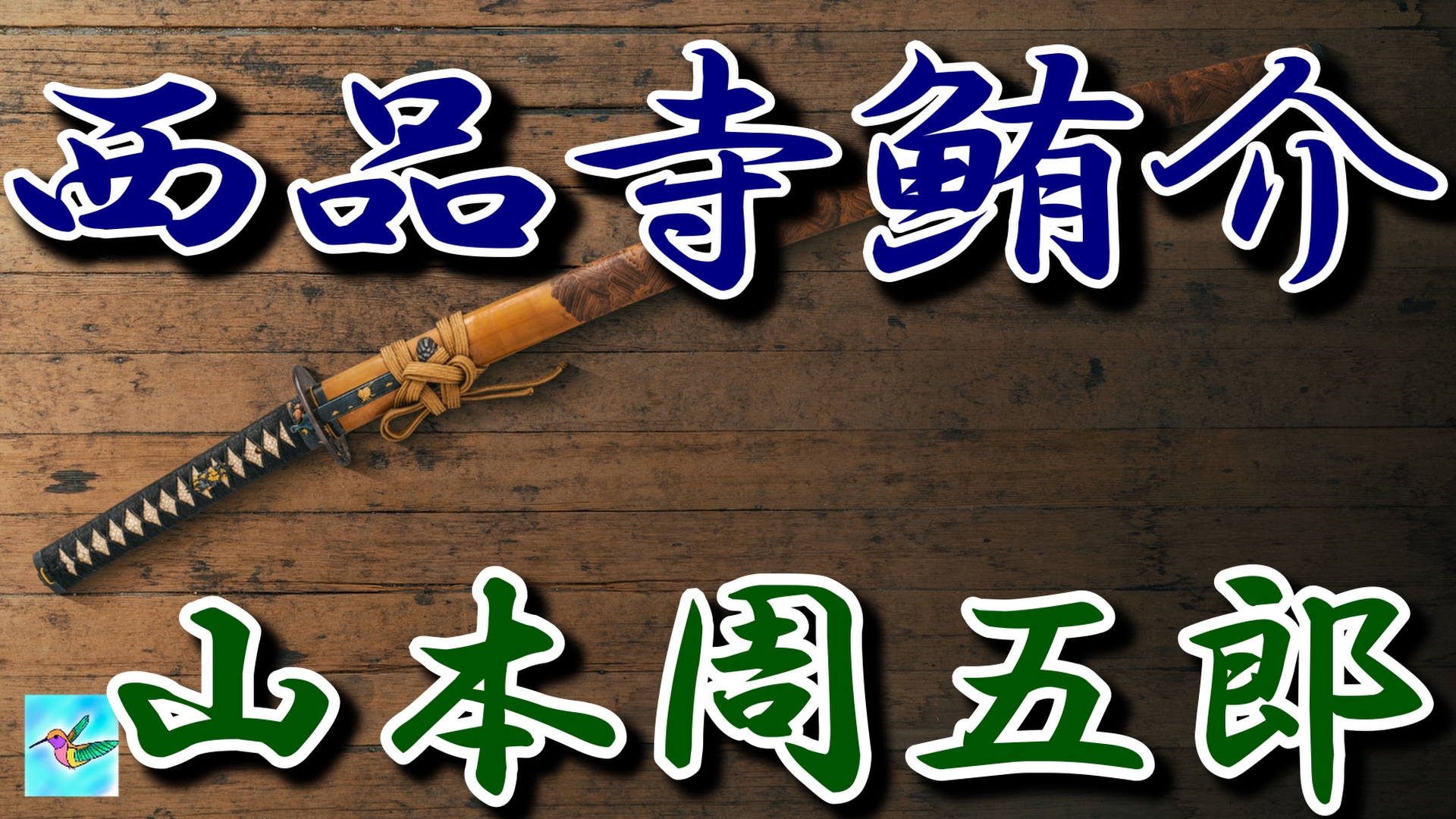【朗読】裏の木戸はあいている 山本周五郎 読み手アリア
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「裏の木戸はあいている」(昭和30年)です。高林の家の裏木戸の内側に金の入っている箱が掛けてあり、窮迫している者は誰でもはいって箱の中から必要なだけ持って行き、返せるときが来たら返せばよかった。この無償で借りることができるお金が入った箱をめぐる話です。
裏の木戸はあいている 主な登場人物
高林喜兵衛・・・家に出入りの吉兵衛一家に起こった出来事から「裏の木戸」のことを思いつく。
和生久之助(にぎゅうきゅうのすけ)・・・重職の家柄で、寄合肝煎を勤める。喜兵衛と少年時代から誰より親しくつきあっている。
藤井十四郎・・・喜兵衛の義兄、放蕩者で喜兵衛以外の家族は匙を投げている存在。
裏の木戸はあいているのあらすじ (※ネタバレを含みます)
高林の裏木戸の内側の箱の金は貧窮したものが、顔も見られず、証文や利息なしに必要なだけ金を持って行き、返せるときが来たら返せばよいし、返せなければ返さなくともよいので、貧窮した人たちはその「裏木戸の箱」をたのみにしていた。喜兵衛はただその箱を調べて、金があればよし、無くなっていれば金を補給していた。彼はその箱を家督相続してからずっと続けていた。喜兵衛は幼い頃、出入りの職人一家が、わずかな金に困って全員死んでしまった、という経験をする。その時、周りの大人たちは口先だけで何もしなかった。自分は何かできることをしようと思い、それがきっかけで「裏の木戸の箱」を始めたのだ。
裏の木戸はあいている 覚え書き
酒色(しゅしょく)・・・飲酒と色事。
放逐(ほうちく)・・・その場所や組織から追い払うこと。
柔和(にゅうわ)・・・性質や態度が、ものやわらかであること。また、そのさま。
薬礼(やくれい)・・・治療や投薬に対して、石に払う代金。くすりだい。
饐える(すえる)・・・飲食物が腐って酸っぱくなる。
雑用(ぞうよう)・・・こまごましたものの費用、雑費。
窮迫(きゅうはく)・・・行き詰まってどうにもならなくなること。
小人(しょうじん)・・・武家で、雑役に従った身分の低い人。
凌ぎ(しのぎ)・・・苦しい局面や辛いことを、なんとか持ちこたえて切り抜けること。
下人(げにん)・・・身分の低い者。
害悪(がいあく)・・・他に災いを与えるような、よくない事。
救恤(きゅうじゅつ)・・・困っている人に見まいの金品を与えて救うこと。