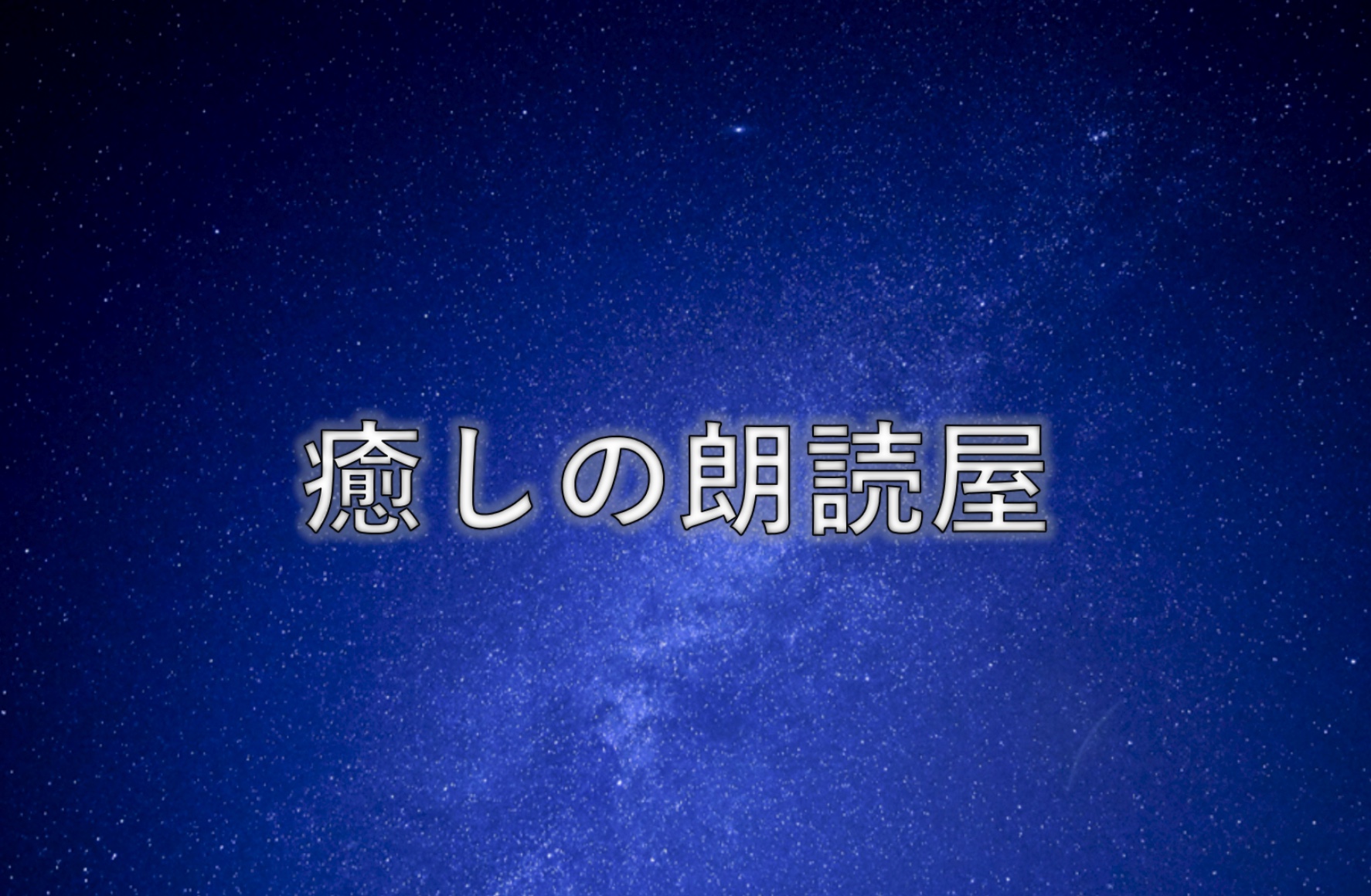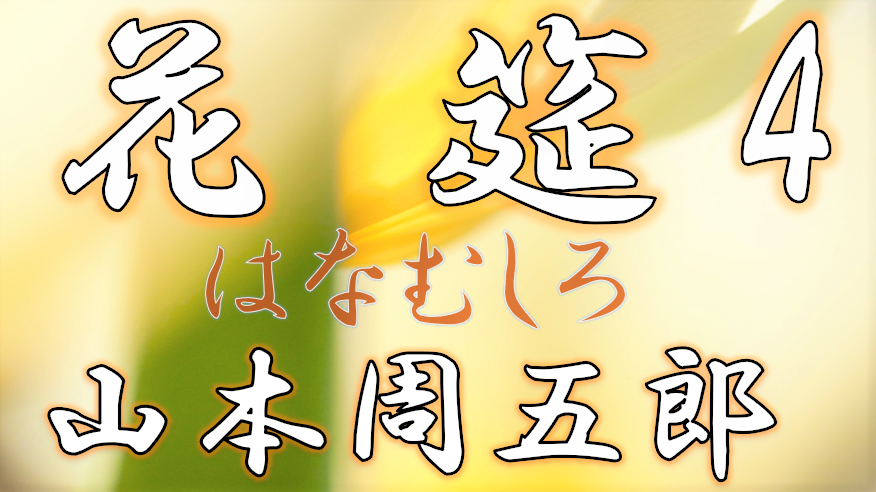【連載朗読】花筵3 山本周五郎 読み手アリア
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「花筵3」です。そのころ美濃のくに大垣の城主は戸田うねめのしょう氏英という人であった。氏英は三十九歳でまだ壮年だが、近頃健康が思わしくなく、養嗣子のはなしが出ていた。大垣藩の国家老の大高舎人は馬廻りから昇進した出頭人であった。十余年も政治の中枢を握り、古くから名門や重臣たちの支持があった。その支持が政治の癌になったのだが、重臣や名門の人たちは舎人を支持することで自分たちの利益を確実にしていた。大垣は木曽川、長良川、揖斐川の三つの河の流域にあるためしばしば非常な洪水にみまわれていた。薩摩の島津氏によって大規模な治水工事が行われたことがあったが、大垣は大垣として年々かなり多額な費用を治水のために支出していた。そしてここに一種の利権のようなものが生じた。その治水工事は重臣たちの廻り持ちで、工事の監査が正確になされず、費用の使途に多くの疑問があった。そのうえ工費の予算追加が度々で、それを捻出するために年貢の増し上げが繰り返されるという悪政に近い状態が現れてきたのである。
花筵3 主な登場人物
奥村喬所・・・お市の父。大垣藩老職。
奥村弁之介・・・お市の四番目の兄。
戸田采女正氏英・・・大垣藩藩主。七歳のとき家を継いだ。幕府の奏者番と新将軍から諸大名に領地確認を意味する沙汰書を出す役を申し付かり、どちらも体も心も疲れる役目で、それ以来健康を衰えている。
大高舎人・・・馬廻りから昇進した出頭人。口巧者で人に執入ることがうまく小才がきく。人物も非凡で才能もあったが・・・
花筵3 覚え書き
出頭人(しゅっとうにん)・・・主君の寵愛を得て、権勢をふるっている者。
執入る(とりいる)・・・目上の人の期限をとって気に入られようとする。
小才(こさい)・・・ちょっとしたことをその場に合わせてうまく処理する能力。
情実(じょうじつ)・・・個人的な利害、感情がからんで公平な取り扱いができない状態や関係。
権益(けんえき)・・・権利と利益。
枢要(すうよう)・・・物事の最も大切なところ。
宰領(さいりょう)・・・監督する役。
私曲(しきょく)・・・自分の利益だけをはかること。
欺謀(ぎぼう)・・・策略によって欺かれること。