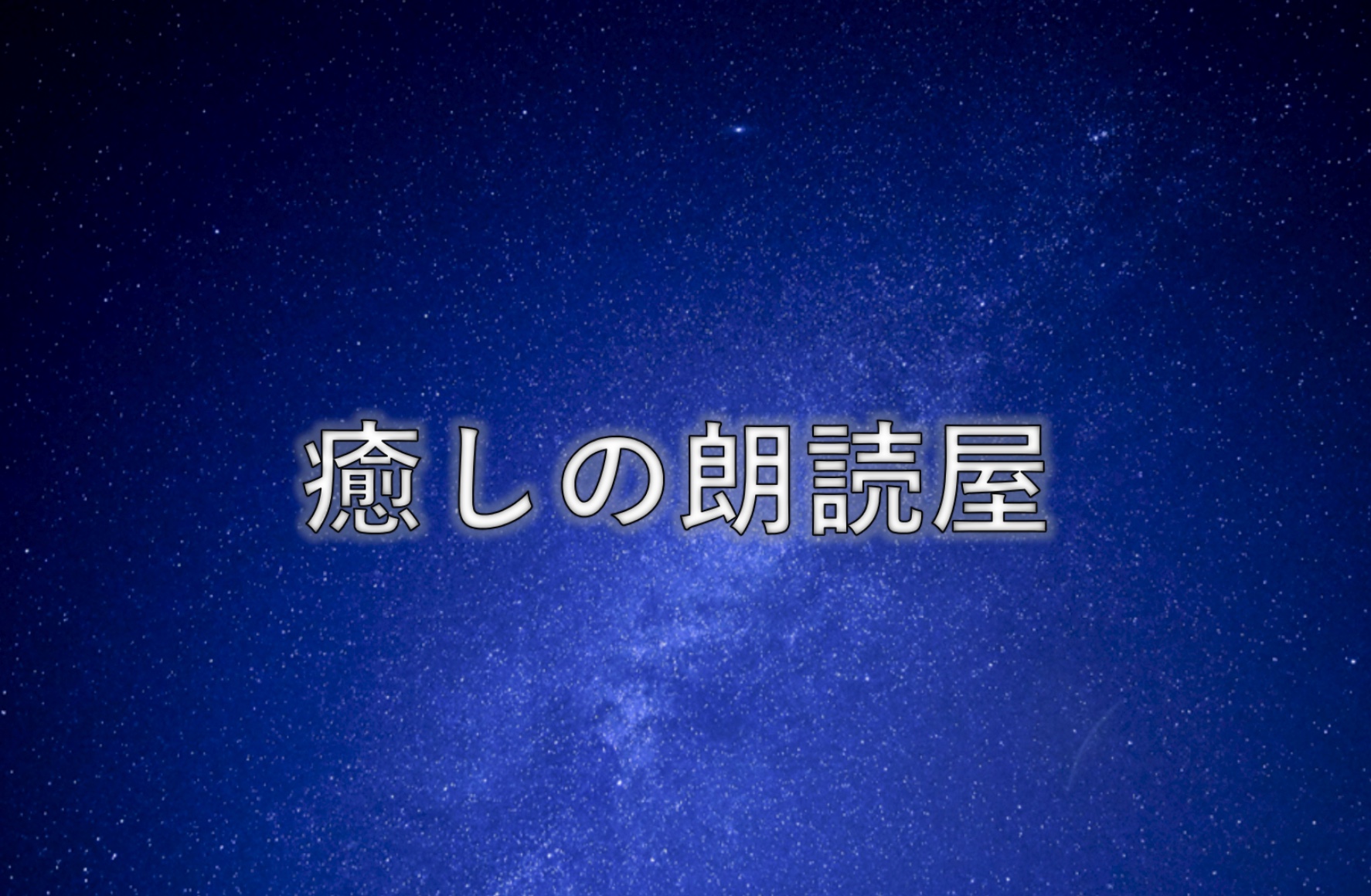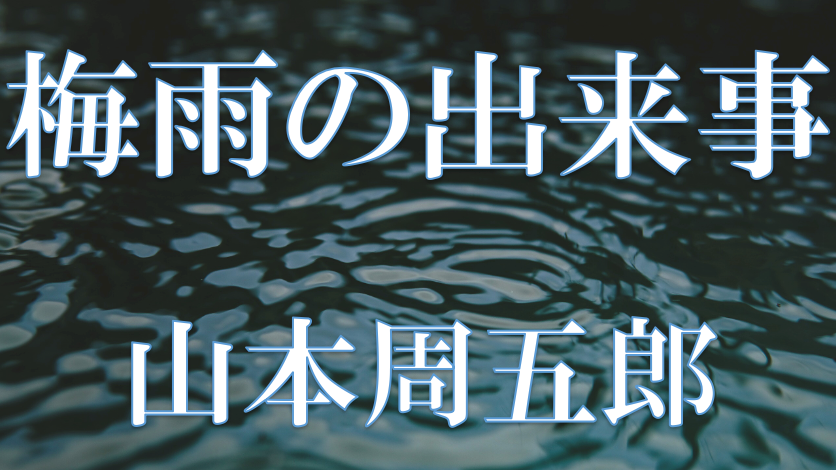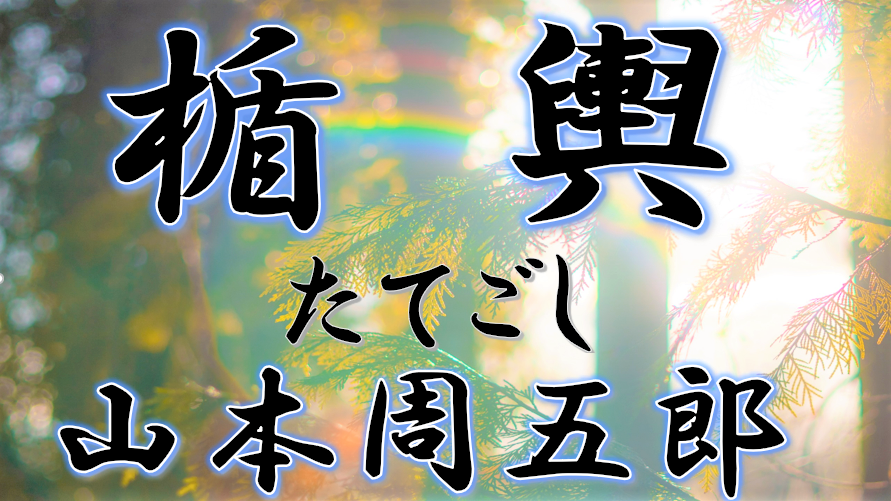【朗読】枡落し 山本周五郎 読み手アリア
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「枡落し」です。この作品は、昭和42年63歳の作品です。小説新潮に掲載されました。「ねえ、死にましょうよ――」世間の冷たい視線と極貧の暮らしに絶望し心中を願う娘・おうめと、苦しみの中でなおも生き抜く道を探し続ける母・おみき、運命に翻弄されながらも必死に未来を掴もうとする親子の愛と選択を描いた、涙なしには読めない感動の江戸人情ドラマです。
枡落し あらすじ
江戸の片隅で、貧しさと世間の冷たい視線に晒されながら生きる母・おみきと娘・おうめ。彼女たちの運命は、夫であり父であった千太郎の罪によって大きく狂わされた。千太郎は賭場で人を殺し、囚われの身となる。近所の人々は、かつて親しく助け合っていたはずのおみきとおうめを「人殺しの家族」と嘲笑し、見捨てた。絶望したおうめは「おっ母さん、一緒に死にましょう」と訴えるが、おみきは「生きること」を選ぶ。彼女たちのそばには、幼なじみの芳造がいた。幼い頃から母親に愛されず、寒い川で蜆(しじみ)を取りながら生きてきた芳造は、おうめに想いを寄せ、「一生を賭けてもお前を幸せにする」と誓う。おみきは、かつての自分と千太郎を重ねながらも、娘の幸せを願い、二人の未来を見守ることにする。そんな中、千太郎が「無実の罪で捕らわれている」と告げる男・幸助が現れる。おみきは心を揺さぶられる。
枡落し 主な登場人物
◆ おみき(母)
本作の主人公。鼈甲(べっこう)の加工職人。かつては裕福な家の娘だったが、父の死後、夫・千太郎の素行が悪化し、貧しい暮らしへと転落。夫が人殺しの罪で捕らえられた後、世間から冷たい目を向けられながらも、娘・おうめと共に懸命に生きることを選ぶ。過去の苦しみや後悔を抱えつつも、娘の幸せを最優先に考えている。
◆ おうめ(娘)
17歳。母と共に貧しい暮らしを送るが、父の罪によって更なる苦難を味わう。世間の偏見や辛い過去に耐えられず、母に「一緒に死にましょう」と訴えるほど絶望していた。しかし、幼なじみの芳造の存在に救われ、やがて彼と共に新しい未来を築こうと決意する。
◆ 千太郎(父)
おみきの夫であり、おうめの父。かつては真面目な職人だったが、義父(おみきの父)が亡くなった後に酒や博打に溺れ、家族を顧みなくなる。おみきやおうめから金や物を奪い、暴力を振るうようになった。最終的に賭場で人を殺し、囚われの身となる。物語終盤で八丈島へ島流しにされたことが判明し、もう二度と戻ることはない。
◆ 芳造(よしぞう)
23歳。「伊予巴(いよともえ)」という鼈甲屋の職人で、おうめとは幼なじみのような関係。幼少期に母親に愛されず、寒い川で蜆(しじみ)を取りながら生きてきたという過酷な過去を持つ。おうめを深く愛し、「一生をかけて幸せにする」と誓う。千太郎の冤罪疑惑を調べ、詐欺師の企みを見破る。最終的に、おうめとの結婚を見据えて自分の店を持とうとする。
◆ 縄屋 喜六(なわや きろく)
猿屋町の家主で、御徒町の差配・吉兵衛の幼なじみ。おみき親子が引っ越してきた後も、親身になって世話を焼く。威勢のいい性格だが、人情深い。
◆ 吉兵衛(きちべえ)
御徒町の差配(大家のような役割)。千太郎が捕まる前からおみき親子の境遇を知っており、何かと助け舟を出していた人物。
◆ 幸助(こうすけ)
千太郎と同じ牢にいた男。おみきに「千太郎は無実だ」と偽りの話を持ちかけ、金を騙し取ろうとする詐欺師。芳造によって計画を見破られ、番所(役人)に突き出される。
◆ 大蛇の辰(だいじゃのたつ)(架空の人物)
幸助が「千太郎の無実を証言できる」と話した架空の生き証人。実際には存在しなかった。
◆ おみきの父
鼈甲職人として名高かったが、酒好きで早くに亡くなる。おみきを溺愛し、彼女に千太郎との結婚を決めさせた人物。千太郎の本性を見抜けなかったことが、娘の人生を狂わせたともいえる。
◆ 芳造の母
夫をこき使いながら、若い男たちと酒を飲んでいたという奔放な女性。芳造が幼い頃に蜆売りをさせ、彼の人生に深い傷を残した。最終的に芳造は母を捨て、二度と会うことはなかった。
アリアの備忘録
おみきとおうめは、千太郎の罪によって「人殺しの家族」として世間から冷たい目を向けられます。かつて親しく付き合っていた人々も手のひらを返したように態度を変え、親子は孤立してしまいます。人々の関心や善意は状況次第でいとも簡単に変わる という現実、そして世間とは非情なものであり、助けてくれる人もいれば簡単に見捨てる人もいる。人は結局、自分の力で生き抜かなければならないということでしょうか。また、冒頭でおうめが「死にたい」と訴えるほど絶望しています。しかし母・おみきは考え続け、結局「生きていく道を探す」ことを選びます。おうめは最終的に幸せになることを選んで、新しい道を開きます。そしておみきと千太郎の夫婦は、愛情のない結婚でした。おみきは「夫を本当に愛したことがあっただろうか?」と自問し、千太郎がぐれたのは「自分のせいでもあるのか」と考えます。一方、おうめと芳造の関係は、互いに深い愛情があるからこそ成り立っています。芳造は、おうめのために戦い、彼女を幸せにしようと努力する。愛で人は変わることができるということですね。最終的におみきはおうめの幸せを守ることを選びました。
この物語はおみきの視点を中心に描かれ、千太郎の気持ちや彼の視点は一切描かれていません。千太郎がなぜぐれたのか、なぜおみきや娘を顧みずに暴力や博打に走ったのか、彼自身の内面が語られることはなく、すべておみきの視点から「結果」として語られています。これは周五郎氏の意図的な構成かもしれません。物語のテーマは「おみきとおうめがどう生きるか」にあるため、千太郎の事情や心情を掘り下げることよりも、彼が「妻と娘を苦しめる存在」として機能することが重視されたのではないでしょうか。また読者に「あの男は本当にどうしようもない奴だったのか?」と考えさせる余地を残しているとも言えます。千太郎の気持ちは描かれないままですが、読者は彼の境遇を知ることで、彼なりの絶望や苦しみがあったのではないか、と想像することもできます。千太郎の内面を描かないことで、おみきやおうめの苦悩がより際立ち、物語の焦点がぶれないようになっているのかもしれません。そう考えると、千太郎の描かれ方はとても計算されたものだったのではないか、と思えます。お読みいただきありがとうございました。