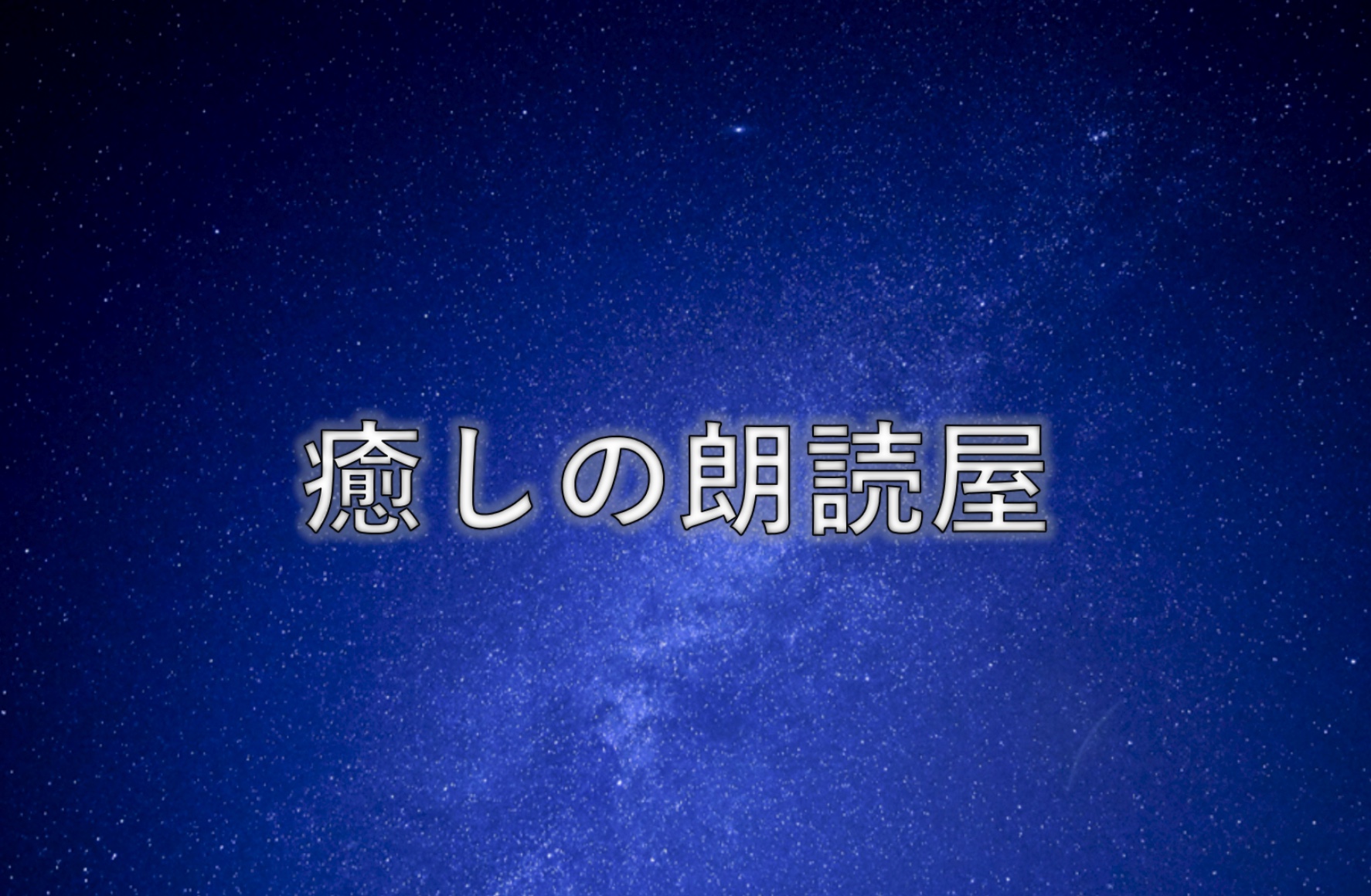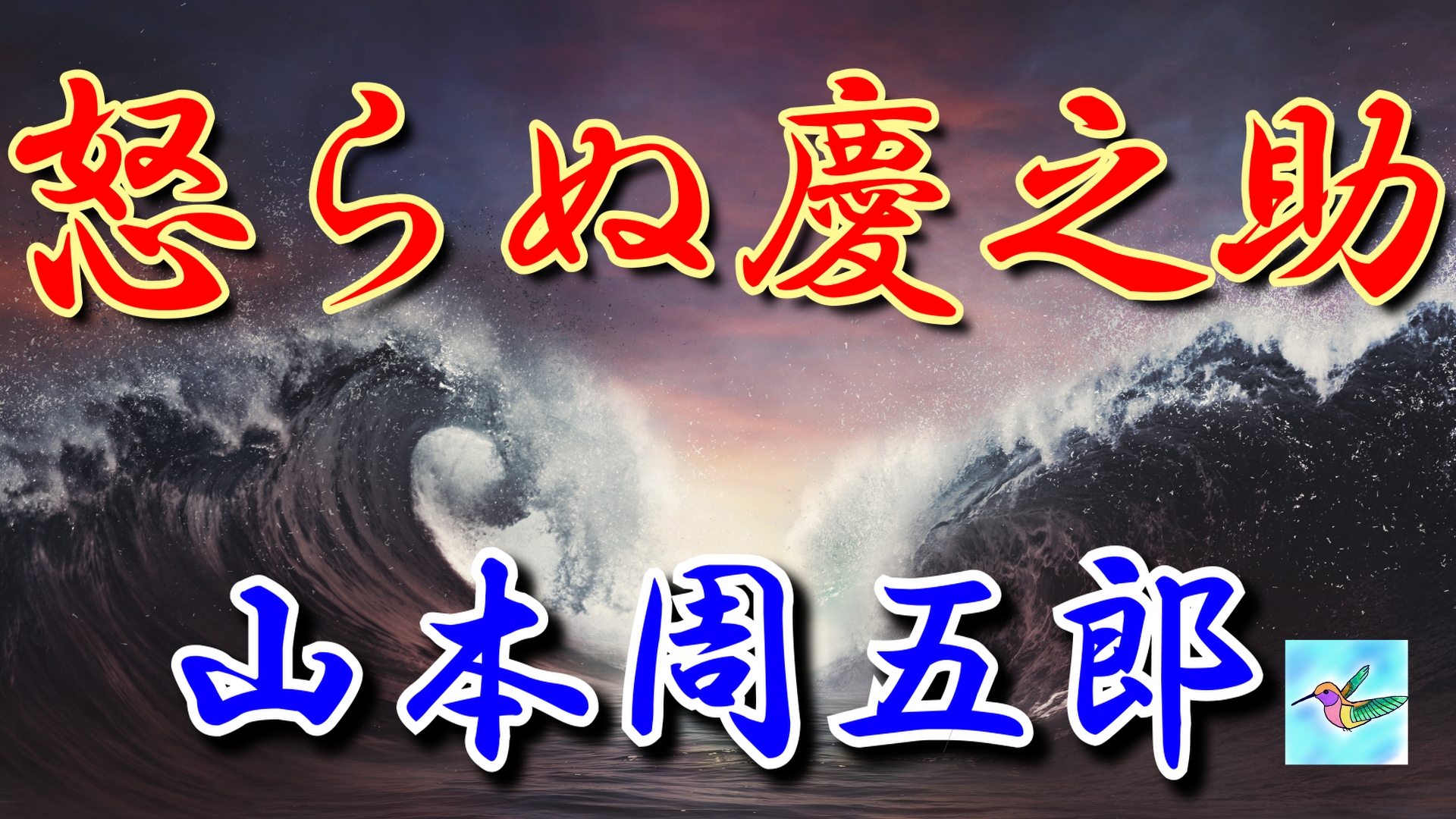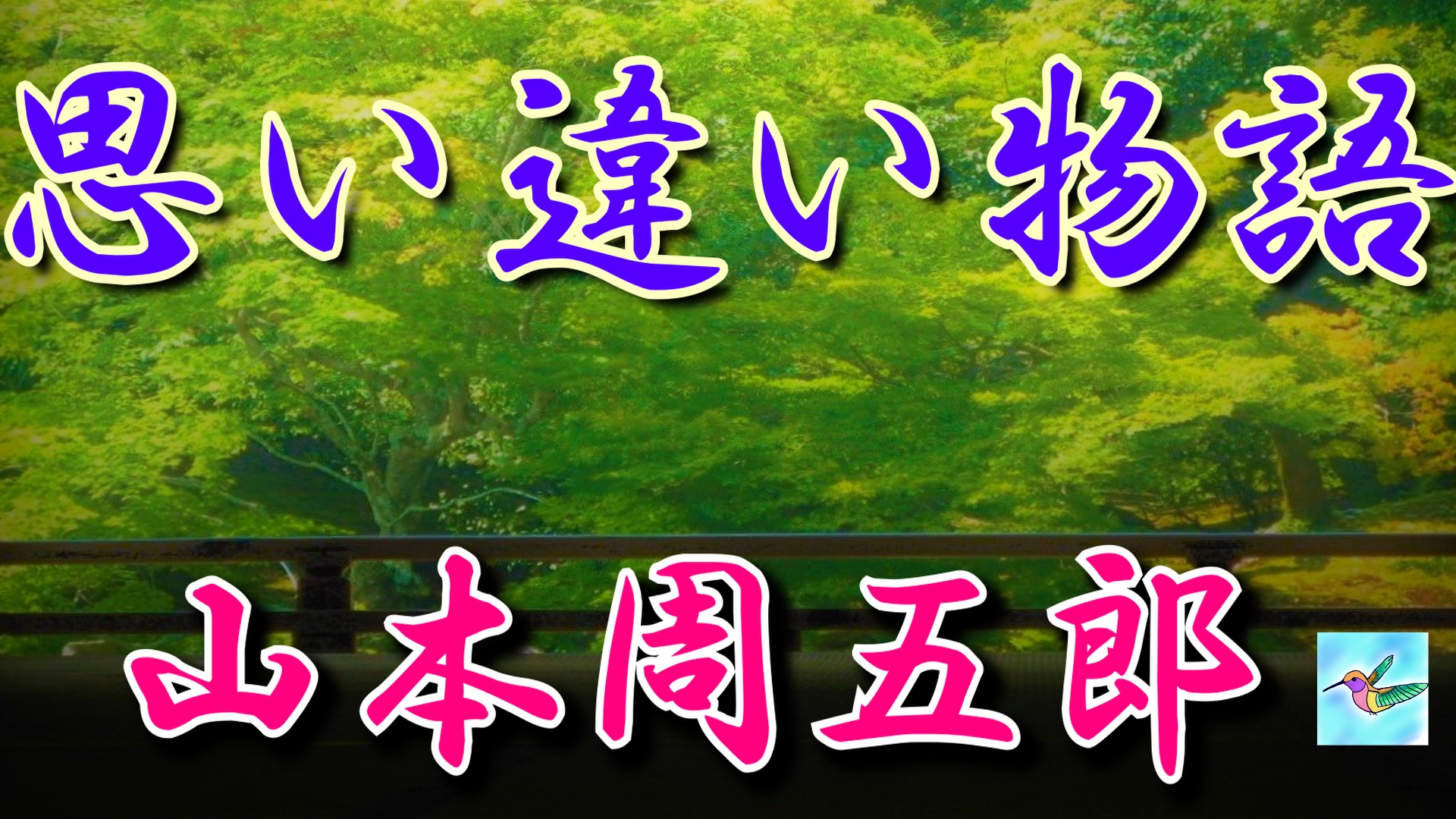【朗読】御意討ち秘伝 山本周五郎 読み手アリア
こんにちは!癒やしの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「御意討ち秘伝」です。この作品は、昭和12年34歳の作品です。藤次郎の恋によく似てますが終わり方が違っています。どうぞその違いをお楽しみください。
御意討ち秘伝 主な登場人物
高松絃次郎・・・温厚で控えめな性格の武士。深江に心を寄せていたので彼女の頼みを聞いてしまう。
藤枝清三郎・・・絃次郎と共に道場の「三羽烏」と呼ばれていた。酒に溺れてしまう。
深江・・・絃次郎と藤枝の師匠、貝原次郎左衛門の娘二十歳。藤枝をずっと前から愛している。
文枝・・・深江の妹で18歳。派手ではないが、思慮深く、温かい心を持つ。
貝塚次郎左衛門・・・小田原藩で道場を構える剣術の名手。深江と文枝の父親。総試合で勝った者に深江を目合わせることを決める。
堀越市松・・・三羽烏の一人。酒癖が悪く破門になる。魔剣の市松と呼ばれた。
倉本孫市・・・絃次郎の友人。
御意討ち秘伝 あらすじ
物語の中心は、剣術道場の心優しく穏やかな武士、高松絃次郎と、その師匠の娘である深江、そして深江の心を掴んだもう一人の武士、藤枝清三郎の複雑な関係です。師匠の長女、深江は酒癖が悪く、心が乱れがちな藤枝を愛し、彼を立派な武士に戻したいと願っています。そのため彼女は絃次郎に、明日の試合でわざと藤枝に負けて彼を勝たせてほしいと懇願します。しかし武士として誇り高き絃次郎はこれを断り、自分の信念を貫こうとします。試合では藤枝が勝利し、深江と結ばれますが、その後も藤枝は立ち直ることなく再び堕落します。最終的に藤枝は、三羽烏の一人で破門になった堀越市松に斬られて命を落としますが、実際には藤枝の名誉を守るために・・・・・という話です。物語は絃次郎の深い義理と愛情、そして彼の心を密かに見守り続けた深江の妹の文江の愛情がぴったり合ういい話です。
アリアの感想と備忘録
剣術道場の若い武士たちの人間模様と感情の揺れ動きが繊細に描かれていて、特に「武士道の誇り」と「人間としての弱さや愛情」が交錯するところに心を動かされました。特に絃次郎の誠実で温厚で控えめで誇り高き性質というのは正に武士らしい武士でとても好ましいです。自己犠牲を払っても藤枝の名誉を守ることを選んだ武士の誇りと人間としての優しさのバランスが絃次郎の魅力ですね。物語の最後に描かれていた深江の妹、文江と絃次郎の新たな関係で、絃次郎も新たな道を歩み始めることになります。この結末が、物語全体の緊張感や悲劇的な展開の中で、一つの希望や救いを感じさせました。