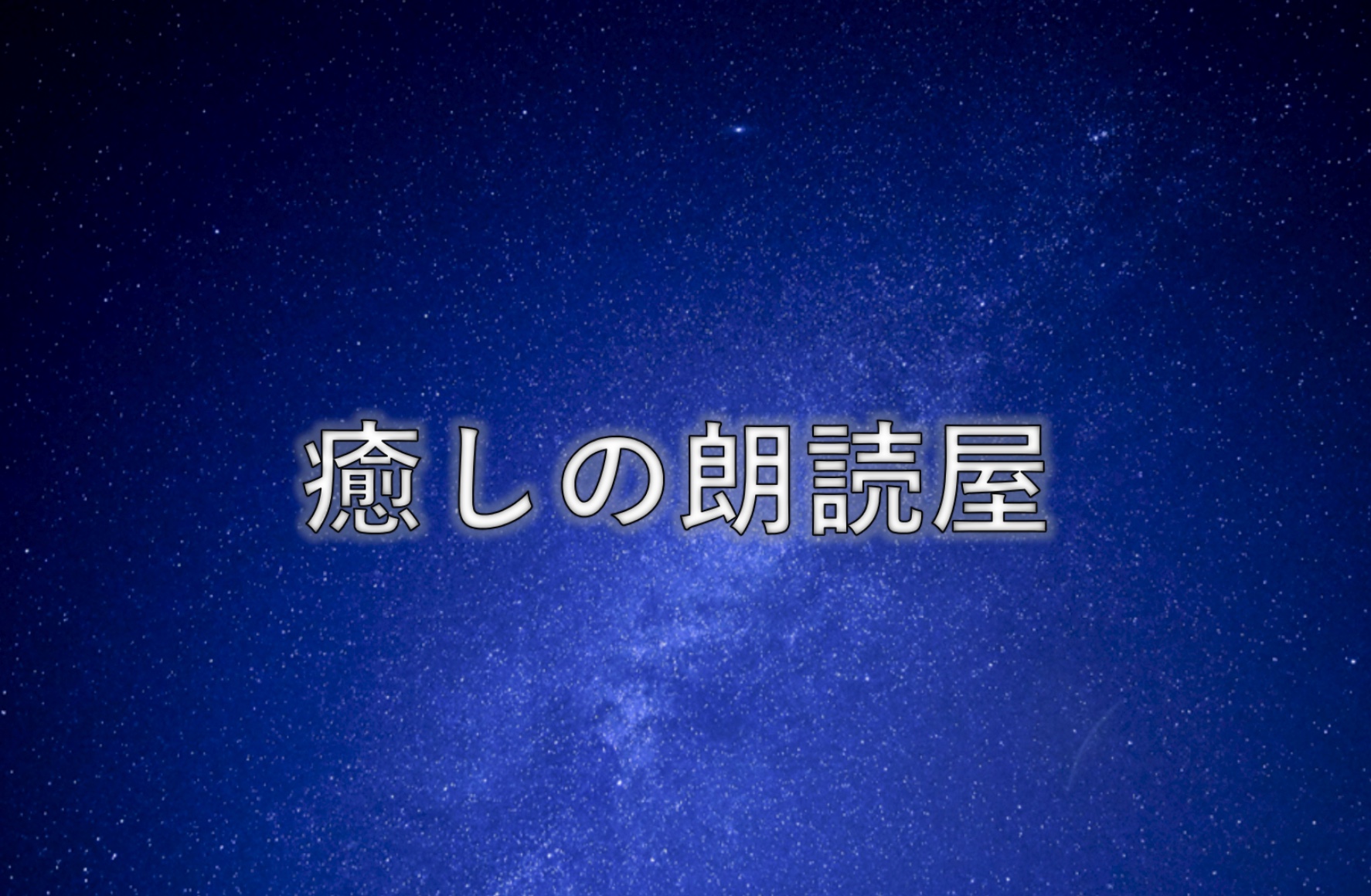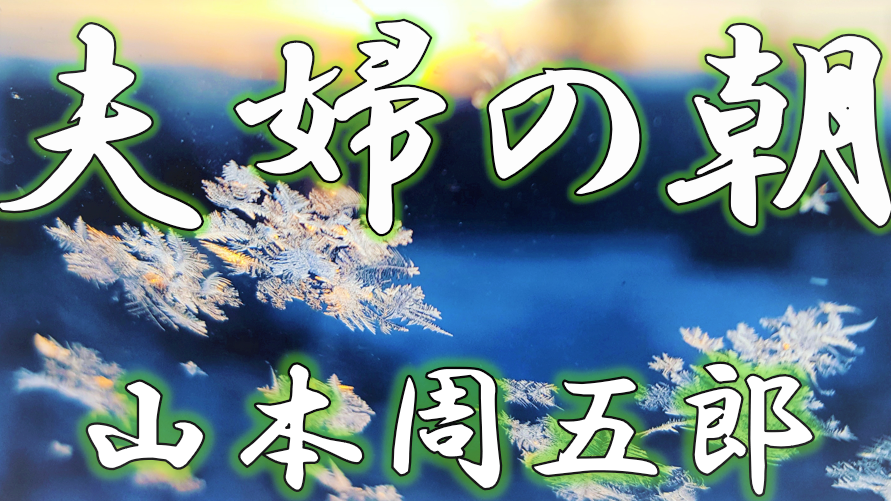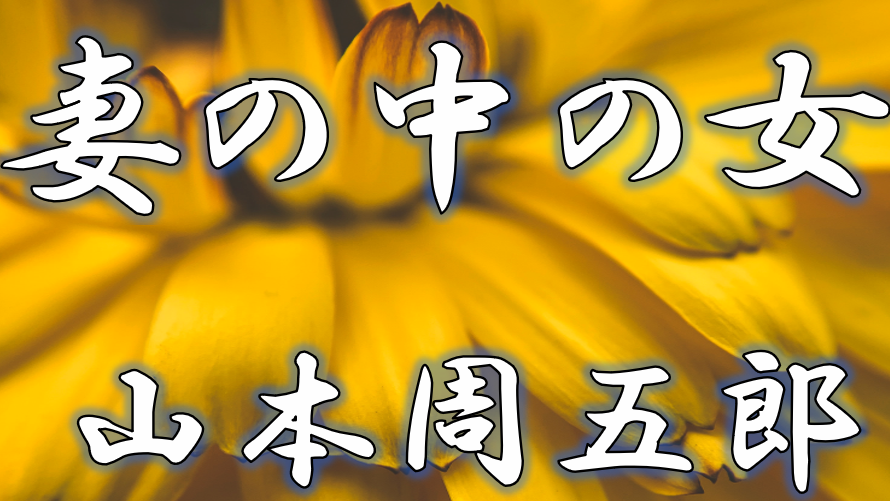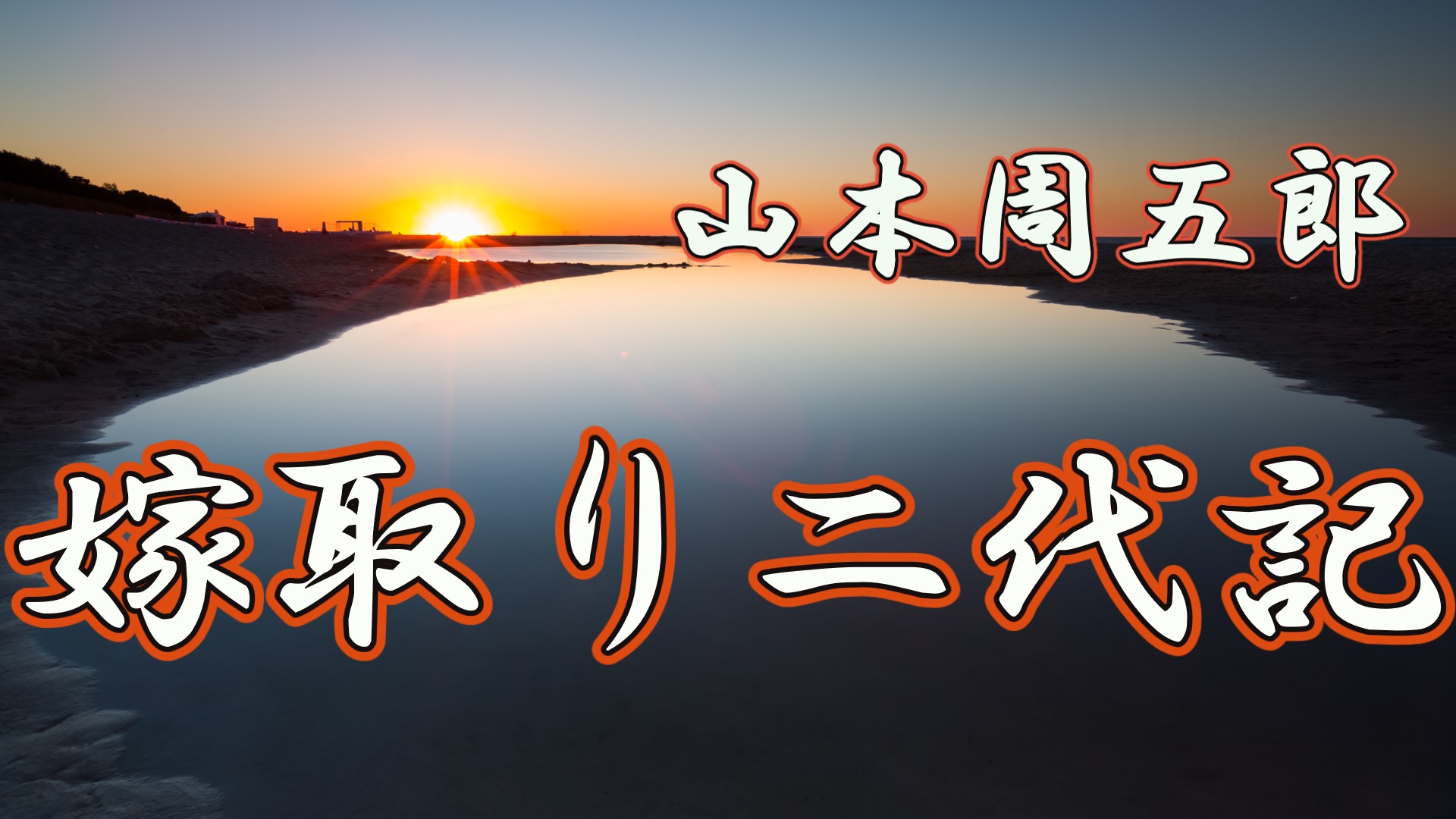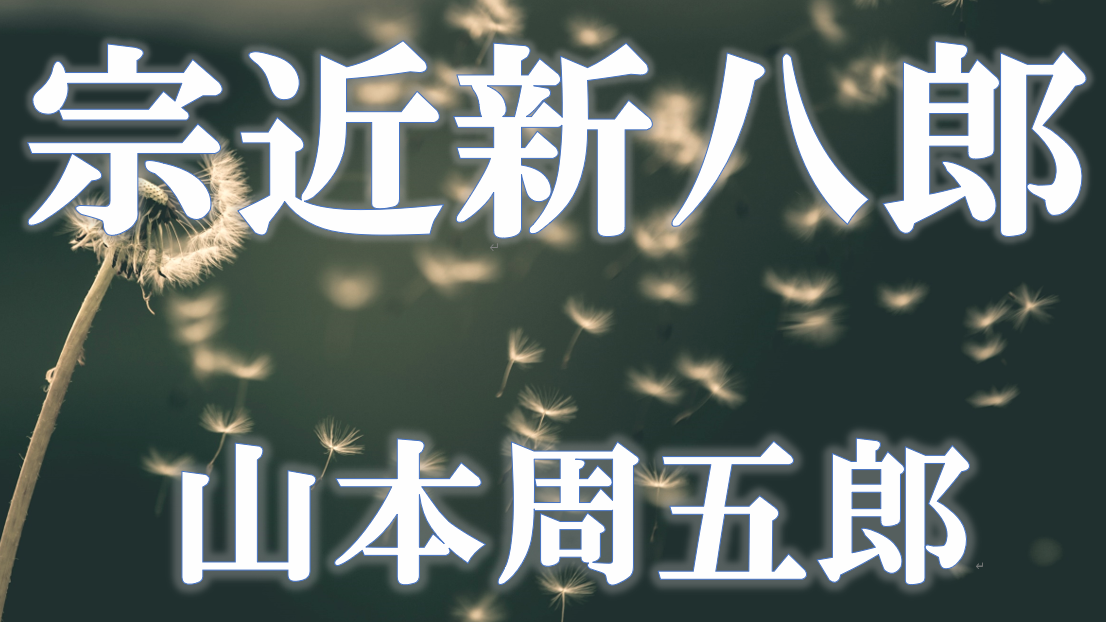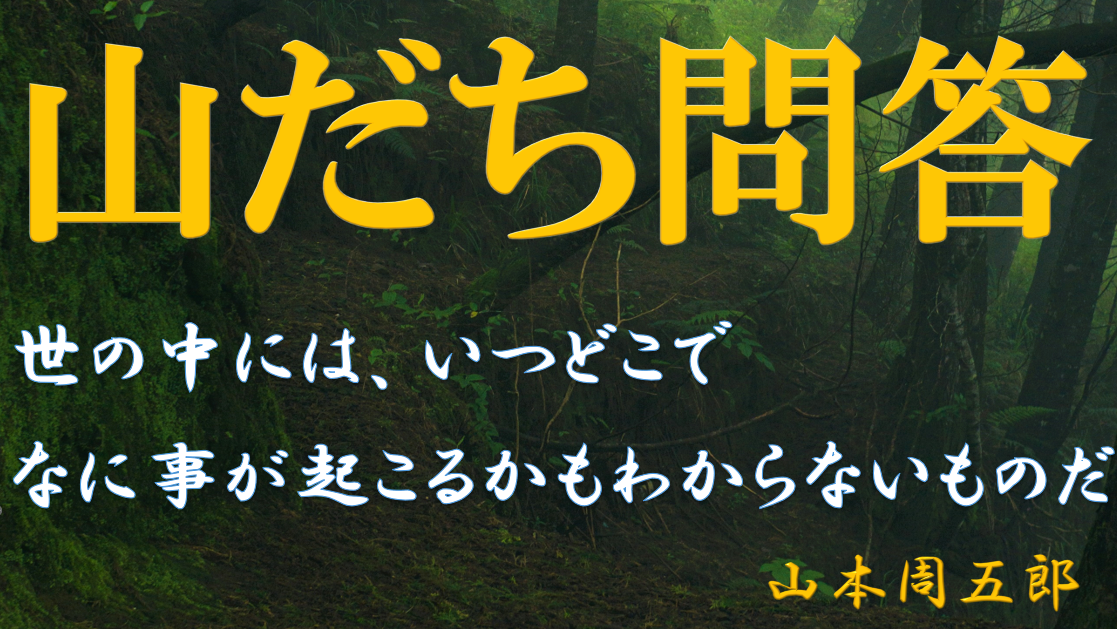【朗読】夫婦の朝 山本周五郎 読み手アリア
こんにちは!癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「夫婦の朝」です。この作品は、昭和16年婦人倶楽部に掲載されました。(扇野/新潮文庫)主人公のお由美は、加納家へ嫁してきて足掛け三年、苦労を知らぬ明るい気質で、夫に愛され、幸せに溢れる生活を送っていた。夫の三右衛門は口数が少なく、濃い一文字眉と、髭の剃り跡の青い角ばった顎はちょっと近づき難いほどだったが、表情や言葉には温かな底の深いものを感じさせた。ある日、お由美が婢のよねを連れて浅草寺へ詣でた帰りに寄った掛け茶屋で、茶汲み女がそばへ寄ってきて小さな紙片を差し出した。お由美は何の気もなく受け取ったが、その紙片には「新五郎」という署名が書かれていた。お由美は懸命に驚愕を抑えながら素早くその紙片を丸めた。
夫婦の朝 主な登場人物
お由美・・・二十三歳。絖のように白く引き締まった肌、黒い大きな瞳を持つ。良人の静かな愛情にしっかりと包まれているのを知って、「由美は仕合せ者よ。」と折に触れては心からそう呟くのだった。
加納三右衛門・・・二十八歳。食禄は五百石足らずだが、佐竹家でも名門の家柄。父が勘定奉行だったので、三右衛門は二十歳の時に江戸詰の留守役を命ぜられ、今では筆頭の席に就いている。
沼部新五郎・・・元秋田藩士。お由美の兄と友達で、一時は家族のように行き来していた。お由美は美貌で才子の新五郎に乙女心の恋心を燃え立たせたことがあった。
夫婦の朝 覚え書き
木偶(でく)・・・あやつり人形。
不審かる(いぶかる)・・・怪しくおもうこと。
衆評(しゅうひょう)・・・世間一般の人たちの批評。評判。
信(たより)
退っ引きならぬ(のっぴき)・・・引き下がったり撤退したりできない様子。
縄目(なわめ)・・・敵などにつかまって縄で縛られること。
破落戸(ごろつき)・・・一定の住所、職業を持たず、あちこちをうろついて人の弱点につけこんでゆすったり嫌がらせをする悪者。
執持(とりもち)・・・しっかりととらえて忘れないこと。
水掛け論(みずかあけろん)・・・両者が互いに自説にこだわって、いつまでも争うこと。
慄然(りつぜん)・・・恐れおののくさま。。恐ろしさにぞっとすること。
蹌踉(そうろう)・・・足元がしっかりせず、よろめくこと。
徒に(いたずらに)・・・無駄に。成果を伴わないさま。
覿面(てきめん)・・・まのあたり。
艱難(かんなん)・・・困難に出会って苦しみ悩むこと。