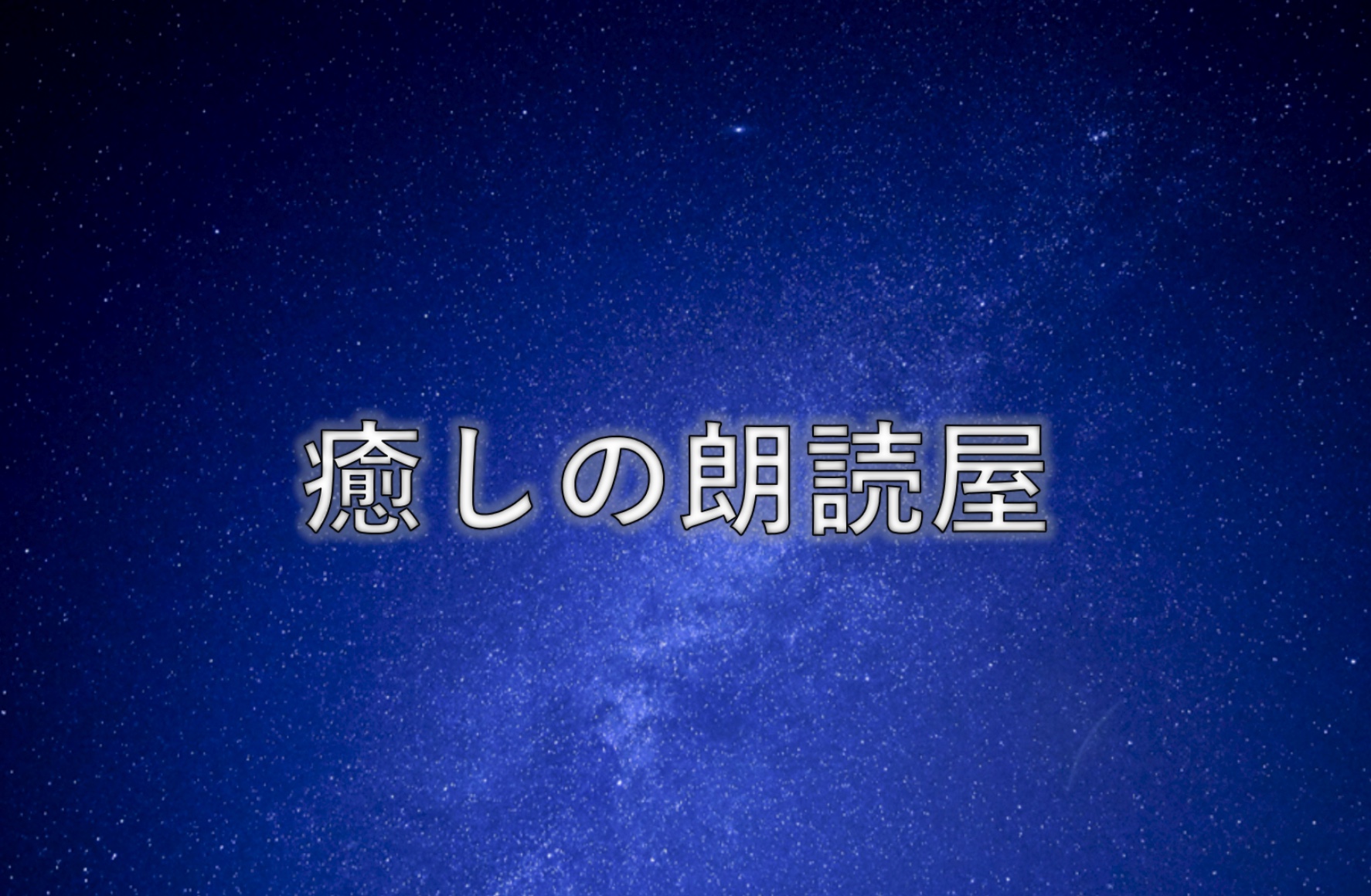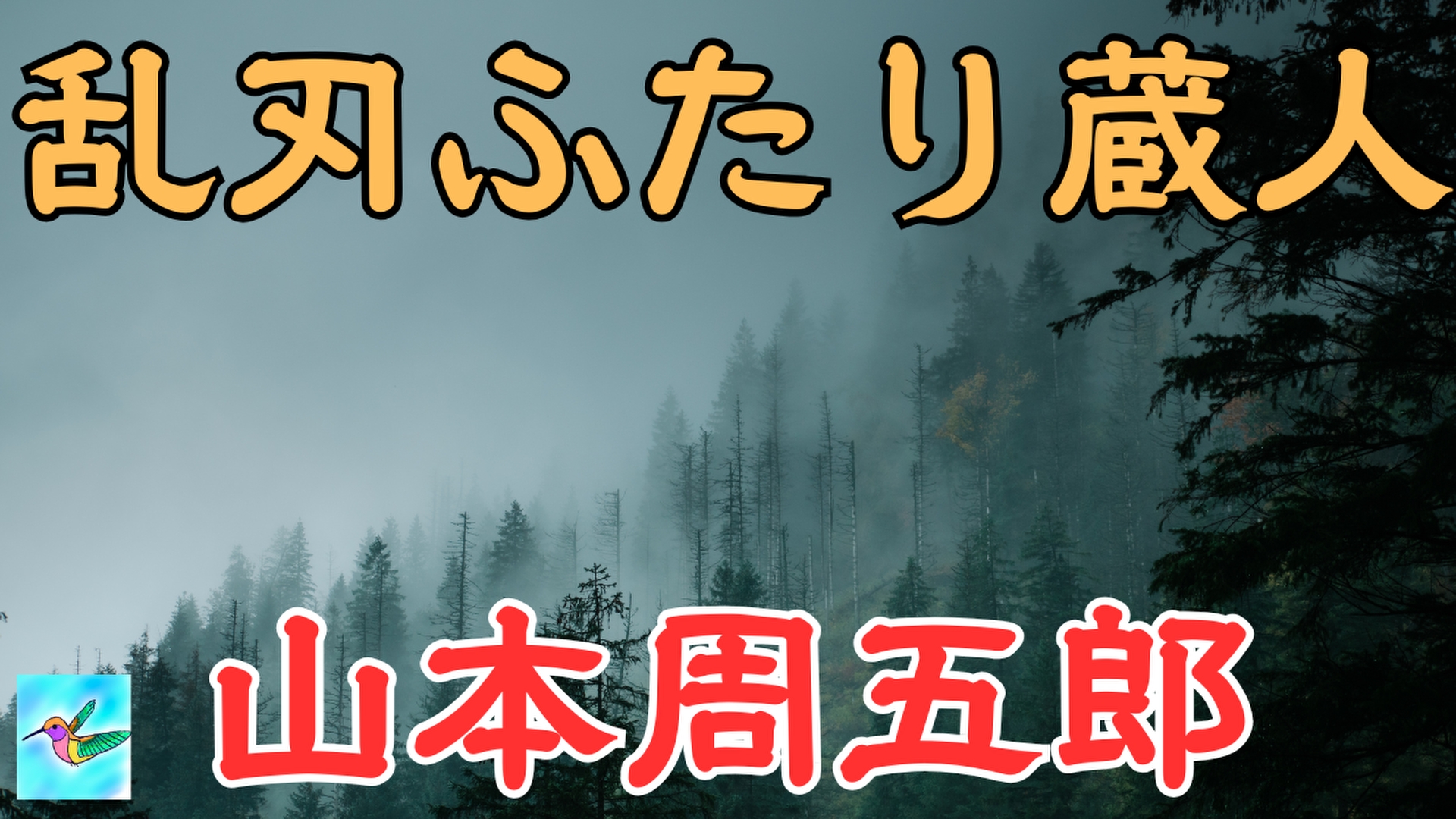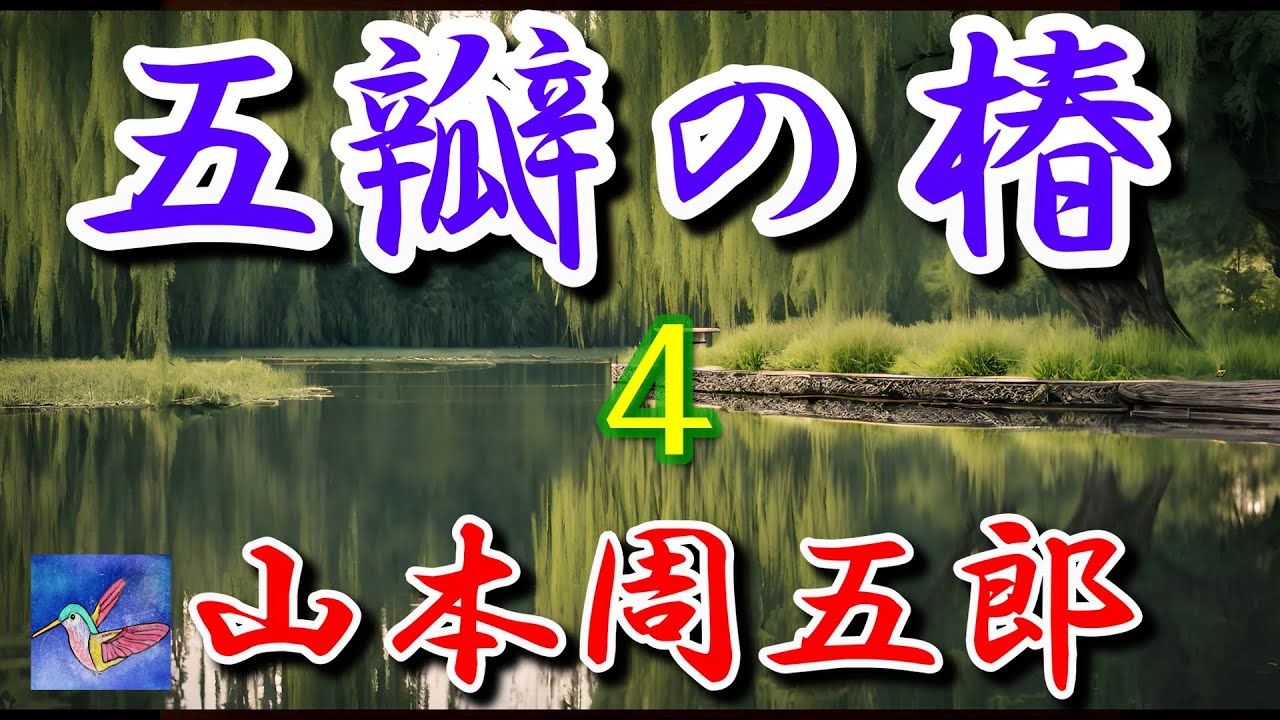三十二刻 山本周五郎 読み手 アリア
こんにちは 癒しの朗読屋アリアです。今回は、山本周五郎作「三十二刻」です。この作品は1940年昭和15年に書かれた武家もの短編小説です。「三十二刻」は、良人 主馬の出府中に舅によって実家に帰された宇女が、疋田家と山脇家の騒動を知り、兄に見送られ実家へ戻っていくところから始まります。
三十二刻 主な登場人物
疋田宇女・・・主馬の出府中に実家に帰されるが、疋田家の大事に実家へ戻り、全ての火薬を水浸しにし、酒瓶を全て打ち壊す。
疋田図書・・・秋田藩佐竹家の老職。自分の全ての希望をかけた自慢の息子を奪い取った家格の合わない嫁を憎んで実家に帰した。
疋田主馬・・・宇女の良人。中小姓で新婚半年で主君修理大夫義隆に持して江戸へ出府した。
六郎右衛門・・・疋田家の家扶。
三十二刻のあらすじ(※ネタバレ含みます)
疋田図書は譜代中での名門であり、山脇長門は廻座の肝入格である。二人は互いの性格が合わぬだけでなく、「廻座」と「譜代」と対立する勢力の代表的位置のため、長いあいだ悶着を繰り返してきた間柄だった。それがついに来るところへきた。長門は憤懣を暴力に訴え、図書はついに受けて起った。疋田図書は、七十二名の家士たちとともに門を閉ざし立て籠った。邸内には藩から委託された火薬製造所もあった。敵を屋敷に引き付け、機をみて一挙に決戦する考えだった。いよいよ合戦を待つばかりとなった時、火薬が全て水浸しになり、酒瓶も全て打ち壊されているという変事が起こる。屋敷内に敵と通謀する者があるのではないか・・・そこへ宇女が出てきた。黒髪を束ねて背に垂らし、白装束の腰紐をかたく締上げた凛々しい姿で、薙刀を右手に抱込んでいた。
三十二刻 覚え書き
懸隔(けんかく)・・・二つの物事がかけ離れていること。非常に差があること。
叢林(そうりん)・・・樹木が群がって生えている林。
水盃(みずさかずき)・・・二度と会えないかもしれない別れのときなどに、互いに杯に水を入れて飲みかわすこと。
名聞(みょうもん)・・・名声が世間に広まること。世間での評判・名声。
転封(てんぽう)・・・江戸時代、幕府の命令で、大名の領地を他に移すこと。
随身(ずいじん)・・・つき従って行くこと。また、その人。お供。
食客(しょっかく)・・・客の待遇で抱えておく人。
矜持(きょうじ)・・・自負。プライド。
横車(よこぐるま)・・・横に車を押すように、道理に合わないことを無理に押し通そうとすること。
悶着(もんちゃく)・・・感情や意見の食い違いから起こるもめごと。
憤懣(ふんまん)・・・怒りが発散できずにいらいらすること。腹が立ってどうにもがまんできない気持ち。
逆茂木(さかもぎ)・・・敵の侵入を防ぐために、先端を鋭くとがらせた木の枝を外に向けて並べ、結び合わせた柵。
什器(じゅうき)・・・日常使用する器具・家具類。
別盃(べっぱい)・・・別れを惜しんで飲む酒。別れのさかずき。
痴者(しれもの)・・・愚か者。ばか者。
忿怒(ふんぬ)・・・ひどく怒ること。
敢然(かんぜん)・・・思い切ってことをするさま。
鬨声(ときのこえ)・・・士気を鼓舞するために、多数の人が一緒に叫ぶ声。
跫音(あしおと)
総身(そうしん・そうみ)・・・からだ全体。
窺み視(ぬすみみ)
平明(へいめい)・・・わかりやすくはっきりしていること。またそのさま。
蓆(むしろ)・・・い・わらなどで編んで作った敷物。
衾(ふすま)・・・布などで長方形に作り、寝るときにからだに掛ける夜具。
齟齬(そご)・・・物事がうまくかみ合わないこと。食い違うこと。
撓直し(ためなおし)・・・曲がっているものを伸ばしてまっすぐに直す。
定法(じょうほう)・・・こういう場合はこうするものと、決まっているやり方。
下知(げじ)・・・上から下へ指図すること。
先途(せんど)・・・これから進む先。行き先。
譴責(けんせき)・・・しかり責めること。不正や過失などを厳しくとがめること。